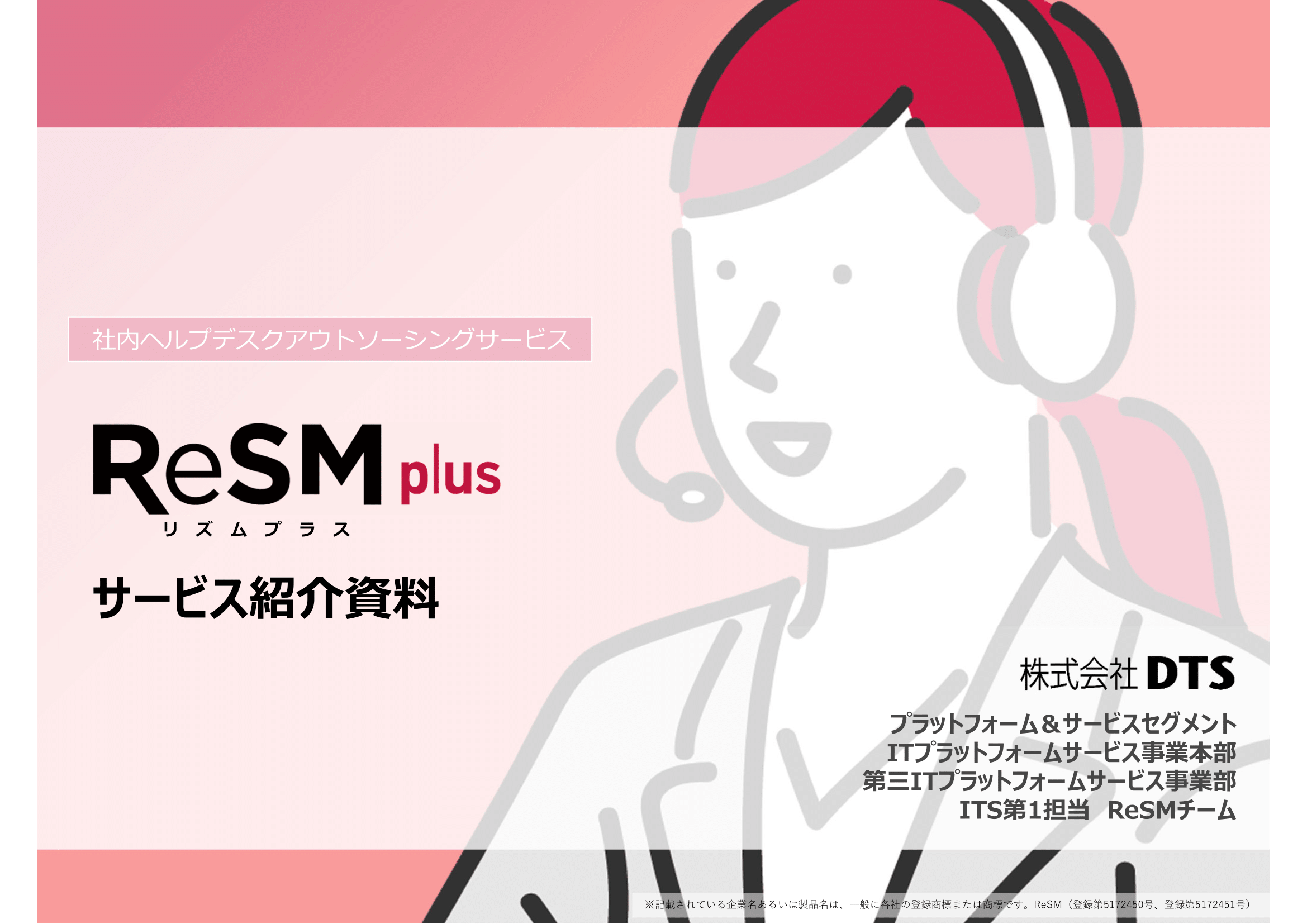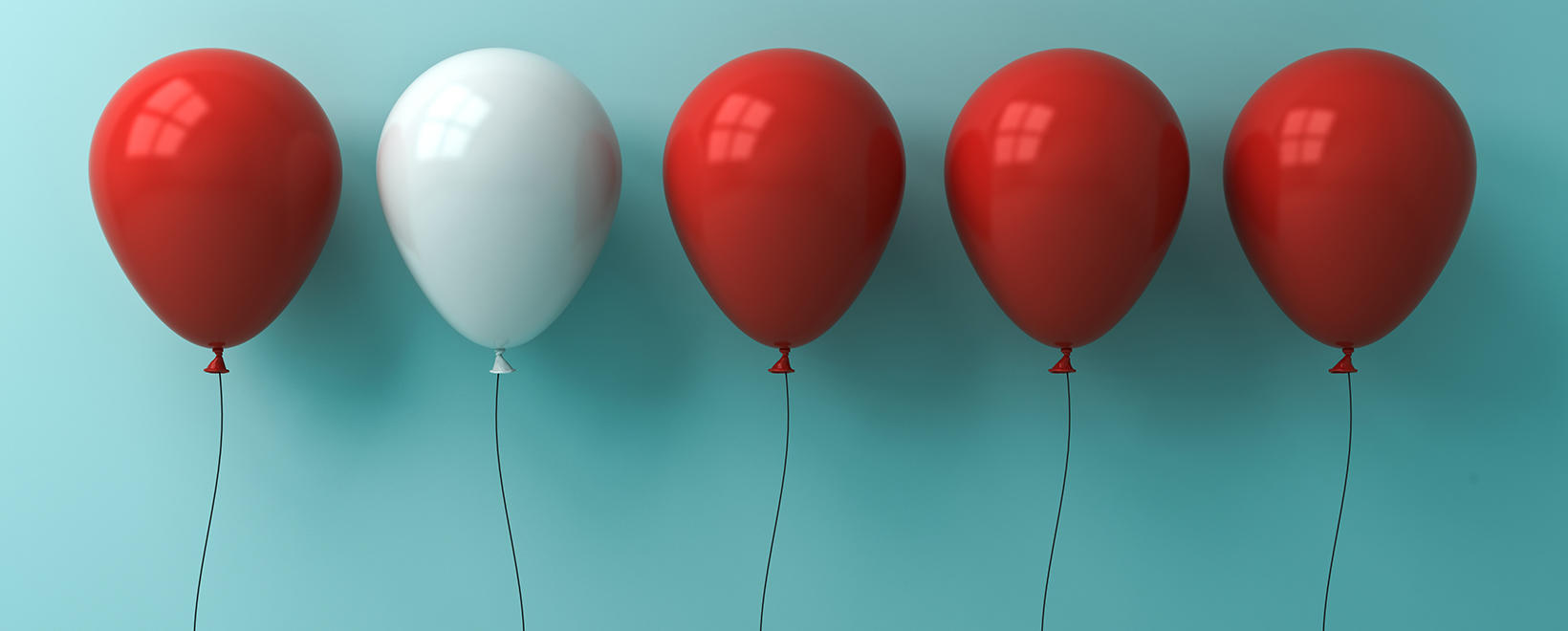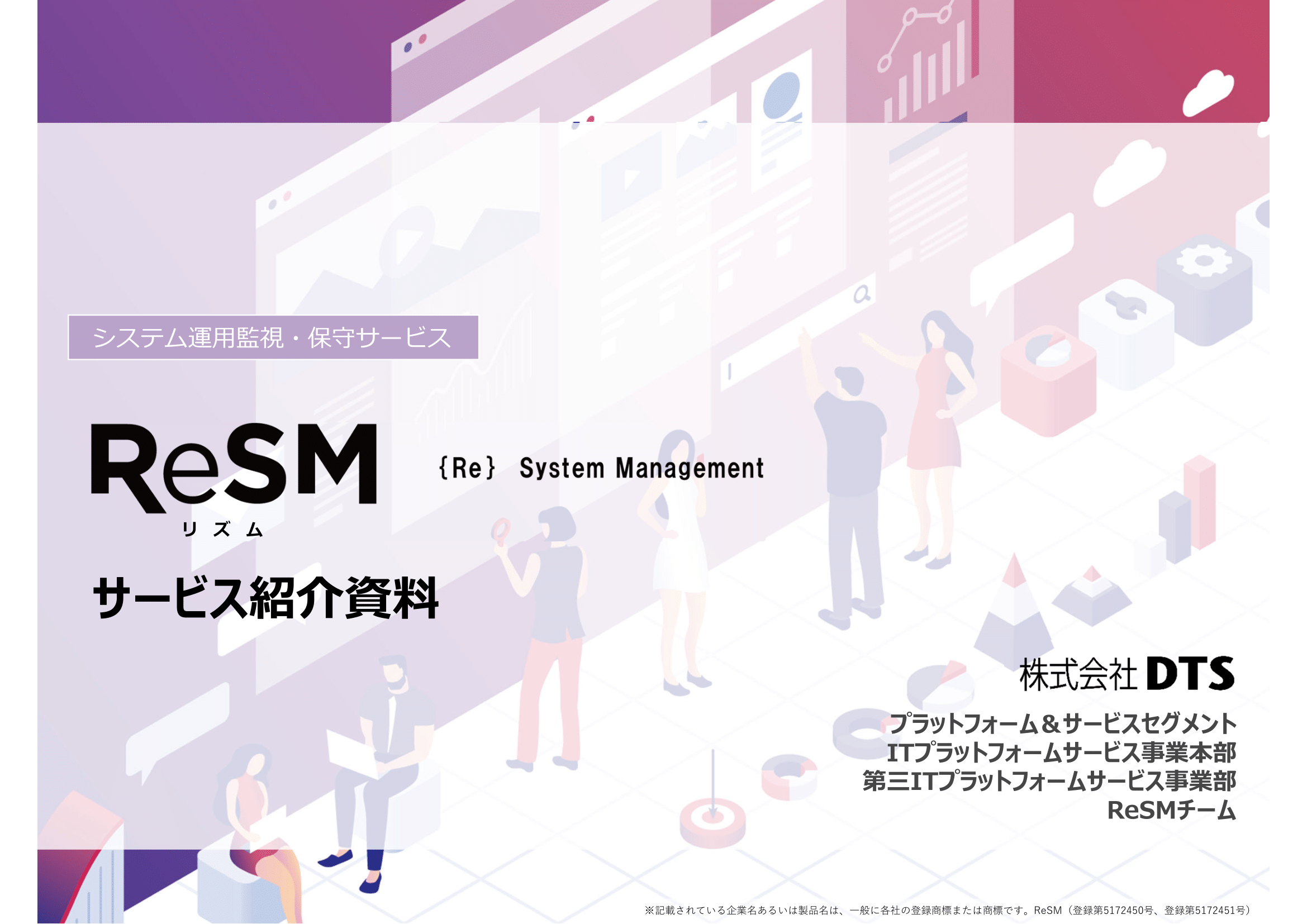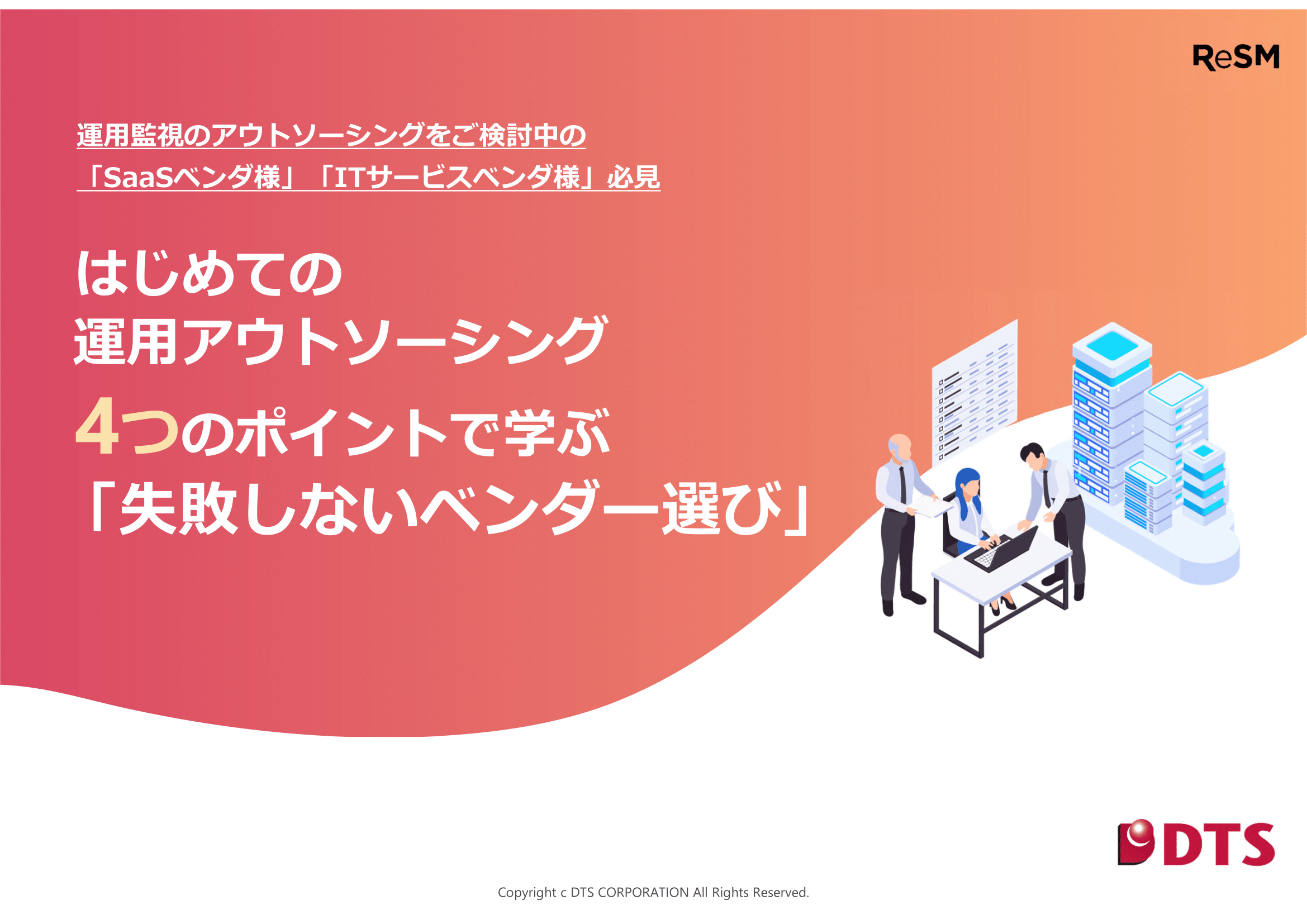社内向けのFAQシステムとは?機能や導入メリット、選び方、作成手順を解説

FAQシステムとは
FAQシステムとは、よくある質問(Frequently Asked Questions)とその回答を体系的に管理し、利用者が自己解決できる環境を提供する仕組みです。従来の紙マニュアルや単純なFAQページと異なり、検索機能・カテゴリ分け・分析機能・更新管理など、運用を支えるさまざまな機能を備えています。利用者は知りたい情報を即座に検索でき、担当者は同じ質問に繰り返し回答する負担を減らせる点が大きな特徴です。
たとえば、社内のITサポートにおいて「パスワードを忘れた場合の手続き」や「プリンターの設定方法」といった問い合わせは頻繁に発生します。これらをFAQシステムに登録しておけば、従業員は自分で検索して解決でき、担当者が都度対応する必要はありません。
結果として、顧客サポートの効率化や社内ナレッジの資産化が進み、問い合わせ対応コストの削減と顧客満足度の向上に直結します。
FAQシステムの定義と役割
FAQシステムは単なる「質問と回答の一覧」ではなく、利用者が自己解決できる環境を整えるための基盤です。利用者は24時間いつでも疑問を検索して解決でき、担当者は重複対応を避けて付加価値の高い業務に集中できます。
また、FAQの蓄積は企業のナレッジ資産となり、属人化を防ぎながら全社員が同じ情報にアクセス可能になります。特に社内FAQシステムでは、人事・IT・総務など部門横断的に知識を共有でき、業務効率化や新人教育の短縮に大きな効果を発揮します。
FAQシステムとFAQページ・チャットボットの違い
FAQページは、よくある質問を一覧形式で掲載した静的なコンテンツです。シンプルですが、質問数が増えると利用者が目的の回答を探すのが困難になり、更新作業の手間も大きくなります。
一方、FAQシステムは検索精度を高める機能やアクセス履歴分析、更新管理機能を備えており、大規模なナレッジ運用に適しています。また、近年はチャットボットとの併用も一般的です。
チャットボットは会話形式でユーザーをナビゲートする一方で、回答の正確性は背後にあるFAQデータの品質に依存します。FAQシステムと連携することで、チャットボットの回答精度が高まり、検索性と利便性を両立できます。利用目的や対象ユーザーに応じて、FAQページ・FAQシステム・チャットボットを適切に組み合わせることが効果的です。
FAQシステムの主な活用シーン
FAQシステムは、社外向け・社内向け・コールセンター向けなど多様な場面で活用されています。
▪️社外向け
顧客が自己解決できる仕組みを整えることで問い合わせ数を削減し、サポート体制の強化につながります。たとえばECサイトで「配送状況の確認方法」や「返品手続き」などをFAQ化することで、顧客は待ち時間なく解決でき、満足度が向上します。
▪️社内向け
社内向けでは、従業員からの問い合わせ対応の効率化に効果を発揮します。人事・総務・IT部門などに集中しやすい質問をFAQ化すれば、従業員は自分で情報を探し、担当者の工数を削減できます。新人や異動者でも同じ水準の情報にアクセスできるため、教育コスト削減にも寄与します。
▪️コールセンター向け
コールセンターではオペレーター支援として活用されます。FAQシステムにより、オペレーターは回答を瞬時に検索でき、対応時間短縮と品質均一化を実現できます。新人でも一定の品質を担保できるため、教育・研修コスト削減にもつながります。
このように、利用場面を明確にすることで、自社に最適なFAQシステムを選びやすくなります。
FAQシステム導入のメリット
FAQシステムを導入する最大の価値は「問い合わせ対応の効率化」と「顧客・従業員の自己解決支援」にあります。繰り返し発生する定型的な質問をFAQ化することで、担当者の負担を減らし、顧客は待ち時間なく解決できるようになります。
さらにナレッジを一元管理することで属人化を防ぎ、組織全体の対応品質を均一化できる点も大きな強みです。
ここでは導入効果を4つの観点から整理します。
| FAQシステム導入のメリット |
|---|
| 問い合わせ件数・対応工数の削減 |
| ナレッジの一元管理と属人化防止 |
| 顧客満足度・サービス品質の向上 |
| 業務時間外にも自身で問題解決を図れる |
問い合わせ件数・対応工数の削減
FAQシステムを導入すると、利用者が24時間365日アクセスできる自己解決環境が整います。
例えば、IT部門に多い「パスワード再設定」「システムエラーの初期対応」などは、FAQシステムに登録しておくだけで自己解決率が上がります。コールセンターでも「注文状況確認」「配送日程の変更」といったよくある問い合わせは自動的に減り、応対の効率化が可能です。
FAQシステムの最大の導入効果は、繰り返し発生する同様の問い合わせを大幅に減らせる点です。利用者が24時間365日FAQを参照できるようになれば、わざわざ担当部署に電話やメールをする必要がなくなります。その結果、担当者は単純な問い合わせ対応に追われることなく、付加価値の高い業務へ集中できるようになります。
この削減効果は単なる工数削減にとどまらず、顧客満足度や従業員満足度の向上にも直結します。
ナレッジの一元管理と属人化防止
FAQシステムを導入することで、ナレッジを一元的に管理できるようになります。従来、担当者ごとに異なる対応をしてしまったり、特定の社員に知識が偏る「属人化」が課題になりがちでした。FAQシステムでは、情報を共通のデータベースに集約し、誰が対応しても同じ水準の回答が可能になります。
また、更新履歴やバージョン管理機能により、常に最新の情報を提供できる点も強みです。これにより、新人や異動者でも短期間で業務に適応でき、教育コストの削減にもつながります。組織全体のナレッジを資産化し、長期的な業務品質の安定を実現します。
顧客満足度・サービス品質の向上
FAQシステムは、顧客体験の改善にも直結します。顧客は疑問が生じた際、すぐに回答を得られることを期待しています。顧客にとって「すぐに回答が得られる」ことは、満足度に直結します。FAQシステムがあれば、待ち時間を大幅に削減し、即時に正確な情報を提供できます。
さらに、一貫性のある回答が提示されることで、企業に対する信頼感が高まります。たとえば、製品利用に関するトラブル時でもFAQで即時解決できれば、顧客は安心感を得られ、企業への信頼度も向上します。スピードと正確さを兼ね備えた対応は、リピーター増加やブランド価値の強化につながります。
業務時間外にも自身で問題解決を図れる
従来の問い合わせ窓口は営業時間に制約があり、顧客が疑問を解決できるのは平日昼間に限られていました。FAQシステムを導入すれば、24時間365日、顧客や従業員が自己解決できる環境を提供できます。これは特にグローバル展開している企業や24時間サービスを求められる業界で大きなメリットとなります。
例えば、ECサイトの購入者が深夜に「注文履歴の確認方法」を知りたい場合、FAQシステムにアクセスすれば即座に解決できます。担当者が不在でも一定水準のサポートを提供できることで、顧客満足度を高めつつ、サポート体制を補完することが可能です。
FAQシステム導入のデメリット
FAQシステムは多くのメリットをもたらしますが、導入や運用にあたってはいくつかの課題や注意点も存在します。システム導入を成功させるには、こうしたデメリットを理解し、あらかじめ対策を講じることが重要です。
ここでは代表的な4つの課題を整理します。
| FAQシステム導入のデメリット |
|---|
| 初期構築・運用に工数がかかる |
| 利用者が定着しない可能性 |
| コンテンツの鮮度維持が課題 |
| 導入コストや運用費用が発生する |
初期構築・運用に工数がかかる
FAQシステムは単に導入すれば効果が出るわけではなく、質問・回答データの整備が不可欠です。過去の問い合わせ履歴を精査し、よくある質問を整理して登録する作業には大きな工数がかかります。さらにカテゴリ設計や検索キーワードの最適化なども必要で、準備不足のまま公開すると「使いづらいFAQ」として定着率が下がるリスクがあります。
例えば、IT部門にFAQを導入する場合、これまでの問い合わせ履歴を精査し「頻度の高い質問」「解決に時間がかかる質問」を優先的に登録する必要があります。初期工数は大きな負担ですが、既存のナレッジやテンプレートを活用すれば効率的に進めることが可能です。準備段階をしっかり整えることで、導入後の効果を最大化できます。
利用者が定着しない可能性
FAQシステムは導入しても、利用者に活用されなければ意味がありません。FAQが検索しづらかったり、UI/UXが使いにくいと、結局利用者は従来通り電話やメールで問い合わせてしまいます。この場合、問い合わせ件数削減という本来の目的を達成できません。
利用者に定着させるためには、検索精度やデザインの改善に加え、利用促進の周知活動も欠かせません。社内FAQであればイントラネットやチャットツールと連携させて自然に利用できる導線を作り、社外FAQであれば公式サイトや問い合わせフォームにFAQへのリンクを設けるなどの工夫が必要です。運用初期には利用促進の周知や教育を行い、習慣化をサポートする施策が求められます。
コンテンツの鮮度維持が課題
FAQシステムの価値は「常に最新かつ正確な情報を提供できること」にあります。しかし一度登録したFAQが放置されると、情報が古くなり誤回答や不満につながります。特に製品仕様や社内ルールが頻繁に変わる業界では、更新作業が継続的な負担となりやすい点がデメリットです。
解決策としては、定期的なレビューと改善サイクルを確立し、FAQの鮮度を維持する仕組みを整えることが重要です。責任者を明確にし、アクセス数や検索ワードをもとに更新対象を優先付けすれば、効率的な運用が可能です。FAQシステム自体に分析機能が備わっていれば、利用状況を把握しながら改善を進められます。
導入コストや運用費用が発生する
FAQシステムは無料のオープンソースや簡易的なクラウドサービスも存在しますが、本格的に活用するには有料サービスを導入したするコストが必要です。クラウド型の場合は月額利用料、オンプレミス型では初期投資や保守費用がかかります。さらに、利用規模の拡大や追加機能導入に伴ってコストが増える点も注意が必要です。
そのため、FAQシステム導入にあたってはROI(投資対効果)を意識することが欠かせません。単純にコスト削減効果だけでなく、顧客満足度向上や業務効率化といった定性的なメリットも含めて評価し、計画的に投資判断を行う必要があります。
提供方法ごとにみるFAQシステムの種類
導入形態は大きくクラウド/オンプレミス/オープンソースの3種。意思決定は主に「スピード(導入までの時間)」「統制(データ管理・セキュリティ)」「拡張性(カスタマイズ・連携)」のトレードオフで整理できます。まずは要点を比較表で俯瞰し、その後に各タイプの具体像を深掘りします。
| 観点 | クラウド型 | オンプレミス型 | オープンソース |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 低〜中 | 高 | 低(導入工数は中〜高) |
| 導入速度 | 最速(週〜月) | 遅め(月〜) | 中(体制次第) |
| カスタマイズ | 中(ベンダー範囲内) | 高 | 高(自社開発力依存) |
| セキュリティ/統制 | ベンダー標準準拠 | 自社ポリシーに最適化 | 自社設計次第 |
| 保守 | ベンダー主導 | 自社担当 | 自社/コミュニティ |
| 連携(CRM/CTI等) | 主要連携の用意が豊富 | 既存基盤に密連携可 | API次第で柔軟 |
| ロックイン | 中(移行計画必須) | 低〜中(契約形態依存) | 低(コード保有) |
| 向く組織 | 早期効果を狙う部門 | 統制・厳格審査が必要 | 技術力で差分化したい |
クラウド型FAQシステムの特徴
クラウド型FAQシステムは、インターネット経由でサービスを利用する形態で、近年最も多く採用されています。
最大の特徴は、初期費用を抑えつつ短期間で導入できる点です。システムの保守やバージョンアップ、セキュリティ対応は提供ベンダーが行うため、運用負担が軽く、社内に専門エンジニアがいなくても利用できます。
一方で、インターネット接続が必須であるため、ネットワーク障害や外部環境に依存するリスクもあります。また、ベンダーが提供する機能に制約があるため、自社特有のカスタマイズには限界がある点も押さえておくべきです。
とはいえ、中小企業から大企業まで幅広く活用されており、スピード感を重視する企業には最適な選択肢です。
オンプレミス型FAQシステムの特徴
オンプレミス型FAQシステムは、自社のサーバー環境にシステムを構築する方式です。
セキュリティポリシーや業務要件に合わせた高度なカスタマイズが可能で、既存の社内システムとの統合もしやすい点が強みです。特に、金融や医療など厳格なセキュリティ要件が求められる業界では、オンプレミス型が選ばれるケースが多く見られます。
ただし、導入にはサーバー購入や環境構築といった初期コストが発生し、システム保守・アップデートも自社で行う必要があります。そのため、運用負担はクラウド型に比べて大きくなります。
長期的にはライセンス費用が一定であるため安定運用が見込めるものの、運用体制をしっかり整えられる企業向けといえるでしょう。
オープンソースFAQシステムの特徴
オープンソース型FAQシステムは、ソースコードが公開されているシステムを自社環境に導入する方式です。
ライセンス料が不要または低コストで利用でき、自由度の高いカスタマイズが可能です。UIの変更や独自機能の追加など、自社のニーズに合わせて柔軟に対応できる点が大きな魅力です。
一方で、導入や保守には自社での技術対応が求められます。トラブル発生時も自力で解決しなければならないため、エンジニアリソースが不足している企業にはハードルが高い選択肢です。また、コミュニティベースのサポートに依存するケースも多く、企業向けに安定した運用を求める場合は注意が必要です。
技術力の高い企業や、費用を抑えて独自の仕組みを構築したい組織に適しています。
利用用途ごとにみるFAQシステムの種類
FAQシステムは導入目的や利用対象によって求められる機能が変わります。大きく分けると「社内向け」「社外向け」「コールセンター向け」の3タイプがあり、それぞれに特徴や導入メリットがあります。自社がどの利用シーンを重視するのかを明確にすることで、より適切なシステム選定が可能になります。
| 観点 | 社内向けFAQ | 社外向けFAQ | コールセンター向けFAQ |
|---|---|---|---|
| 主な対象者 | 従業員(IT・人事・総務など) | 顧客・利用者 | オペレーター |
| 解決したい課題 | 社内問い合わせの効率化、属人化防止 | 問い合わせ件数削減、顧客満足度向上 | 応対品質の均一化、教育コスト削減 |
| 重視機能 | 権限管理、更新の容易さ、検索精度 | 高速検索、UI/UX、モバイル対応 | 高速検索、CRM/CTI連携、回答統一 |
| 効果のイメージ | 業務効率化・教育コスト削減 | 顧客体験の改善・ブランド価値向上 | 応対時間短縮・新人でも高品質対応 |
| 向いている組織 | IT・管理部門の負担軽減を狙う企業 | ECサイトや顧客サポートが多い業種 | コール数が多く教育負荷の高いセンター |
社内向けFAQシステムの特徴
社内向けFAQシステムは、従業員が日常業務で直面する疑問や手続きを自己解決できるようにする仕組みです。特にITサポート、人事、総務などに寄せられる定型的な問い合わせを効率化するのに役立ちます。
例えば「パスワード再設定方法」「複合機のエラー対応方法」「経費精算の手順」「福利厚生の利用条件」など、社員全員に共通する質問をFAQ化すれば、担当部門の負担を大きく軽減できます。さらに、権限管理や更新のしやすさが重要な評価ポイントとなり、情報をタイムリーに反映できる体制が不可欠です。
社内ナレッジが一元化されることで、新人教育や異動者の立ち上がりもスムーズになり、組織全体の生産性向上に寄与します。
社外向けFAQシステムの特徴
社外向けFAQシステムは、顧客やユーザーが製品・サービスに関する疑問を自己解決できるようにするための仕組みです。顧客が求めるのは「待たされずに、正確でわかりやすい回答を得ること」です。そのため検索性の高さやUI/UXのわかりやすさが、利用率と満足度を左右します。
例えばECサイトに導入すれば「注文状況の確認」「返品・交換の手続き」といった問い合わせがFAQで即時に解決でき、問い合わせ件数削減と顧客満足度向上を同時に実現できます。さらに、ブランド体験にも直結し、利便性の高さが企業イメージを向上させる要素になります。
コールセンター向けFAQシステムの特徴
コールセンター向けFAQシステムは、顧客対応を行うオペレーターを支援するために特化した仕組みです。オペレーターがFAQデータベースから迅速に回答を検索できることで、応対時間を短縮し、サービス品質を均一化できます。
特に新人オペレーターの教育効果が高く、FAQシステムを利用すれば経験が浅くてもベテラン同様の水準で対応可能になります。また、CRM(顧客管理システム)やCTI(電話システム)と連携すれば、顧客情報を踏まえたパーソナライズ回答が可能となり、より高度なサポートが実現します。
結果として、コールセンターの生産性向上と顧客体験の改善を両立できるのが大きなメリットです。
FAQシステムの主要機能
FAQシステムは、単に質問と回答を並べるだけの仕組みではありません。利用者がスムーズに自己解決できるようにし、運用担当者が継続的に改善できるよう、多彩な機能が搭載されています。代表的なものは「検索」「分析」「他システム連携」「AI活用」などで、近年は高度化・自動化が進んでいます。以下に主要機能を整理します。
| 機能カテゴリ | 主な内容 | 利用者メリット | 運用者メリット |
|---|---|---|---|
| 検索機能・キーワード補完 | 高速検索、サジェスト、誤字補正 | 欲しい情報にすぐ到達 | 検索導線の最適化で利用率UP |
| 分析・レポーティング | 検索語分析、未解決件数、閲覧数 | ニーズに合った情報を見つけやすい | 改善対象を定量的に把握 |
| 他システム連携 | CRM・チャットボット・社内ポータル・社内チャットツール | 一貫した体験、利便性向上 | 顧客対応や社内連携を効率化 |
| AI・機械学習 | 自然言語処理、意図理解、学習改善 | 曖昧な質問でも適切回答 | 回答精度を自動で高め運用負荷を軽減 |
検索機能・キーワード補完
FAQシステムの基本機能として最も重視されるのが検索機能です。利用者は疑問が生じたとき、キーワードを入力して即座に回答を探したいと考えます。そのため、検索速度や精度が利用体験を大きく左右します。
多くのFAQシステムには、入力途中で候補を表示するサジェスト機能や、誤字・表記揺れを補正する仕組みが搭載されています。これにより、利用者は曖昧な入力でも目的の回答にたどり着きやすくなります。例えば「パスワード変更」と「パスワード再設定」が混同されやすいケースでも、適切なFAQを表示できれば、自己解決率は格段に向上します。
分析・レポーティング機能
FAQシステムには、利用状況を分析して改善につなげる機能も備わっています。代表的な指標には「検索回数」「未解決の検索ワード」「閲覧数の多い質問」などがあります。これらを把握することで、利用者が本当に求めている情報や不足しているコンテンツを明確化できます。
例えば「VPN 接続 エラー」という検索が多いのに適切なFAQが存在しない場合、すぐに新規コンテンツを追加すべきだと判断できます。また、検索結果が利用されないケースを分析すれば、回答の表現改善やUIの見直しにも役立ちます。このようにデータを活用することで、FAQシステムは単なる情報提供ツールから「継続的に改善できるナレッジ基盤」へと進化します。
他システム連携(CRM・チャットボット等)
FAQシステムは、単独で運用するだけでなく、他システムとの連携によって真価を発揮します。代表例がCRM(顧客管理システム)やチャットボットとの統合です。顧客情報とFAQを結び付ければ、過去の問い合わせ履歴や顧客属性を踏まえた最適な回答を提示でき、顧客体験を大きく向上できます。
また、チャットボットと組み合わせることで、会話形式でFAQ検索を行えるようになり、利用者は自然なやり取りの中で問題を解決できます。FAQ活用の履歴は他部門でも活用可能で、商品改善やマーケティング施策にフィードバックすることも可能です。
社内向けFAQシステムの場合、チャットツールとの連携は効果的です。チャットツールで受けた質問・回答を自動でFAQシステムに登録するという仕組みを構築すれば、FAQの運用工数を格段に抑えることができます。
AI・機械学習機能
近年のFAQシステムでは、AIや機械学習の技術を取り入れた高度な機能が注目されています。自然言語処理を用いて質問意図を理解し、ユーザーの曖昧な問い合わせにも適切な回答を提示できるようになっています。
さらに、社内ドキュメントを学習して、RAGを活用した回答精度改善をする仕組みも普及しています。これにより、運用担当者が個別に改善作業を行わなくても、システムが自動的にFAQの精度を高めることが可能です。結果として、運用負荷を軽減しながら、利用者の満足度を高められる点が大きなメリットです。
FAQシステムの選び方
FAQシステムは多種多様な製品が存在し、機能や価格帯も幅広く展開されています。導入効果を最大化するためには、自社の利用目的や体制に合わせて最適なシステムを選定することが不可欠です。ここでは、選定時に押さえるべき主要なポイントを整理します。
| 評価観点 | 具体的チェック項目 | 重視するケース |
|---|---|---|
| 自社用途との適合性 | 社内利用か社外利用か、対象ユーザー層 | 利用目的が明確な場合 |
| 操作性・運用しやすさ | UIの直感性、更新のしやすさ | 担当者リソースが限られる場合 |
| 検索精度・UI/UX | 表示速度、カテゴリ設計、モバイル対応 | 顧客向けや利用率重視の場合 |
| セキュリティ・信頼性 | 暗号化、稼働率、障害対応体制 | 金融・医療など厳格な業界 |
| 導入・運用コスト | 初期費用、月額費用、拡張コスト | ROIを重視する場合 |
自社用途との適合性
まず重要なのは「自社がどのような用途でFAQシステムを導入するのか」を明確にすることです。社外顧客向けなのか、従業員向けの社内利用なのか、あるいはコールセンター支援なのかによって、求められる機能は大きく異なります。
例えば、社外向けであれば検索性やUIのわかりやすさが利用率を左右します。一方、社内向けでは情報更新のしやすさや権限管理機能が重視されます。コールセンターではCRMやCTIとの連携性が鍵となり、オペレーターの生産性向上に直結します。導入目的と対象ユーザーを明確にすることで、システム選定の精度が格段に高まります。
操作性・運用しやすさ
FAQシステムは導入後に継続的な運用が必要です。そのため「担当者がいかに簡単に操作できるか」「更新作業が効率的にできるか」が成功の分かれ目となります。UIが複雑で更新に時間がかかると、FAQの鮮度維持が難しくなり、利用者の満足度低下につながります。
理想的なFAQシステムは、コンテンツ追加や修正が直感的に行える管理画面を備えています。加えて、承認フローや履歴管理が標準搭載されていれば、組織全体で安心して運用を続けられます。
検索精度とUI/UXの質
FAQシステムの利用者にとって最も重要なのは「欲しい回答にどれだけ早くたどり着けるか」です。そのため、検索精度の高さや表示スピードは導入効果を左右する決定的な要素です。
さらに、カテゴリ設計やタグ機能を駆使して情報を整理し、ユーザーが迷わず回答にアクセスできる仕組みを整える必要があります。モバイル対応やアクセシビリティへの配慮も、近年では必須条件となっています。利用者がストレスなく使えるUI/UXを実現することが、定着率を高める最大のポイントです。
セキュリティ・信頼性
FAQシステムには顧客情報や社内機密が含まれるケースも多いため、セキュリティ対策は欠かせません。導入前にはデータの暗号化、アクセス制御、ログ監査といった仕組みが整っているかを確認する必要があります。
また、稼働率や障害対応の体制、さらには法規制や業界標準への準拠状況も重要です。特に金融、医療、公共機関などの業界では、システムの信頼性が導入可否を左右する決定要素となります。
導入・運用コスト
最後に、コスト面も慎重に検討すべきポイントです。初期費用だけでなく、月額費用や将来的な拡張に伴うランニングコストまで見通すことが重要です。
クラウド型では利用規模に応じて料金が変動する場合が多く、オンプレミス型では初期投資が大きい代わりにランニングコストが安定するケースもあります。無料トライアルや期間限定プランを活用し、費用対効果を実際に検証することをおすすめします。
FAQシステムの価格・費用相場
FAQシステムは提供形態や規模、機能によって価格帯が大きく異なります。無料で利用できる簡易的なツールから、数百万円規模の大規模システムまで幅広く存在するため、自社のニーズと予算を踏まえて選定することが重要です。ここでは「無料」「クラウド型」「オンプレミス型」に分けて費用感を整理します。
| 提供形態 | 費用目安 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 無料FAQシステム | 0円〜 | 利用人数・機能制限あり。サポートは限定的 | 小規模導入や試験運用 |
| クラウド型FAQシステム | 月額数万円〜50万円程度 | ユーザー数・機能に応じ課金。サポートやアップデート込み | 中小〜大企業。早期導入・スケール重視 |
| 業務可視化 | 初期数百万円〜+保守費 | 自社サーバーで運用。カスタマイズ自由度が高い | セキュリティ要件が厳格な企業、金融・医療など |
無料FAQシステムの特徴と制限
無料で利用できるFAQシステムやオープンソース製品は、導入コストを抑えたい企業や、試験的に運用を始めたいケースに適しています。基本的な検索機能や簡単なカテゴリ分けが利用でき、社内で小規模に運用する場合には十分活用できます。
ただし、無料プランには多くの場合「利用人数制限」「FAQ件数制限」「機能制限」が設けられています。さらに、サポート体制が弱く、トラブル発生時は自社で解決しなければならない点もリスクです。長期的・本格的に運用するには、機能面や信頼性に物足りなさを感じる場面が出てくるでしょう。
クラウド型の料金相場
クラウド型FAQシステムは月額課金が一般的で、ユーザー数や利用機能に応じて料金が決まります。小規模利用では月額数万円から利用可能であり、中堅〜大企業向けの高機能プランでは月額10万〜50万円程度が相場です。
料金体系は「基本料金+ユーザー単価」で計算されるケースが多く、上位プランに移行すると検索精度向上機能、分析機能、チャットボット連携などが利用できるようになります。導入前には、初期設定費用の有無や追加機能のコストも確認しておくことが重要です。
オンプレミス型の料金相場
オンプレミス型FAQシステムは、自社サーバーに構築するため初期費用が高額になりやすい特徴があります。サーバー購入や環境構築、ライセンス費用を含めると、数百万円規模の投資が必要となるケースも少なくありません。
さらに、定期的な保守契約やバージョンアップ費用も発生するため、ランニングコストを考慮した長期的な予算設計が求められます。ただし、運用が安定すれば月額費用が発生しない分、長期的にはコストを抑えられる場合もあります。セキュリティやカスタマイズ性を重視する企業には有力な選択肢です。
FAQシステム導入手順
FAQシステムを効果的に導入するには、単に製品を契約するだけでは不十分です。導入目的を整理し、要件定義から運用開始後の改善まで一連のプロセスを踏む必要があります。以下では、代表的な導入ステップを順を追って解説します。
①ニーズの特定と要件整理
最初のステップは「何のためにFAQシステムを導入するのか」を明確化することです。顧客向けの問い合わせ削減なのか、社内業務効率化なのかによって、必要となる機能や運用体制は大きく異なります。
例えば、社内向けであれば「権限管理」「更新のしやすさ」、社外向けであれば「検索性」「多言語対応」などが重視されます。また、IT部門、人事部門、カスタマーサポート部門など関係部署の意見を集約し、合意形成を図ることが成功の鍵となります。
②製品選定とトライアル
次に、要件に合致する製品候補を比較検討します。この段階では価格や機能だけでなく、運用負担やベンダーのサポート体制も評価対象に含めるべきです。
実際に導入する前には無料トライアルを活用し、操作性や検索精度、UIの使いやすさを確認します。特に「更新作業のしやすさ」や「利用者が直感的に検索できるか」は、カタログや説明資料では判断できないため、試用段階で必ずチェックすべきポイントです。
③質問・回答データの作成
FAQシステム導入で最も重要な工程の一つが「FAQコンテンツの準備」です。実際の問い合わせ履歴をもとに、頻度の高い質問や解決までに時間がかかる質問を優先的に登録します。
回答は簡潔かつ具体的に記載することが望ましく、冗長な説明はかえって利用者の理解を妨げます。また、用語の統一や図表の活用によって、読みやすく実用的なFAQを構築することが可能です。導入後も定期的な見直しを行い、鮮度を維持する体制が欠かせません。
④システム設定と公開
FAQデータが整ったら、システムの初期設定を行います。カテゴリ設計やタグ付け、権限設定を適切に行うことで、利用者がスムーズに情報へアクセスできる仕組みを作れます。
公開前には社内テストを実施し、検索精度やUI表示、アクセス権限が問題なく動作するかを確認することが重要です。公開後はアクセス状況や検索履歴をモニタリングし、初期段階での課題を早期に洗い出します。
⑤効果測定と改善サイクル
FAQシステムは「導入して終わり」ではなく、継続的な改善が不可欠です。検索履歴や未解決ワードを分析し、新たな質問を追加したり、表現を改善したりすることで自己解決率を高められます。
また、利用状況を定量的に可視化し、問い合わせ削減率や対応時間短縮効果をKPIとして測定することで、投資効果を検証できます。改善サイクルを確立することで、FAQシステムは単なる情報提供ツールから、組織のナレッジ資産を育てる仕組みへと進化します。
FAQシステム活用事例
FAQシステムは業種や利用目的によって効果の出方が異なります。他社の事例を知ることで、自社に導入した際の成果を具体的にイメージしやすくなります。ここでは「一般企業」「教育機関」「自治体」の3つのケースに分けて紹介します。
象印マホービン株式会社様の活用事例
炊飯ジャーや電気ポットで知られる象印マホービン株式会社では、社内システム部門が全国の社員から寄せられるIT関連問い合わせに対応していました。しかし、体制が特定のスタッフに依存しており、担当者不在時には業務が滞る「属人化」が大きな課題でした。
同社は2023年にFAQシステムと有人対応を組み合わせた「ReSM plus」を導入。過去8,000件の対応履歴をFAQ化し、問い合わせ状況や対応記録をポータル上で可視化することで、属人化しない安定した体制を短期間で構築しました。
導入後は、問い合わせ数が月200件から120〜150件へ減少し、約8割がFAQや代行対応で解決できるようになりました。さらに、対応進捗が可視化されることで「問い合わせ後に放置されている感」がなくなり、社員満足度も向上。FAQシステムによって「ナレッジの可視化」と「業務負担軽減」を同時に実現した好例といえます。
太陽石油株式会社様の活用事例
石油製品の製造・販売を行う太陽石油株式会社では、社内のシステム部門が全国拠点から寄せられるIT関連の問い合わせに対応していました。導入前はすべて電話対応で行っており、毎日数件〜十数件の問い合わせに追われ、時には半日近く工数を取られることもありました。また、記録が残らないため対応が属人的になり、同じ質問でも担当者によって回答が異なるという課題もありました。
2022年に「ReSM plus」を導入し、散在していた情報を270件のFAQに集約。さらに問い合わせ内容を自動的にFAQへ反映する仕組みを整え、ナレッジの最新性を維持できる体制を構築しました。
その結果、導入から1年で電話問い合わせが半減。社員はまずFAQを確認する習慣が根づき、自己解決率が大幅に向上しました。対応が統一化されたことで「同じ質問に同じ答えが返ってくる」状態が実現し、ユーザー満足度も改善。システム部のメンバーは問い合わせ対応に追われることなく、企画業務や本来のミッションに集中できるようになりました。
太陽石油の事例は「FAQシステムを核にした自己解決文化の醸成」によって、情シス部門の生産性と社員体験の両方を改善できる好例といえます。
株式会社JTBコミュニケーションデザイン様の活用事例
JTBコミュニケーションデザインは、MICE事業や観光施設の運営など多彩な事業を展開しています。同社ではエリアマネジメント部門が公共施設や観光案内所などの運営を担っており、拠点ごとに異なるIT環境での問い合わせ対応が課題となっていました。拠点によってOSやネットワークが異なるため、ヘルプデスクは複雑かつ属人的になり、担当者は半日かけて対応することもあったといいます。
そこで2020年に「ReSM plus」を導入。FAQシステムとヘルプデスクを一体でアウトソーシングできる点が決め手でした。導入は大型施設から段階的に進められ、最終的に全国43施設で利用可能に。ユーザーはまずFAQを検索し、解決しない場合のみヘルプデスクに問い合わせる仕組みとすることで、対応の標準化と効率化を実現しました。
導入効果として、定型的な問い合わせの多くがFAQで解決できるようになり、本社にエスカレーションされる件数は従来の半分に削減。現場のITリテラシーも向上し、担当者はDX推進などコア業務に注力できるようになりました。同社は「ReSM plusによる安定運用を自社ビジネスの武器にしていきたい」と評価しており、FAQシステムが事業競争力にも直結することを示す好例です。
教育機関での導入事例
大学や専門学校などの教育機関でもFAQシステムは有効です。例えば、授業履修登録や奨学金申請、施設利用に関する問い合わせは、毎年同じ内容が繰り返し発生します。ある大学ではFAQシステムを導入し、学生ポータルから24時間アクセス可能なFAQを提供しました。
その結果、学務課への問い合わせ件数が減少し、窓口対応の混雑が緩和されました。さらに、学生は時間や場所を選ばず情報を得られるようになり、利便性が向上します。更新頻度の高い情報も迅速に反映できるため、学生・教職員双方にメリットが生まれました。
自治体での導入事例
自治体においても、住民からの問い合わせを効率化する手段としてFAQシステムが注目されています。特に手続き案内や災害時の情報提供では迅速さが求められるため、FAQ化することで住民サービスの質を大きく改善できます。
ある自治体では「住民票の発行方法」「ごみ分別ルール」「災害時の避難情報」などをFAQ化し、公式サイトからアクセスできるようにしました。その結果、役所窓口の混雑が軽減されただけでなく、多言語対応により外国人住民への情報提供もスムーズになりました。住民からは「わざわざ役所に行かなくても解決できる」との声が多く寄せられ、行政サービスの信頼性向上に寄与しました。
FAQシステムの最新トレンド
FAQシステムは単なる問い合わせ集ではなく、近年はDXやCX(顧客体験)戦略の一部として進化しています。特にAIや外部連携の進歩により、従来の「検索型FAQ」から「対話型・予測型FAQ」への移行が進んでいます。ここでは代表的なトレンドを紹介します。
AIと機械学習の高度化
近年、FAQシステムにAI技術を取り入れるケースが急増しています。従来はキーワード検索に依存していたため、入力表現が異なると目的の回答が見つからないこともありました。しかし、自然言語処理(NLP)を搭載したシステムでは、ユーザーの質問意図を理解し、最適な回答を提示できます。
さらに、利用データを自動学習し、回答精度を継続的に改善する仕組みも普及しています。例えば「ログインできない」という曖昧な問い合わせでも、過去の検索傾向を学習して「パスワード再設定」「システム障害確認」など関連度の高い回答を優先的に表示できます。これにより、人手では対応しきれない大量の問い合わせも効率的に処理できるようになります。
マルチチャネル対応
従来のFAQシステムはWebページ中心でしたが、現在はWebサイトだけでなく、スマートフォンアプリ、LINEやSlackといったチャットツールなど、複数のチャネルで展開されるケースが増えています。ユーザーは自分が使い慣れたチャネルからアクセスできるため、利便性が飛躍的に向上します。
さらに、チャネルごとにUIや検索体験を最適化する取り組みも進んでいます。例えばモバイルアプリではシンプルなUI、チャットツールでは自然な会話形式でFAQを利用できるように設計され、顧客接点の拡大と利用率の向上につながっています。
動画・インタラクティブFAQ
テキスト中心だったFAQコンテンツも、多様な形式に進化しています。特に注目されているのが動画FAQです。複雑な手順や操作方法を文章だけで説明するのは難しく、利用者も理解しにくいケースがあります。動画を用いれば、視覚的に分かりやすく伝えることができ、理解度と満足度を大幅に高められます。
また、インタラクティブFAQとして、ユーザーが選択肢を選びながら最適な回答にたどり着ける仕組みも登場しています。従来の検索型と比べ、利用者の操作体験を向上させる新しいアプローチです。こうしたコンテンツ形式の多様化は、今後ますます一般化していくと考えられます。
問い合わせ数の削減を目指すサービス「ReSM plus リズムプラス」
ReSMplusは単なるFAQシステムではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指す支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。
数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。
- FAQシステムに留まらず、問い合わせ代行も行い、貴社だけのナレッジ資産をつくる
- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る
それぞれの特徴についてご紹介していきます。
FAQシステムに加えて有人対応を代行し、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。
FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。
SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。
その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。
パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…
こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。
業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。
まとめ
FAQシステムは、単なる「質問と回答の一覧」ではなく、問い合わせ対応の効率化と顧客・従業員の自己解決を支援する戦略的な仕組みです。検索機能やナレッジの一元管理によって属人化を防ぎ、業務工数を削減できるだけでなく、迅速で一貫した回答を提供することで顧客満足度やサービス品質の向上にも直結します。
この記事の著者
近い課題のコラムを見る
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。