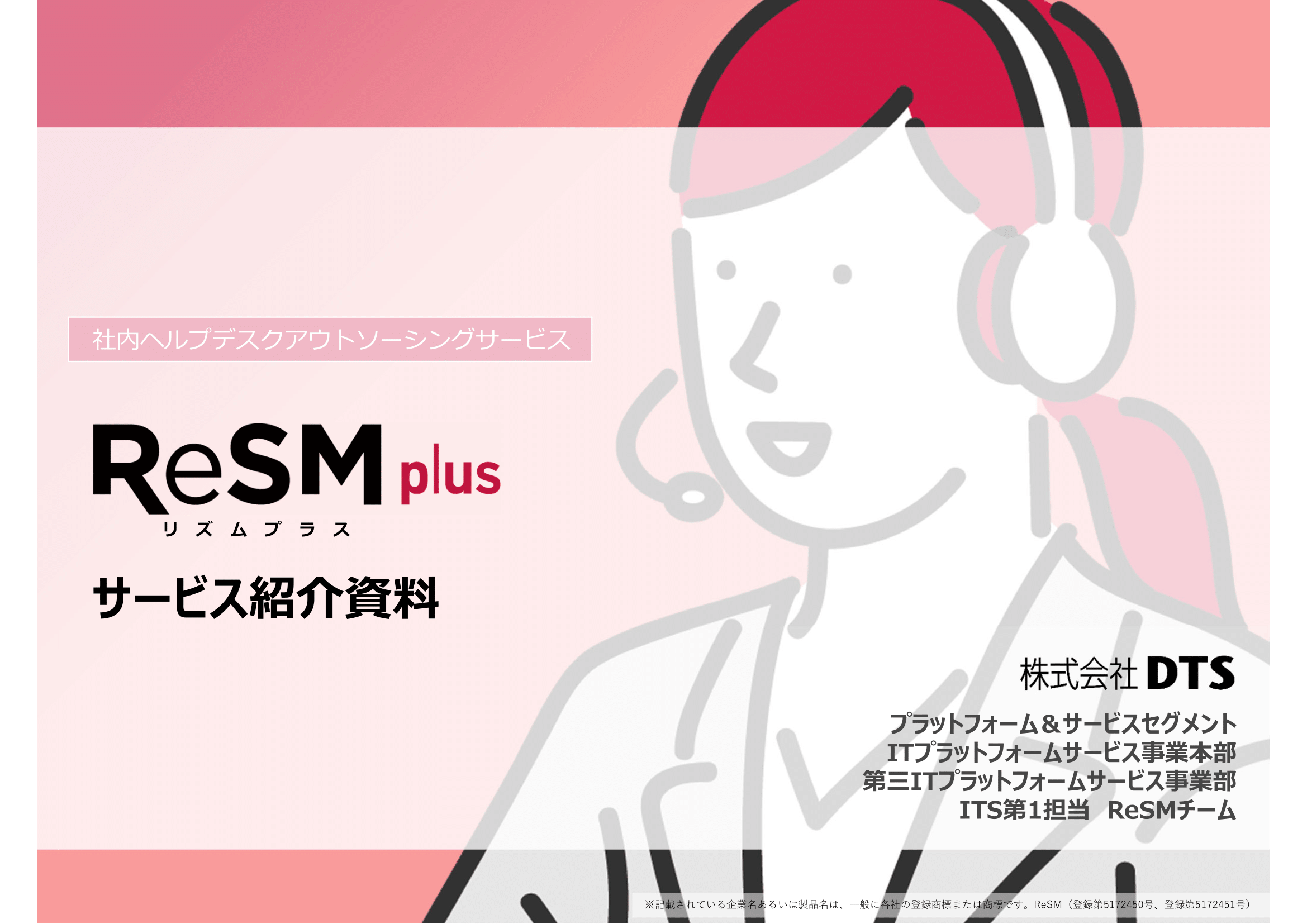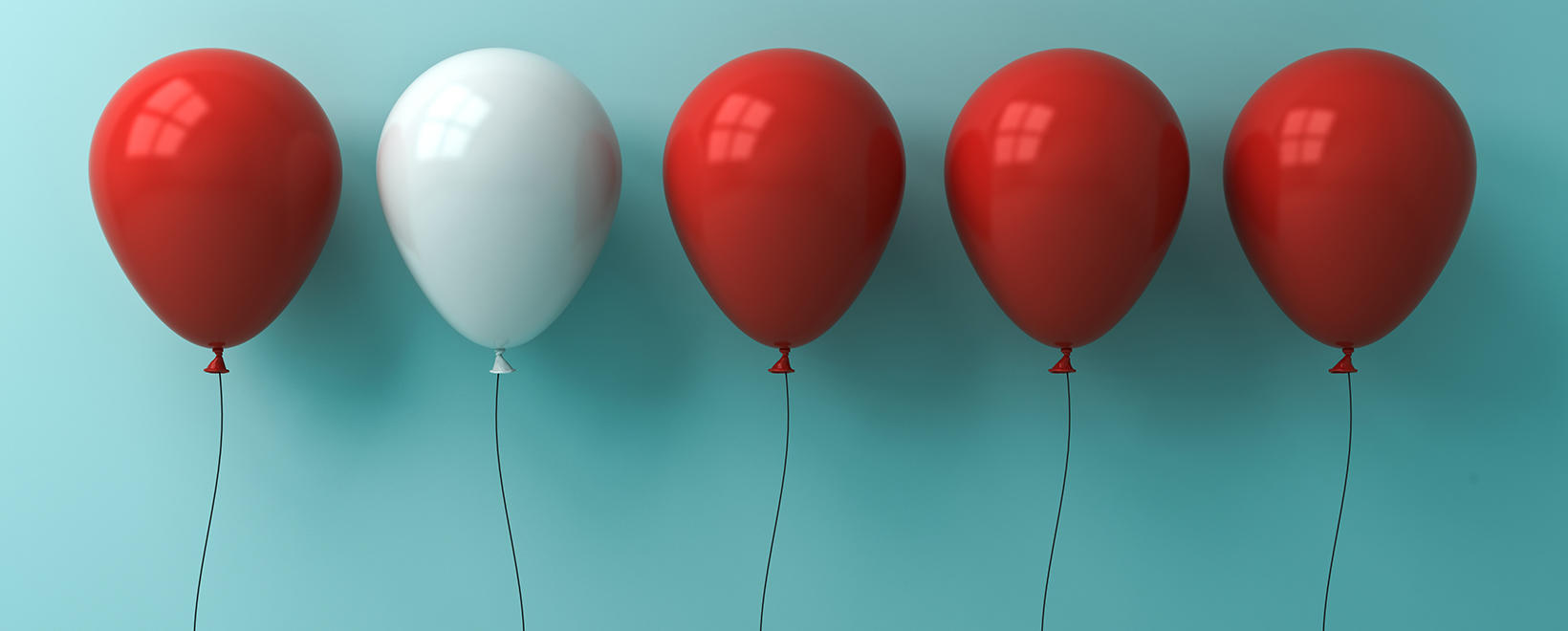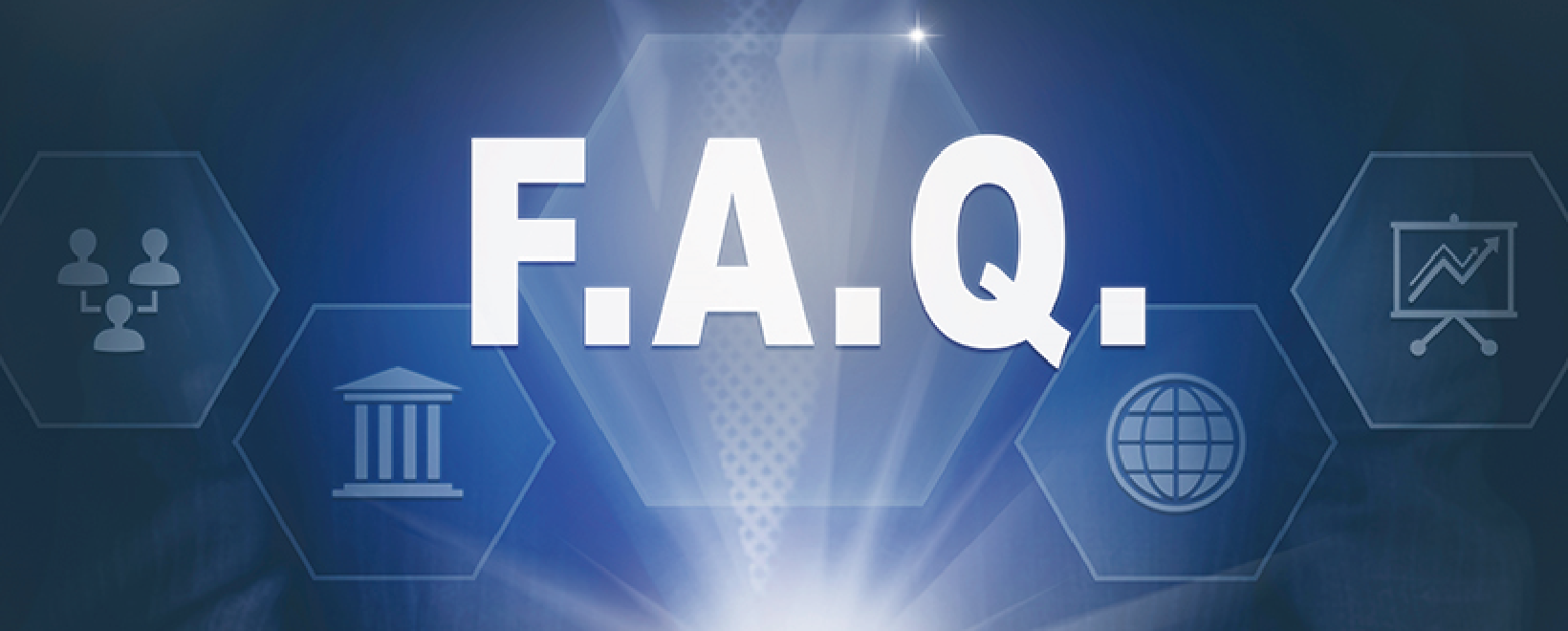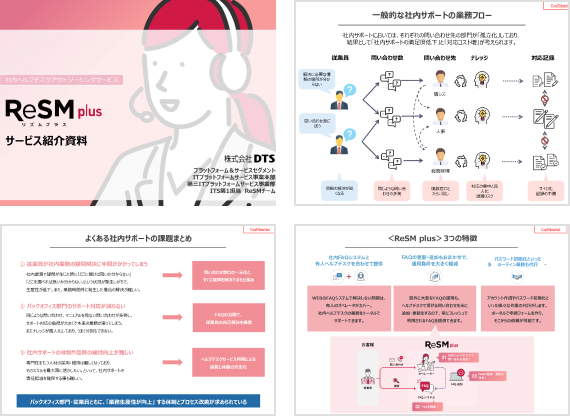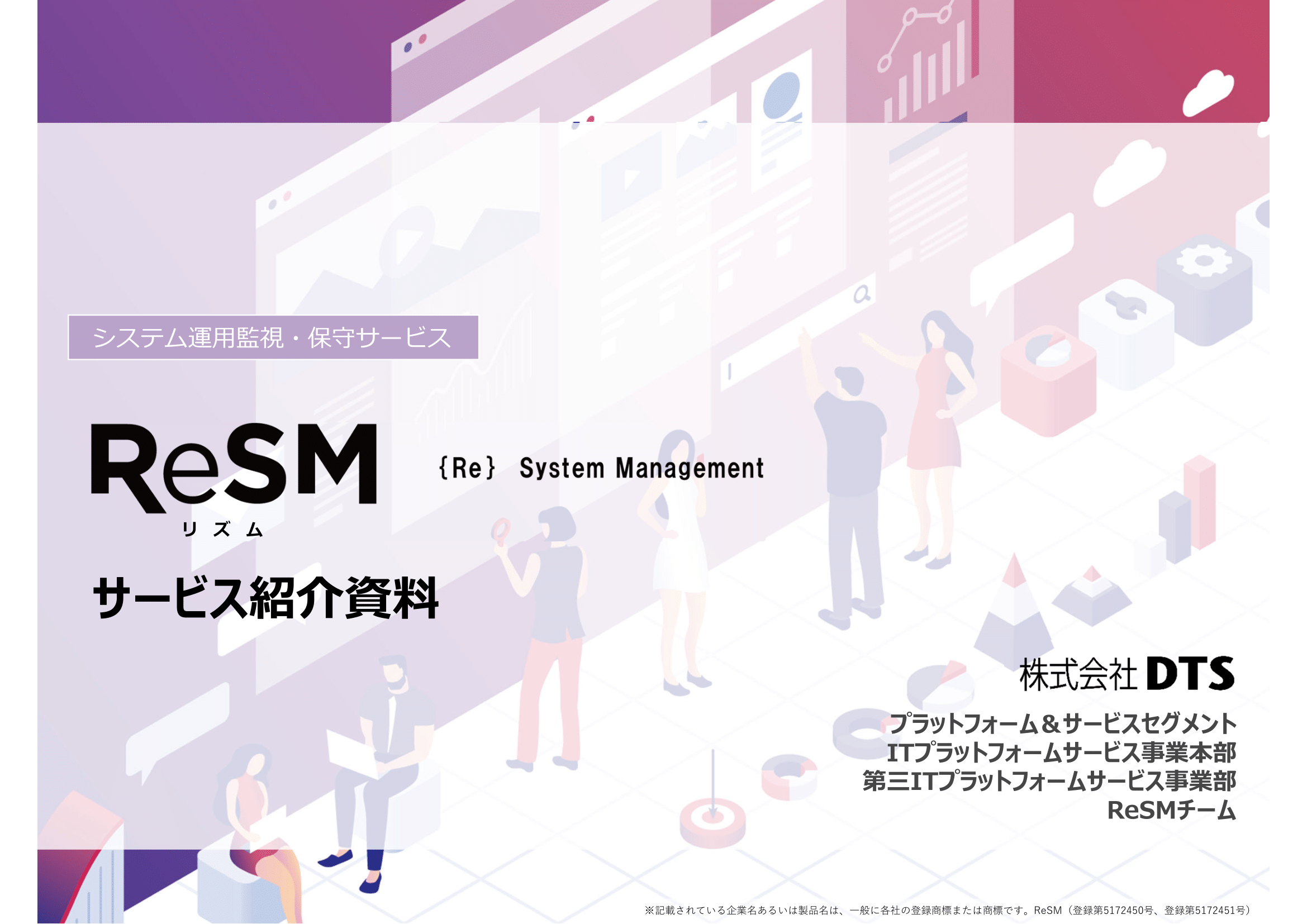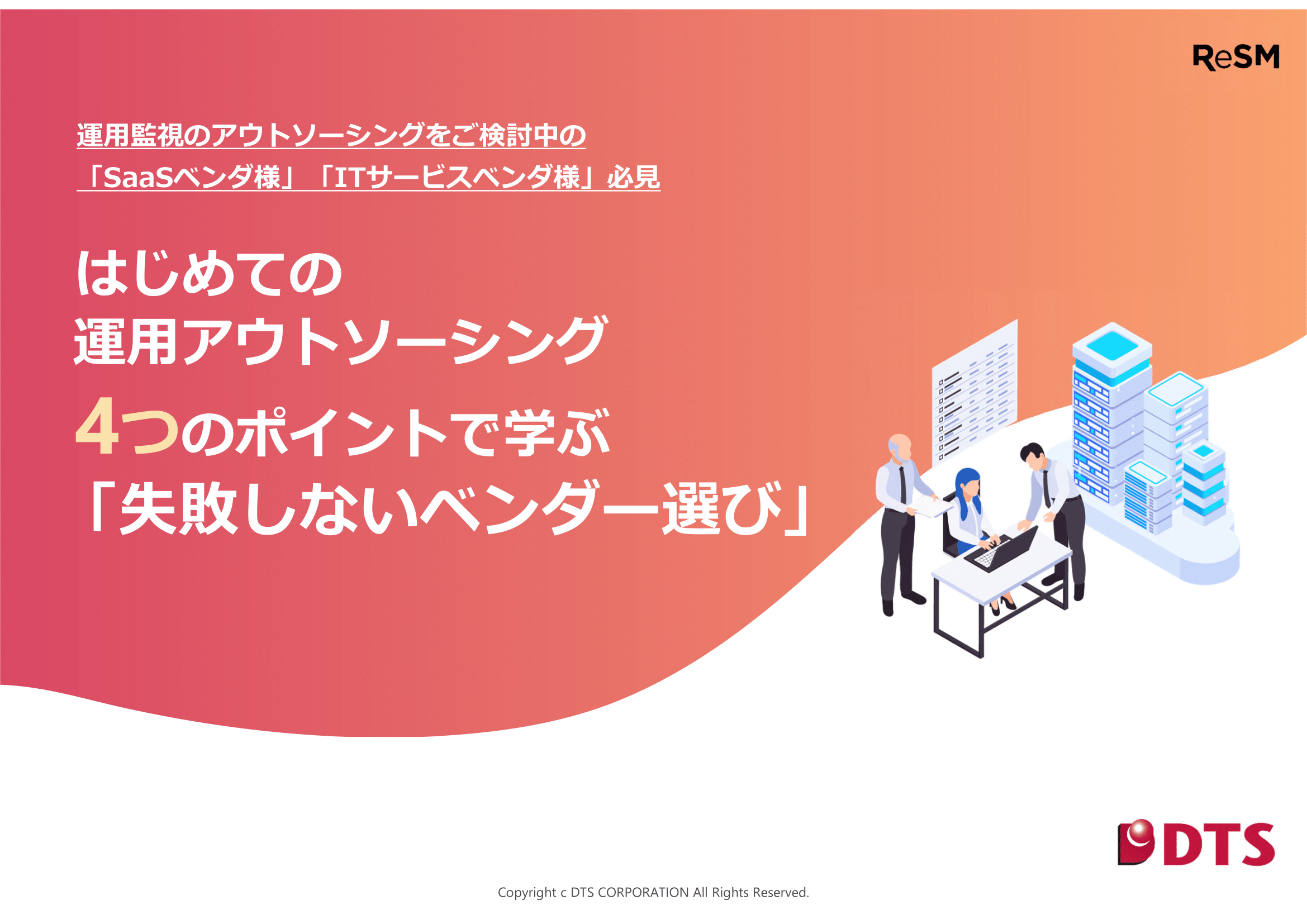どうやって選べばいい?社内問い合わせシステムやツールの選び方|おすすめのタイプや注意点も解説
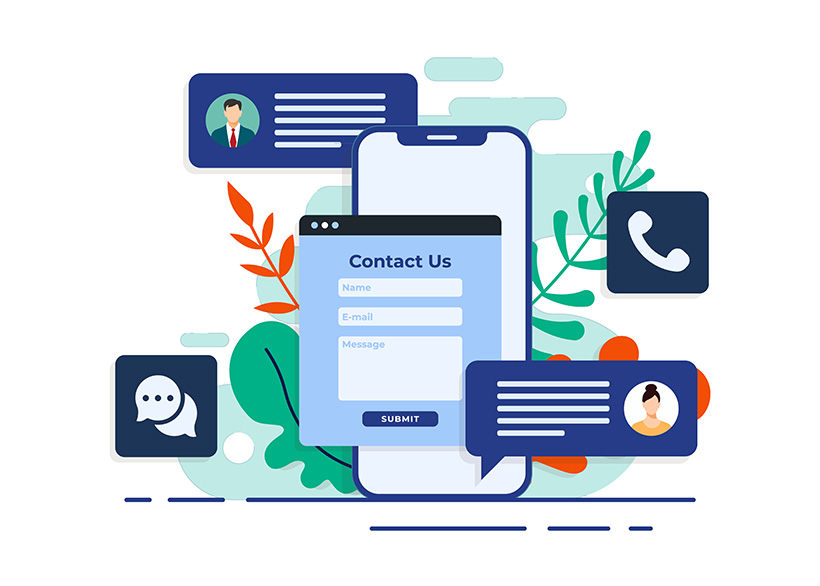
会社のシステム部門やバックオフィス部門が、社内の問い合わせ対応でリソースが圧迫されてしまうケースは少なくありません。問い合わせ対応の負担にお悩みなら、社内問い合わせに対応するシステム・ツールの導入がおすすめです。
本記事では、社内問い合わせシステム・ツールの種類や、社内問い合わせ対応の効率化に効果的なシステム・ツールの選び方などを紹介します。
社内問い合わせ業務とは
社内問い合わせ業務とは、社内、つまり自社の従業員から寄せられる問い合わせに対応し、適切な回答を行うことです。例えば、システム部門には社内で導入しているITツールに関する内容、経理部門には経費精算に関する内容といったように、その部門の担当業務に関する問い合わせが社内から届きます。
よくある社内問い合わせ内容
社内からのよくある問い合わせ内容としては、次のようなものがあります。
- 情報システム部:「ツールの使い方が分からない」
- 人事労務部:「住所や給与振込口座を変更したい」
- 総務部:「◯◯に関して、社内規定がどうなっているか確認したい」
社内問い合わせを減らせない原因
社内問い合わせを減らせないのは、一体何が原因なのでしょうか。ここでは、社内問い合わせがなかなか減らない原因を解説します。
社内マニュアルやFAQが更新されない
社内からの問い合わせには、各部門のコア業務の合間を縫って対応するケースが一般的です。そのため、従業員向けに用意したマニュアルやFAQが、適切に更新されないことも多いでしょう。すると、社内マニュアルやFAQの運用が進まず、結果的に従業員からの問い合わせが増えてしまいます。
「聞いたほうが早い」と考える人が多い
社内マニュアルやFAQがあっても、分かりやすさや検索性が低いと、「自分で調べるより聞いたほうが早い」と思ってしまう従業員は少なくありません。結果的に、自分で調べようとせず、各部門に問い合わせる従業員が増加してしまいます。
問い合わせ窓口が不明確
問い合わせ先の担当部署やチャネルが複数存在すると、どこに連絡するべきか分からず、同じ内容の問い合わせがあちこちに寄せられるケースが少なくありません。担当部署が曖昧なままだと、問い合わせの重複や遅延が発生し、全体として件数が減らない要因につながります。
社内問い合わせ対応における課題
社内問い合わせ業務に対応する部署では、一体どのような課題を抱えているのでしょうか。以下で、詳しく解説します。
コア業務に集中できなくなる
社内からの問い合わせが増加すると、担当者がその対応に手一杯となり、各部門のコア業務に集中できなくなってしまいます。その結果、従業員の生産性が低下し、必要な業務が終わらないまま、残業時間の増加につながる可能性もあるでしょう。
業務が属人化しやすい
コア業務をこなしながら、多くの問い合わせに対応していると、対応マニュアルの整備やノウハウの共有も進みにくくなってしまいます。結果的に、詳しい知識を持つ従業員に業務が偏り、属人化が進んでしまうことになります。業務が属人化することで、担当者が退職した場合に、問い合わせ業務に関するノウハウやナレッジもなくなってしまうのも課題の1つです。
社内問い合わせ業務の効率化、問い合わせを削減する方法は?
ここでは、社内問い合わせ業務を効率化する方法について解説します。
自己解決の仕組みをつくる
マニュアルやFAQを作成していない場合は、まずはそこから着手しましょう。同じような質問が多い場合は、従業員が自己解決できるような仕組みをつくると、問い合わせ件数の削減につながります。情報は随時更新し、常に最新の情報に保つことが大切です。また、従業員にマニュアルやFAQの作成を周知し、使い方などをレクチャーしましょう。
マネジメント層やリーダー層に研修を実施する
問い合わせ件数を減らすためには、部署やチーム内で生じた疑問に、その場で対応できる体制を整えることも重要です。たとえば、各部門のマネジメント層やリーダー層にシステムの使い方のレクチャーを実施すれば、困りごとやトラブルに部署内で対応しやすくなります。
社内問い合わせシステム・ツールを導入する
FAQシステムや情報共有ツール、チャットボットなど、社内問い合わせ対応の効率化につながるシステム・ツールを導入することもおすすめです。問い合わせ対応をシステムに任せることで、各部門がコア業務に集中しやすくなるでしょう。
社内問い合わせシステム・ツールの選び方
社内問い合わせ業務の効率を上げるために、専門のシステム・ツールを導入するとします。選択の際、次の5つのポイントをおさえることが大切です。
ポイント1:導入目的を明確化する
社内問い合わせシステム・ツールの導入目的を明確化すれば、自社の課題に合うシステムやツールが見つかりやすくなります。社内問い合わせ対応において、何がネックになっているのか把握しましょう。
ポイント2:費用対効果について検討する
システムの導入にかかるコストと、期待される効果のバランスを検討することも大切です。導入後の効果については、現状と目標値を比較して検討するとよいでしょう。たとえば、現状の問い合わせ件数が月◯件なら、導入後は月◯件まで削減するといった目標値を設定して比較します。
また、問い合わせに対応する部門だけでなく、「疑問やトラブルをスムーズに解消できる」など、問い合わせをする部門のメリットも検討しましょう。
ポイント3:使いやすさを重視する
どんなに社内問い合わせシステム・ツールの機能が充実していても、使い勝手が悪かったり操作が難しかったりすると、従業員に利用してもらえなくなってしまいます。そのため、運営側、従業員側双方にとって、使いやすい社内問い合わせシステム・ツールを選びましょう。
ポイント4:ベンダーのサポート体制をチェックする
新しいシステムの導入期には、問い合わせ業務の担当部門でも混乱が生じやすいものです。社内問い合わせシステム・ツールのベンダー企業のサポート体制が充実していれば、導入期の業務負担を軽減できます。また、サポートの有無や内容だけでなく、費用についても確認しておくと安心です。
ポイント5:セキュリティ対策について確認する
問い合わせ対応のシステムでは、従業員の個人情報や会社の機密情報をやりとりする場合もあります。情報漏洩を防ぐためにも、社内問い合わせシステム・ツール側のセキュリティ強度を確認しておきましょう。
社内問い合わせシステム・ツール1「FAQシステム」
ここからは、社内問い合わせ対応に有効なシステム・ツールについてさらに深掘りします。まず、「FAQシステム」について詳しく解説します。
FAQシステムとは
FAQとは、よくある質問・回答をまとめた所謂「Q&A」のことです。FAQはエクセル(Excel)や社内サイトでも用意できますが、システム化することで検索機能などが使えるようになるため、非常に便利です。
FAQシステムを導入するメリット
FAQシステムを導入すれば、よくある問い合わせ内容とその回答を従業員に共有できます。問い合わせを受ける側だけでなく、従業員にとっても問い合わせる手間を削減できるという、メリットを得られます。自分のタイミングで気軽に疑問を解消できるため、従業員に使ってもらいやすいでしょう。データや図表なども表示できるため、チャットボットよりも多くの情報を提示できる点も魅力です。
社内問い合わせシステム・ツール2「情報共有ツール」
情報共有ツールも、社内問い合わせ対応に有効なツールの1つです。以下では、情報共有ツールについて詳しく解説します。
情報共有ツールとは
情報共有ツールとは、社内SNSやグループウェア、オンラインストレージなどを指します。従業員からの問い合わせ件数を減らすというよりも、主に問い合わせ対応部門内での情報共有のために用いられる点が特徴です。
情報共有ツールを導入するメリット
情報共有ツールの導入により、問い合わせ対応に関する情報をスムーズに共有すれば、業務の属人化を防げます。なかには情報ストックやナレッジ管理に特化したツールもあるため、問い合わせ対応の効率化を期待できるでしょう。
社内問い合わせシステム・ツール3「チャットボット」
チャットボットは、近年普及が進んでいる社内問い合わせシステムの1つです。ここでは、チャットボットについて解説します。
チャットボットとは
チャットボットとは、利用者と自動で会話するツールのことです。
チャットボットにはシナリオ型とAI型の2種類があります
| シナリオ型 | あらかじめシナリオを用意し、一問一答や選択分岐によって回答を提示する。 シンプルな質疑応答に向いている。 |
| AI型 | AIが質問者の意図を読み取って回答を提示する。 抽象的な質問に対しても回答しやすい。 |
社内問い合わせは「◯◯のときはどうすればよい?」といったシンプルな問い合わせが多い傾向があるため、基本的にはシナリオ型がおすすめです。
チャットボットを導入するメリット
チャットボットを導入すれば、従業員からの問い合わせに対してボットが自動で回答する仕組みを構築できます。営業時間外でも回答を得られるため、残業中や休日出勤中にも従業員の疑問を解消可能です。従業員にとっても、対応部署に問い合わせるよりも、気軽に疑問を解消できるというメリットがあります。
社内問い合わせシステム・ツールを導入する際の注意点
社内問い合わせシステム・ツールを導入する際は、いくつか気をつけたいことがあります。以下では、社内問い合わせシステム・ツールを導入する際に、注意すべきポイントを解説します。
担当者や管理ルールを定める
問い合わせ対応をすべてシステムに任せきりにしていると、いつの間にか回答に使用する情報が古くなってしまうことがあります。システムの担当者や管理ルールを定めて、情報が古くないか定期的に確認し、新しい情報にアップデートを行う体制を構築しましょう。
問い合わせ件数や内容などを管理・分析する
社内から多く寄せられる問い合わせ内容が分かれば、従業員がつまずきがちなポイントを把握できます。問い合わせ件数や内容を管理し、問い合わせが多いものから優先的に対応していくと、担当者の負担軽減にもつながるでしょう。また、蓄積されたデータは、属人化の解消や新規事業のヒントになることもあります。
従業員のITリテラシーを考慮する
機能が充実したシステム・ツールは、問い合わせを受ける側からすると心強い味方です。しかし、あまりに高度なシステムを導入すると、従業員が使いこなせない可能性もあります。従業員のITリテラシーを考慮して、誰でも簡単に扱えるシステムを選定することが大切です。
社内問い合わせ対応の効率化なら「ReSM plus(リズム プラス)」がおすすめ
社内問い合わせ対応の効率化をはかるなら、「ReSM plus(リズム プラス)」の導入をご検討ください。ReSM plusは、オペレーターによる対応とFAQシステムを組み合わせた、社内問い合わせ対応のアウトソーシングサービスです。
有人対応とFAQシステムで、万全の体制を構築
ReSM plusは、誰でも手軽に使えるFAQシステムで、自己解決のルートを整備しています。FAQで解決しなかった問い合わせにおいては、有人オペレーターが対応するため、問い合わせ担当者様の負担を軽減することが可能です。また、問い合わせの内容を記録し、FAQを適宜更新することで、ナレッジの蓄積やFAQの充実度アップにつながり、問い合わせの件数そのものを減らすことができます。
IT・バックオフィスの両方に対応
ReSM plusは、ITにもバックオフィスにも対応しているため、情報システム部門以外にもご活用いただけます。IT資産管理やシステム運用管理などのオプションも充実しており、お客様のご要望に合わせて選択可能です。
まとめ
社内問い合わせ業務は、通常業務の合間を縫って対応するケースが多く、担当者にとって大きな負担となってしまいます。社内問い合わせシステム・ツールを導入すれば、問い合わせ対応の効率化によりコア業務に集中しやすくなり、業務の属人化を防ぐことも可能です。
社内問い合わせシステム・ツールをお探しなら、ぜひ「ReSM plus(リズム プラス)」をご検討ください。ReSM plusなら、有人ヘルプデスク+FAQシステムの提供により、自己解決を促進しながら問い合わせ数の削減を実現可能です。
また、スクリプトやアプリケーションなど、専門知識がなくても利用可能な手軽さも魅力の1つです。ほかにも、問い合わせ内容を元にFAQを追加更新する仕組みにより、質問と回答の充実度を高められます。従業員様からの問い合わせに対応するだけでなく、改善・向上し続ける点が「ReSM plus(リズム プラス)の強みです。
ご興味のある方は、下記より資料をダウンロードのうえご確認ください。また、「他のサービスとどう違うの?」「そもそもFAQが社内になくて・・・」等々、社内ヘルプデスクに関するご相談もお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。
この記事の著者
近い課題のコラムを見る
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。