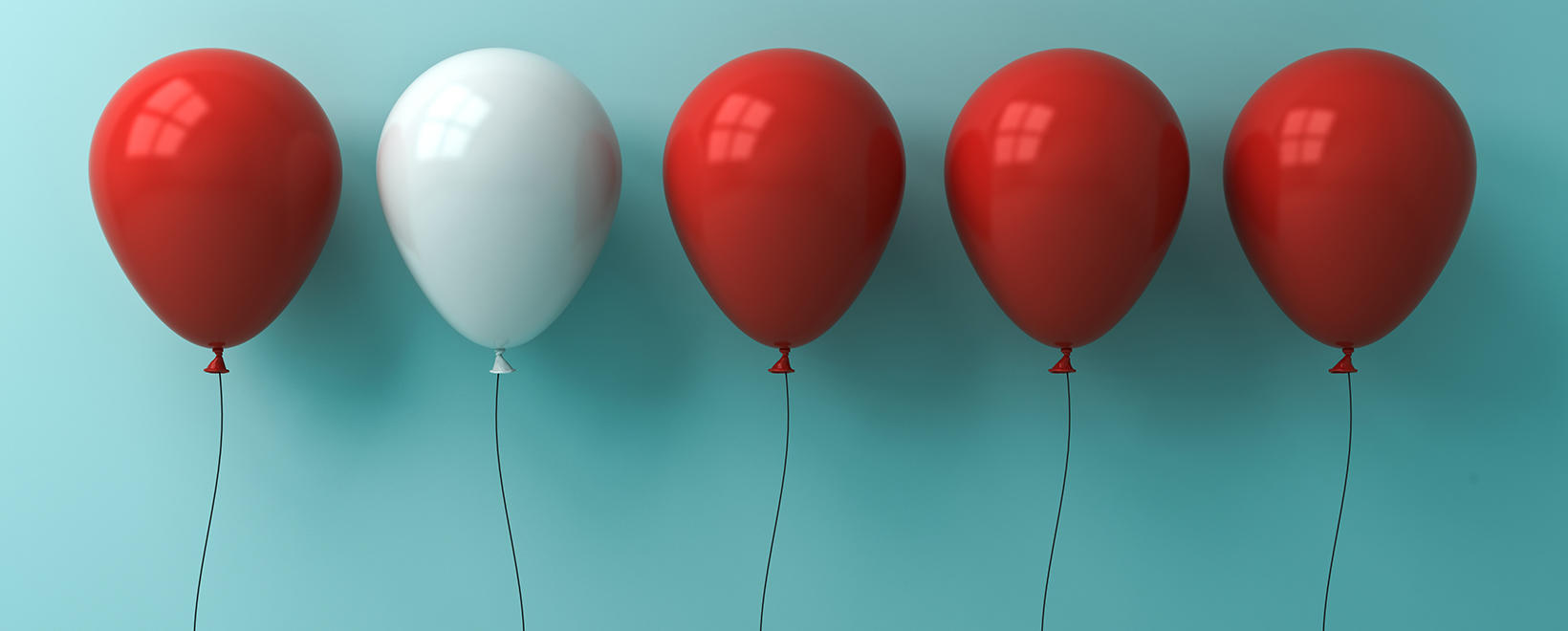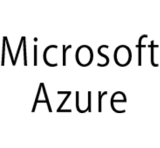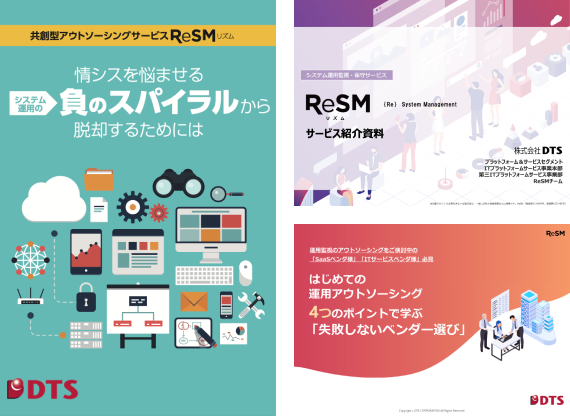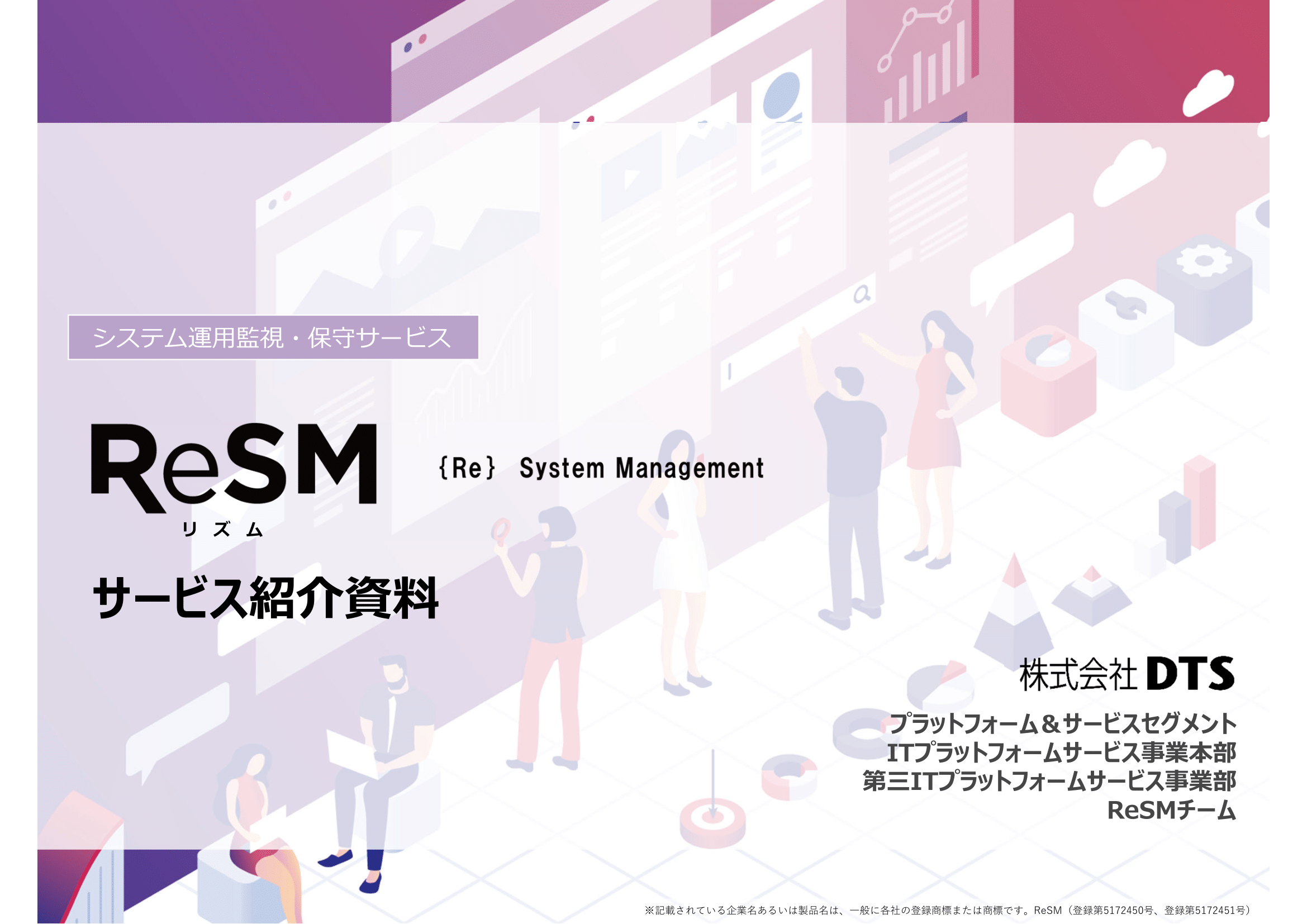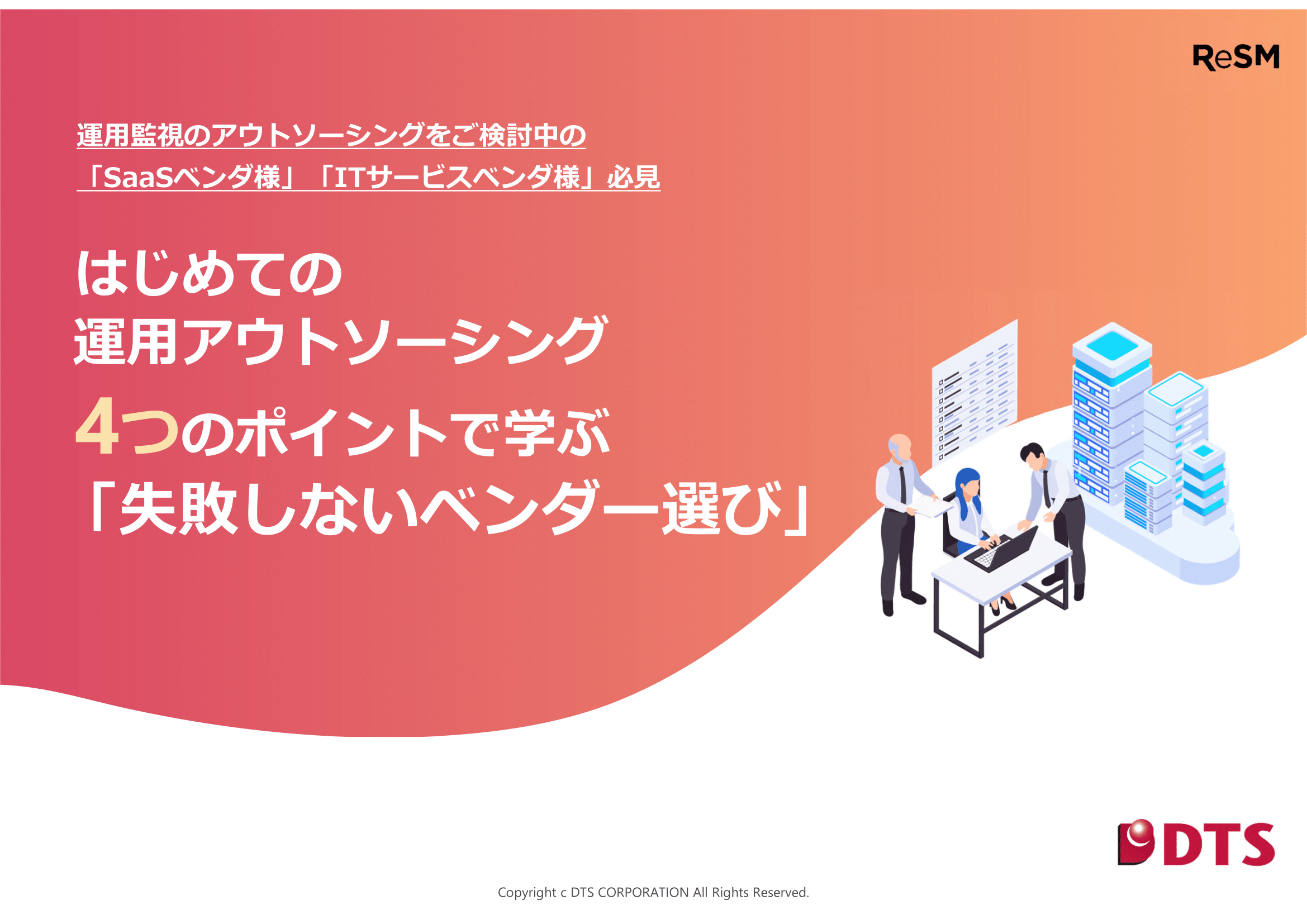システム運用8つの課題とその背景とは|課題解決策と運用改善のメリットも紹介

新規事業や事業の拡大を考える際に、システム運用部門が新たに発生する業務への対応できるかどうかが課題となる場合があります。システム運用部門の業務負荷が常態化し日々の業務に追われているため、新しいことを始めるどころではないという企業も少なくないでしょう。
本記事では、システム運用でのよくある課題と、その背景を解説します。また、課題解決策や改善によるメリットもご紹介。システム運用の効率化を図り、社内のパフォーマンスを向上させるヒントにお役立てください。
「システム運用」の概念と「システム保守」との違い
はじめに、システム運用とは何を指すのかあらためて確認したいと思います。またシステム保守との違いや運用業務の具体例も解説します。
システム運用とは
システム運用とは「本稼働が始まったシステムが安定的に稼働できるよう管理する」業務です。システムが稼働し続ける限り必要な業務で、ユーザーが安心してシステムを利用できる状態を整えます。また、不具合が発生した際は復旧に向けた対応を進めます。システムが正しく安定的に稼働しているかを監視しながら、トラブルを未然に防ぐことがシステム運用の目的です。
システム運用と保守の違い
システム運用が「システムの安定稼働」を目的とするのに対し、システム保守は「トラブルが起きたときの改修や保全」を指します。トラブルが起きた際、システム運用ではトラブル前の状態に復旧させますが、システム保守は原因を究明し、必要な改修・変更も加えます。システム運用は管理業務、システム保守はメンテナンスと考えると、わかりやすいでしょう。タクシーに例えると、車を運転して快適に乗客を運ぶことがシステム運用で、車のメンテナンスが保守といえます。
システム運用業務の具体例
次に、企業IT環境を支える「システム運用業務」の代表的な項目と、その役割をわかりやすく整理してみます。これらの活動を通じて、組織は安定したサービス提供を実現し、ビジネス拡大や新サービス開発に注力できる基盤を築くことが可能になります。
- 監視・トラブルシューティング
サーバやネットワーク機器、アプリケーションの稼働状況を常時モニタリングし、CPU負荷やメモリ使用量、ネットワークトラフィック、ディスク容量などをチェックします。万が一異常や障害が発生した場合には、即座に原因を特定し、問題を切り分け、迅速な復旧に努めます。
- バックアップ・セキュリティ対策
データやシステム設定情報を定期的にバックアップしておくことで、ハードウェア障害やサイバー攻撃、自然災害等によりシステムが損傷した際にも迅速な復元が可能になります。また、OSやミドルウェア、アプリケーションへのパッチ適用、アクセス制御の適正化など、セキュリティリスクを低減する施策も重要です。
- 定期メンテナンス・アップデート
システム全体を長期的に安定稼働させるためには、不要ファイルのクリーニングやログローテーション、パフォーマンスチューニング、ハードウェアのヘルスチェックなど、計画的なメンテナンスが欠かせません。これらの作業により、システムは常に最適な状態を維持します。
- キャパシティプランニング・拡張性確保
利用者数や処理量増加に備え、サーバ増設、ネットワーク帯域強化、クラウドリソースのスケールアウトなど、将来を見据えたリソース計画を行います。これにより、ビジネス拡大時もパフォーマンス低下を防ぎ、顧客満足度を維持できます。
その他、運用手順書や構成図といったドキュメント管理やノウハウの共有、レポート作成といった様々な業務があります。なかでも、障害対応やユーザーからの問い合わせ対応は突発的で作業量の見通しが立てにくい点も、システム運用の課題になりやすいポイントです。
システム運用における8つの課題
システム運用について、企業はどのようなことを課題と感じているのでしょう。以下では、システム運用をしている際によくある8つの課題を解説します。
システム運用が属人化している
属人化とは、特定の担当者に知識スキルが依存した状態です。特定の担当者がいないとシステム運用業務が進まない状況では、作業の属人化の問題が生じます。システム運用が属人化すると、トラブルが起きた際には解決までに必要以上に時間がかかります。また、担当者が休暇中あるいは退職した場合にはシステムが停止してしまうといった大きなダメージにもなりかねません。
最新のシステム運用ドキュメントがない
システム運用をする際には設計書やテスト仕様書、運用マニュアルなどの運用ドキュメントが必要となります。この運用ドキュメントにはシステム運用に必要不可欠な内容が含まれていますが、運用ドキュメントが古い内容だったり不備が生じていたりと、最新版が揃っていないケースは少なくありません。最新の運用ドキュメントがないと、システム運用に必要以上の時間がかかるため、結果システム運用担当者の負担が増える原因となります。
IT人材の不足とスキルギャップ
システム運用に対応できるIT人材の不足に悩む企業は多く、今後もIT人材が足りない状況は続く見通しです。システム運用担当者が高齢化し、新しい人材を確保できないままに定年退職となることも多々あります。また、人材のスキルも十分とはいえません。特にIT業界では技術変化のスピードが速く、いま持っているITスキルが短期間で劣化してしまうからです。システム運用における人材不足は、量・スキルともに課題となっています。
膨大な作業量に対応しきれない
業務効率化が進むなかで、企業が導入するシステムは増える一方です。さらに、システムの複雑化・高度化も続きます。こうした状況下で、ひとたびトラブルが発生すると、システム運用担当者は膨大な作業を抱えることになります。現場だけでは対処しきれなくなるケースもあるでしょう。トラブル対応に追われ、根本的な問題解決は後回しになってしまうという課題もあります。
システム運用の適正コストが分かりにくい
他の業務同様、システム運用のコストも作業内容や工数によって増え続けていきます。一方で、システム運用は直接的に利益を生み出しません。コストの内容が見えにくいこともあり、システム運用費を闇雲に削減しようと考える経営陣もいます。コストの過剰な削減はシステムの安定稼働を防げます。運用コストの最適なバランスを見極め明示する難しさも、システム運用が抱える課題です。
システム運用に手一杯で、改善にまで手が回らない
企業のIT化の要であるシステム運用が、もっともDX化に遅れをとっている事例も散見されます。システム運用担当者に業務負荷がかかりすぎ、運営基盤を維持することで手一杯になっているためです。作業を自動化しようにも、自動化のための作業ができないジレンマに陥っている現場もあります。問題の発見と改善の必要性を理解していても、現実的に着手できない点もシステム運用の課題でしょう。
新しいサービスが次々に登場するため対応しきれない
企業の経営陣は、業務改善・業績向上のためにと、次々に新しいツールやアプリの導入を決定します。導入の度に負担が増大するのは、システム運用の現場です。設計に疑問が残ったまま運用を開始しないといけないこともあり、設計不備を運用でカバーする展開となるケースもあります。結果的に、業務改善・業績向上のために導入した仕組みが、システム運用の負荷増大するという悪循環に陥ります。
システム運用現場のモチベーションが上がらない
システム運用は、重要で欠かせない業務である反面、ルーティン作業も多く達成感を得にくい業務です。会社や顧客の利益には直結せず、感謝もされにくい部門ともいえます。こういったシステム運用特有の環境によって、担当者のモチベーションが上がりにくい点も課題です。担当者がやりがいを見出せず退職を選ぶ懸念もあります。
システム運用の課題となりやすい背景
このようにシステム運用には多くの課題を抱えています。なぜ、こういった課題は生じるのでしょうか。その背景となる2つの要因を紹介します。
ワークスタイルの多様化
新型コロナウィルスの世界的な流行により急速にリモートワークが広まりました。こういったワークスタイルの変化が新しい働き方として受け入れられる一方で、システム運用側の課題を増やしています。リモートワークに対応した環境の準備や運用、セキュリティの強化などは今までになかった課題の例です。また、新しいワークスタイルを導入したものの、運用ルールの作成や内容の見直しに着手ができていない企業もあります。
すでに過大な負荷を抱えていたシステム運用部門が、結果的に社内のヘルプデスクを兼務せざるを得ず、新たな課題につながるケースも見られます。
システムやソフトウェアの提供形態の変化
SaaSの普及に代表されるように、ソフトウェアの提供形態が劇的に変化しています。今までよりもシステム導入のハードルが下がった結果、次々と新しいツールが社内に登場するようになりました。新しいツールの導入は、ツールのメリットを直接受けられる部門にとっては喜ばしいことでしょう。
しかし、システム運用担当者は、新しいツールが導入される度にツールの理解と運用体制の整備を求められます。システム運用担当者が対応しきれずトラブルが頻発してしまうといった課題も発生します。
運用の重要性に対する認識不足
システム運用は「当たり前に動いていて当然」という前提で捉えられがちで、スポットライトが当たりにくい領域です。そのため経営層や他部署から十分な理解や評価が得られず、人材確保やツール導入、改善活動の推進が後手に回ります。結果として、運用現場は慢性的なリソース不足に陥り、様々な課題が解消されないまま積み重なっていく傾向があります。また、人材育成や採用、予算配分などが短期的な課題解決に注力され、運用体質そのものを改善するための長期的施策が後回しになりがちです。こうした組織的な硬直性が課題の改善を阻んでいます。
システム運用の課題を解決する3つの方法
今までシステム運用の課題を8つ紹介しましたが、具体的には、どのような対応方法があるのでしょうか。システム運用の課題を解決するための5つの方法を解説します。
1:運用プロセスの標準化とドキュメンテーション整備
標準化した運用手順書やガイドラインを整備することで、属人化を防ぎ、新任スタッフでも迅速に業務を行える環境を作ります。定期的な更新やレビューを通じて蓄積されたナレッジを継続的に改善することで、変化の激しい技術トレンドにも柔軟に対応可能です。標準化は自動化につながり運用の効率化を進める第一歩です。自社に標準化のノウハウや対応リソースがない場合は、システム運用のアウトソーシングを提供するMSP(Managed Service Provider)を活用することも有効です。現状の見える化から標準化支援や運用ベストプラクティスの導入がスムーズになり、運用チームの負担軽減にもつながります。
2:システム運用人材の育成
IT人材が不足する昨今、即戦力たる人材を採用することは厳しい状況です。そのため、人材不足は社内育成によって解決する方法を検討しましょう。
社内で人材を育成すると、「従業員のスキルレベル向上により競争力が高まる」「新技術の習得からインベーションが生まれる期待が持てる」といったメリットがあります。ただし、人材育成には時間がかかります。また、育てた人材が離職する可能性もゼロではありません。万が一の離職にも備え、継続的に人材を育成する時間の確保が重要です。
3:運用業務の内容・リソースの可視化、業務の再配分の検討
システム運用部門の業務について、業務内容やリソースの可視化、そして業務の再配分も検討してみましょう。業務を可視化し整理すると、実は不要な業務を発見できる可能性があります。不要業務を削減できれば、現場の負担を軽減できるでしょう。
また、業務量に応じてリソースを再配分し、人材不足の課題を解消することも可能です。業務の可視化により必要な業務や自動化が可能な業務の発見にもつながります。
4:外部サービスやツールの導入
運用業務のうち必ずしも担当者が行わなくてもよいものは、アウトソーシングや自動化ツールを検討します。技術力のある企業にアウトソーシングできれば、運用の品質は維持しつつ、システム運用担当者の業務負荷を軽減できます。ツールは、人為的ミスや人的リソースの削減に有効です。それぞれの長所と注意点を踏まえ、最適な業務配分を模索しましょう。
5:定期的な改善サイクル(PDCA)の確立と評価指標の明確化
運用においてもPDCAサイクルを回し続けることで、発生したインシデントや課題から学び、再発防止とプロセス改善に役立てます。また、明確な評価指標(KPI/KGI)を設定することで改善効果を「見える化」し、経営層からの理解と支援を得やすくなります。また外部業者が提供する運用レポートや分析ツールを活用するのも有効です。第三者視点からの改善提案や効果測定が可能となり、長期的な運用最適化を実現できるでしょう。
システム運用の課題解決によるメリット
システム運用には多くの課題がありますが、課題解決に取り組むことは企業にとって大きなメリットになります。下記に代表的なメリットをご紹介します。
メリットその1:サービス品質と信頼性の向上
システムの課題を発見し、適切に解決すると生産性が向上します。生産性とは、労働者1人あたり(1時間あたり)が生み出す成果です。課題の解決により業務が効率化し、生産性が高まれば、運用担当者のモチベーションも上がりやすくなるでしょう。業務に主体的に取り組むようになり、さらに生産性が高まる良い循環に入る可能性も考えられます。
メリットその2:システム運用の生産性が向上する
システムの課題を発見し、適切に解決すると生産性が向上します。生産性とは、労働者1人あたり(1時間あたり)が生み出す成果です。課題の解決により業務が効率化し、生産性が高まれば、運用担当者のモチベーションも上がりやすくなるでしょう。業務に主体的に取り組むようになり、さらに生産性が高まる良い循環に入る可能性も考えられます。
メリットその3:事業の継続可能性が高め、競争力を強化する
いまやシステム運用は企業の根幹を担う重要な部門です。事業が安定的に、そして継続的に発展するためにも、システム運用は欠かせません。安定した運用基盤によって、エンジニアや経営層は新サービス開発や市場への迅速な対応に集中できます。技術トレンドへの柔軟な追随やクラウド活用の加速が可能となり、スピーディーなサービス拡張や顧客要望への対応が実現します。結果として、改善された運用は企業競争力を高め、ビジネスの成長と持続的なイノベーションを後押しします。
システム運用の課題を放置することは、将来的なリスクを無視することと同義ともいわれます。システム運用の課題を直視してこそ、事業は継続でき発展していけるのでしょう。
システム運用の監視サービスを利用するのもおすすめ
このように、システム運用は企業の根底を支える重要な役割があります。しかし、自社がシステム運用に割けるリソースは限定的です。企業活動が活発になるにつれ導入するシステムは増えていきますが、社内でシステムを完璧に運用することは困難です。そのため、システム運用は外部の専門サービスを利用することもおすすめです。結果、社内の運用担当者をコア業務に振り分けられるようにもなります。
株式会社DTSの「ReSM」サービスは、システムを24時間365日手厚く運用監視します。経験豊富な技術者が、1社1社に最適な体制で必要な運用業務を適正コストで提供します。
まとめ
システムの高度化、ワークスタイルの変化などにより、企業のシステム運用はかつてないほど多様な課題に直面しています。IT人材の高齢化やリソース不足も課題を深刻にさせる要因です。ただ、企業にとってシステム運用は事業活動の「命綱」ともいえる重要要素のため、課題を抱えた不安定な状態のままでは永続的な発展は見込めません。
システム運用は専門サービスに任せ自社の従業員はコア業務に集中させる、といった思い切った戦略転換も必要です。インフラ構築からシステム運用・監視まで手掛けるDTSに、ぜひ一度ご相談ください。
近い課題のコラムを見る
関連するサービス
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。