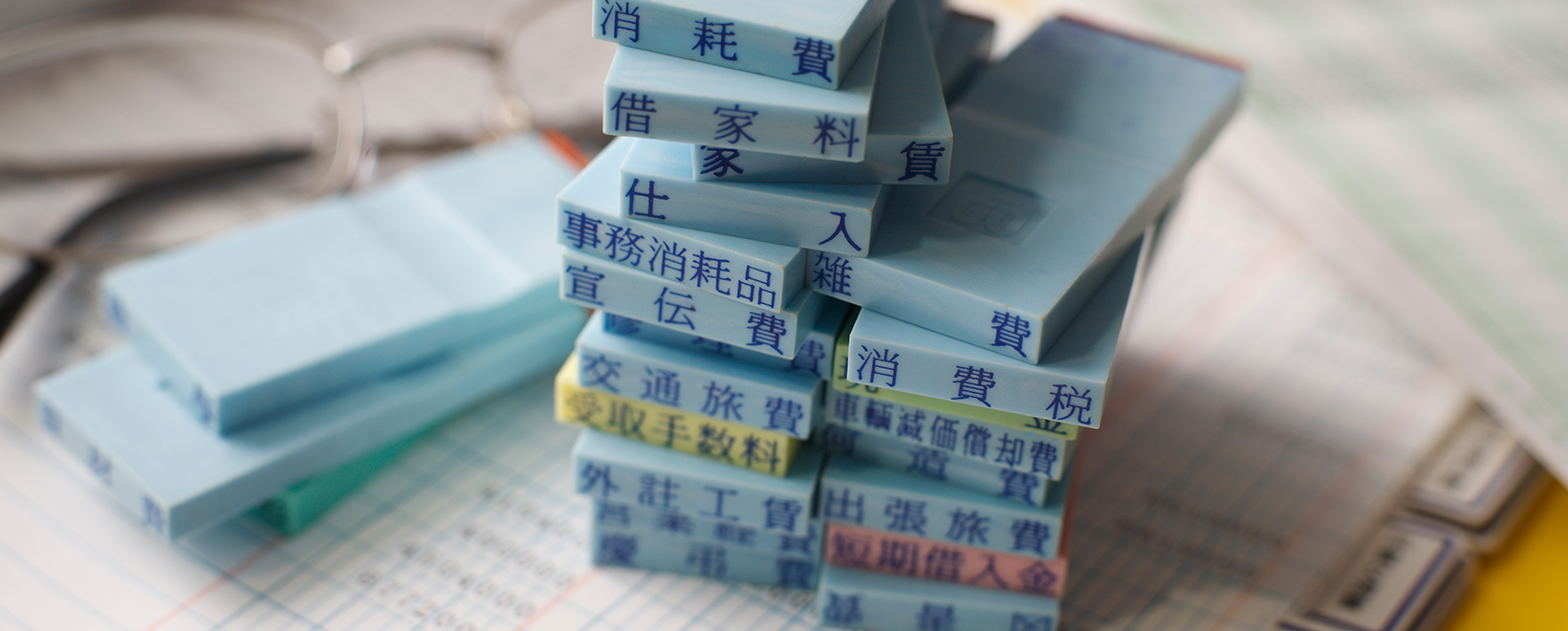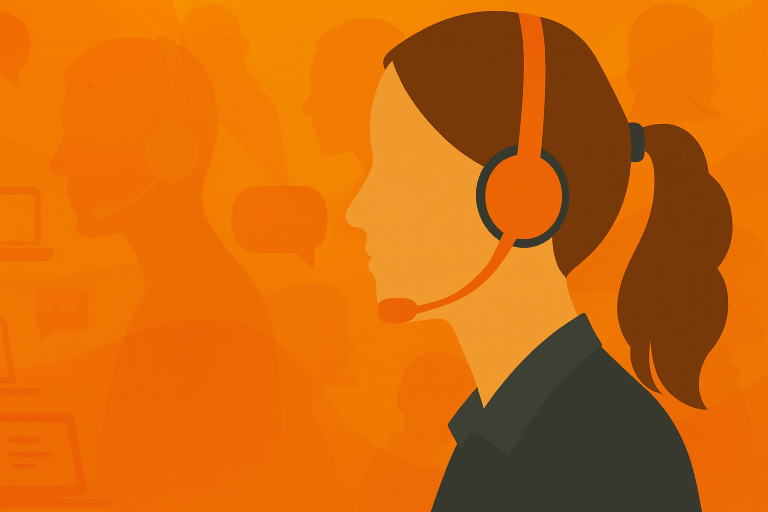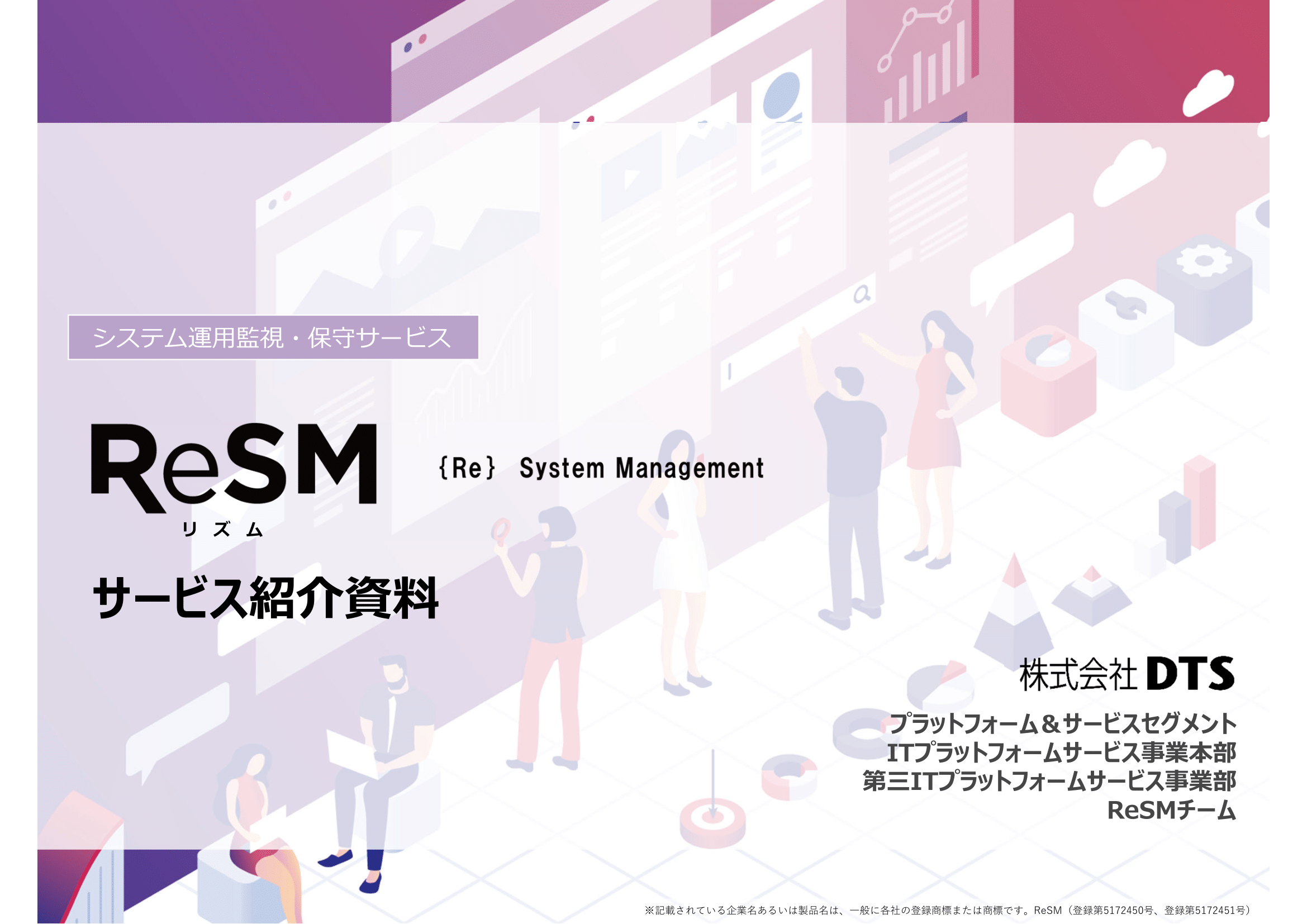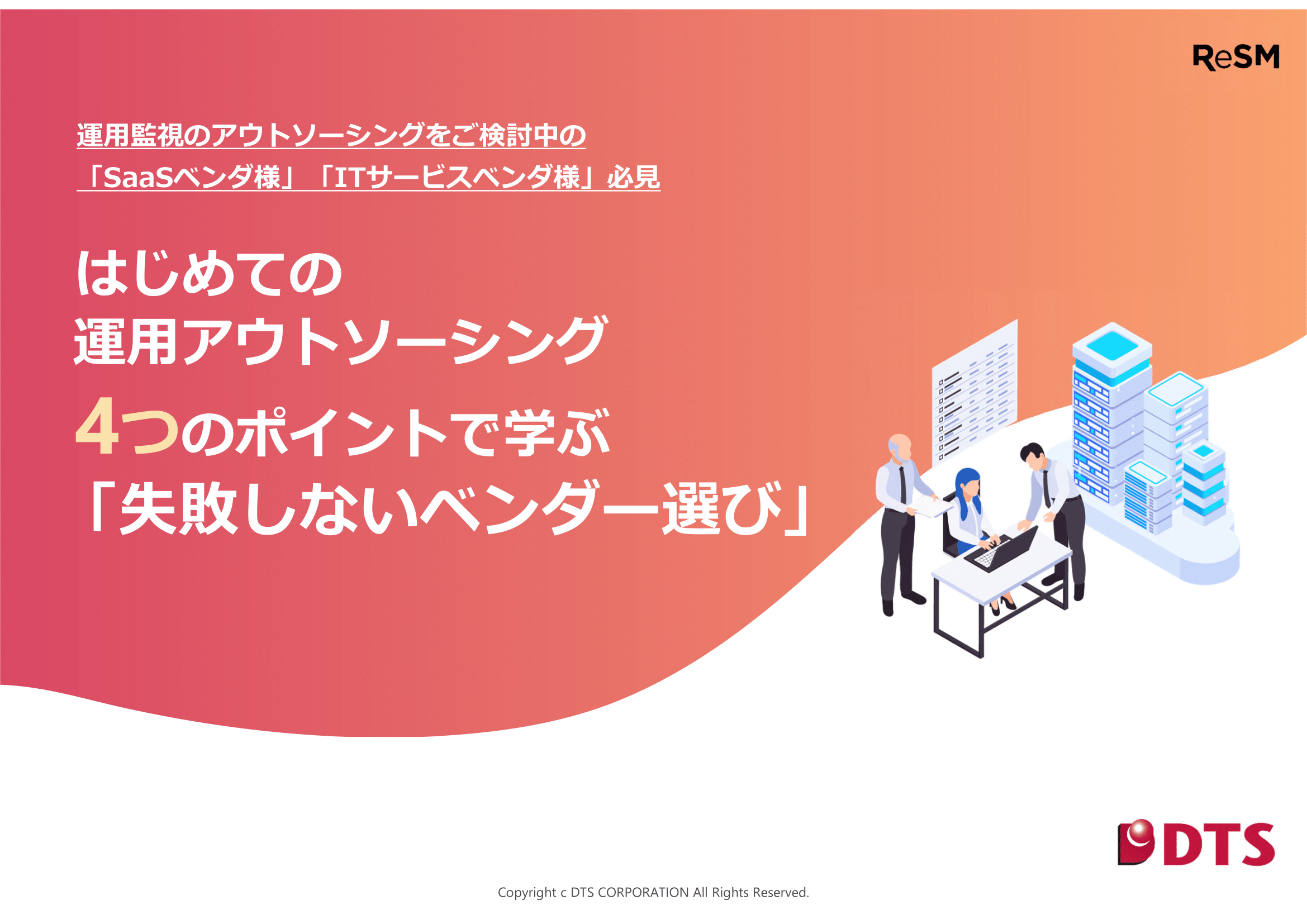テレワーク時代の社内ヘルプデスク業務の可視化・効率化のポイント

ヘルプデスク業務の可視化とは
社内ヘルプデスクとは
社内ヘルプデスクは、社員からの問い合わせやトラブルを一元的に受け付ける窓口です。パソコンやネットワークの不具合、アカウント発行やパスワードリセット、業務システムの操作方法まで、多岐にわたる相談が寄せられます。利用者にとっては日々の業務を円滑に進めるための重要な存在であり、企業にとっても生産性や社員満足度に直結する機能といえます。
一方で、問い合わせの件数が急増したり、対応が特定の担当者に依存したりすると、現場は疲弊しがちです。こうした状況を打破するために注目されているのが「ヘルプデスク業務の可視化」です。
可視化の目的と効果
ヘルプデスク業務の可視化には大きく3つの目的があります。
1. 属人化の解消
対応方法を明文化・共有することで、特定の担当者に依存しない体制を実現します。
2. 業務効率化
問い合わせ件数や対応時間を可視化することで、リソースの最適配分や無駄削減が可能になります。
例えば、よくある質問をFAQ化すれば自己解決率があがり、担当者は高度な案件に集中できます。また、経営者にとっては、データが投資判断やDX推進の根拠となり、組織的な成長に寄与します。
サービスデスク・テクニカルサポートとの関係
「ヘルプデスク」「サービスデスク」「テクニカルサポート」 は混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。
| 部門 | 役割 |
|---|---|
| ヘルプデスク | 利用者からの問い合わせ窓口(パスワードリセット、操作方法など) |
| サービスデスク | ITサービス全般の品質管理・改善を担う |
| テクニカルサポート | 製品やシステムに関する高度な技術支援を行う |
この3者は役割に違いがあるものの、根本には「利用者の課題を解決する」という共通の目的があります。ヘルプデスク業務の可視化は、これらの部門の情報連携を円滑にし、組織全体のサービス品質を底上げする効果を持っています。
例えば、ヘルプデスクで頻出する問い合わせを分析してサービスデスクに共有すれば、システム改善につながりますし、解決困難な事案をテクニカルサポートへ効率よくエスカレーションするためにも可視化は不可欠です。
可視化が必要となる背景と現状課題
テレワーク導入で社内ヘルプデスクの負担が増大
新型コロナウイルスを契機に多くの企業でテレワークが普及しました。これにより、ヘルプデスクに寄せられる問い合わせは一気に増加しました。
テレワークを導入した企業のなかには、自宅からのアクセスに関するシステムについて十分に検討をする時間がなく、とりあえず導入したというところも少なくないでしょう。そうすると、導入後にユーザーから「社内システムにつながらない」「パフォーマンスが悪くて使えない」などの問い合わせが社内ヘルプデスクに殺到します。
さらに、テレワークを始めるにはWeb会議システムやチャットなど、新たなツールも導入しなければなりません。導入すると今度は、「使い方がわからない」などの問い合わせが社内ヘルプデスクに押し寄せます。オフィスでみんな一緒に働いているときであれば、隣の人に聞くなど部署内で解決できたことが、テレワークになるとその相手が情報システム部門に変わるのです。
ITの導入により、業務効率化が進むことは企業にとっては喜ばしいことですが、その一方で働き方の急激な変化が社内ヘルプデスクに大きな負担をかけることになっています。結果として、対応遅延や情報の断絶が発生しやすくなり、組織全体の生産性低下につながっています。
属人化による業務停滞
ヘルプデスク業務は担当者の知識や経験に依存しやすく、属人化が進むと、業務全体の停滞を招きます。特定の担当者しか分からない対応方法が存在すると、不在時には問い合わせが滞留し、引き継ぎ時には情報不足で品質低下を引き起こします。これは利用者の不満につながります。
可視化によって対応履歴やナレッジを共有する仕組みを整えれば、誰が担当しても一定水準の対応が可能となり、業務の停滞リスクを大幅に低減できます。
業務効率の低下
問い合わせの進捗や対応履歴が見えないと、効率は著しく下がります。
典型例としては、同じ案件に複数担当者が対応して二重作業になるケースや、優先度が不明確で後回しになってしまうケースです。結果的に、利用者からの催促が増え、さらにやり取りが膨らむ「非効率の連鎖」が発生します。進捗やステータスをリアルタイムに把握できる仕組みが欠かせません。
応対品質のばらつき
ヘルプデスクの現場では、同じ問い合わせであっても担当者によって回答内容やスピードが異なることがあります。熟練者なら即答できる一方、経験の浅い担当者では回答が遅れたり誤った情報を伝えてしまったりするリスクがあります。
こうした品質のばらつきは利用者の不満や信頼低下を招きやすく、結果的に「ヘルプデスクに聞いても解決しない」という評価に繋がりかねません。可視化とナレッジ共有を進めることで回答の標準化が可能になり、応対品質を安定化させることができます。
可視化すべき主な業務項目
ヘルプデスク業務を効率的に改善するには、「何を可視化するか」を明確にすることが重要です。単に問い合わせ件数を数えるだけでは不十分であり、内容や傾向、担当者の負荷状況などを多角的に把握する必要があります。
| 可視化すべき主な項目 |
|---|
| 問い合わせ件数と内容の傾向 |
| 対応状況と進捗管理 |
| ナレッジとインシデント履歴 |
| 担当者別の負荷と貢献度 |
問い合わせ件数と内容の傾向
まず基本となるのが、問い合わせ件数と内容の可視化です。件数の推移を時期別・カテゴリ別に整理することで、業務量の増減や繁忙期の特定が可能になります。たとえば月初にアカウント発行の問い合わせが集中する場合、それに合わせたリソース配置や事前案内を検討できます。
さらに、内容を分類して分析すれば、繰り返し発生する問題を特定でき、FAQやマニュアル改善に直結します。このように「件数」と「内容」をセットで把握することで、リソース配分や改善施策の根拠を得ることができます。
問い合わせ内容の分類は工数がかかり、億劫な作業と思われる方も多いのではないでしょうか。ChatGPTやCopilotを始めとする生成AIは、内容の分類が得意分野です。これまでは手を付けられなかったが、この機会に改めて取り組まれるという方も多いです。
対応状況・進捗管理
問い合わせを受け付けてから解決に至るまでのステータスを可視化することも不可欠です。「受付中」「対応中」「解決済」「保留」などの進捗を一目で確認できれば、対応漏れや放置を防止できます。
また、優先度を明確に設定することで、緊急度の高い案件から順に対応できる体制を整えられます。進捗管理は利用者にとっても安心材料となります。問い合わせが今どの段階にあるかが分かれば、不安や催促が減り、信頼感を高める効果があります。
ナレッジとインシデント履歴
過去の対応事例やトラブルシューティングの履歴を蓄積・共有することも重要な可視化対象です。同じようなトラブルが再発した場合でも、蓄積されたナレッジを検索して活用できれば、迅速かつ正確に対応できます。これにより、再発防止と一次解決率の向上を同時に実現できます。
さらに、ナレッジを活用すれば担当者の経験差による品質のばらつきを抑えられ、新人教育やスキルトランスファーにも効果を発揮します。可視化された履歴は「組織の資産」として活用価値が高いのです。
担当者別の負荷・貢献度
最後に、担当者ごとの業務量や対応時間の可視化も欠かせません。
特定の担当者に業務が集中していないか、対応スピードや解決率に偏りがないかを把握することで、公平で効率的な業務配分が可能になります。過剰に負担がかかっている担当者を早期に把握できれば、バーンアウトを防ぐことにもつながります。加えて、個々の成果を客観的に評価する指標にもなり、人材育成や評価制度に反映できる点もメリットです。
ヘルプデスク業務を可視化する方法
ヘルプデスク業務の可視化を実現するには、ツール・業務プロセス・運用体制を組み合わせて仕組み化することが重要です。可視化の目的は「課題を把握して改善につなげる」ことにあるため、現場にとって使いやすく、継続的に活用できる方法を選ぶ必要があります。
以下では代表的な手法を紹介します。
| 可視化を行う代表的な手法 |
|---|
| 可視化ツールの導入(チケット管理ツール、ナレッジ管理ツール) |
| 自動録音、文字起こしの活用 |
| 業務フロー図、マニュアル作成 |
可視化ツールの導入
業務可視化の中心となるのが、チケット管理システムやダッシュボード、BIツールです。これらを活用することで、問い合わせ件数や進捗、解決率などをリアルタイムに把握できます。ツール選定の際は以下の3点が重要です。
- 必要機能とコストのバランス
- 各担当者にとって運用しやすいか
- 既存システムとの連携性
単に高機能であることよりも、担当者が日常的に使い続けられる操作性や、部門間での情報共有に適した形式を備えているかが重要です。
チケット管理ツール
チケット管理ツールは、問い合わせを一元管理する代表的な仕組みです。問い合わせが入ると自動でチケット化され、対応履歴や進捗が記録されます。これにより、対応漏れや重複作業を防ぎ、案件ごとの優先度を明確にできます。また、リアルタイムで進捗を確認できるため、マネージャーがリソース配分を判断する際の根拠にもなります。代表例としては、Jira Service Management、ServiceNow などが挙げられます。
ナレッジ管理ツール
ナレッジ管理ツールは、FAQやマニュアル、解決事例を一元的に蓄積・共有する仕組みです。利用者は検索を通じて自己解決でき、問い合わせ件数の削減に直結します。また、回答が標準化されることで応対品質が安定し、経験の浅い担当者でも一定水準のサポートが可能になります。Confluence や Notion、あるいはチケット管理ツールに統合されたナレッジベース機能など、選択肢は幅広く存在します。
自動録音・文字起こしの活用
電話やオンライン会議を通じたやり取りを自動的に録音・文字起こしすることで、応対品質の客観的な評価が可能になります。記録をトレーニング用教材として活用すれば、新人教育の効率化にもつながります。
また、通話内容がログとして残ることで、言った言わないのトラブル防止にも有効です。特にリモート環境では、証跡を残すことが安心材料となります。近年では生成AIの活用によって、高性能な文字起こしツールも多数存在しています。
業務フロー図・マニュアル作成
可視化はデータだけでなく、業務手順やフローの図式化によっても実現できます。業務全体をフローチャートやプロセスマップに整理すれば、ボトルネックや重複作業が浮き彫りになり、改善の着眼点を得やすくなります。
さらに、手順をマニュアルとして明文化すれば、属人化を防ぎ、新人教育や引き継ぎの効率化が可能です。現場で活用しやすいよう、シンプルかつ実務に即した形式で整備することがポイントです。
可視化による改善ポイント
可視化の最大の価値は、単なる「見える化」で終わらせず、その結果を業務改善につなげることにあります。問い合わせ件数や進捗状況、担当者負荷を把握するだけでは不十分で、そこから課題を抽出し、改善策を実行し、効果を検証する一連のサイクルを回すことが重要です。ここでは、可視化データを活用した具体的な改善ポイントを紹介します。
ヘルプデスク業務の可視化は、単に「状況を見える化する」だけでは効果が限定的です。重要なのは、可視化データを活用して課題を抽出し、改善施策へと落とし込むことです。ここでは、可視化データを活用した具体的な改善ポイントを紹介します。
改善目標の設定
まず行うべきは、可視化データをもとにした改善目標の設定です。測定可能なKPIを定めることで、改善活動が形骸化せず、組織全体で目標を共有できます。
■目標設定の例
- 問い合わせ1次解決率を○%に引き上げる
- 平均対応時間を○分短縮する
さらに、目標設定の段階で部門横断的な合意形成を行うことで、改善が一部の担当者にとどまらず、組織全体の取り組みとして根付く効果があります。数値化された目標は経営層への報告や投資判断にも役立ちます。
業務フローの見直し
可視化によって業務プロセスのボトルネックや重複作業が明らかになれば、その改善が次のステップとなります。例えば、同じ問い合わせが何度も発生している場合は、FAQの強化やシステム仕様の改善を検討できます。
進捗確認の問い合わせが多い場合は、ユーザー向けのステータス通知機能を導入することで、二度手間を減らすことが可能です。メールやteams、slackといったチャットツールと連携し、ユーザーへ自動通知を飛ばすこともできます。業務フローの見直しは、小さな改善の積み重ねが大きな効率化につながる領域であり、データに基づいたアプローチが特に有効です。
ナレッジとインシデントの一元管理
可視化の中で特に効果が大きいのが、ナレッジとインシデント履歴の一元管理です。過去の事例や解決策を集約し、誰でもアクセスできる状態にすることは、可視化改善の中でも最も効果が大きい取り組みです。ナレッジを一元管理することで、対応スピードが向上し、属人化のリスクを解消できます。
新人や経験の浅い担当者もデータベースを活用することで、ベテランに近いレベルの対応が可能になり、品質の標準化が進みます。さらに、インシデントの傾向を分析することで、システム改修や教育施策など戦略的な改善にもつなげられます。ここでもツールの連携が効果的です。メールやチャットツールで受け取った問い合わせを、直接チケット管理ツールに登録するといったことも可能です。
継続的な可視化と改善の仕組み
ヘルプデスク業務の可視化は、一度導入すれば終わりではありません。IT環境や働き方は常に変化するため、継続的に見直しと改善を行う仕組みが必要です。仕組みが固定化すると、すぐに陳腐化してしまいます。ここでは、改善を持続させるための3つの観点を解説します。
定期レビューサイクルの構築
可視化データは定期的にレビューし、改善アクションに結びつける必要があります。
例えば週次では「対応漏れや遅延案件の有無」を確認し、月次では「問い合わせ件数の推移や対応時間の平均値」を評価するといった具合に、短期・中期の視点で確認を行うと効果的です。レビュー会議では現場担当者の意見を取り入れることが重要であり、単なる数値評価に終わらず「なぜこの結果になったのか」「次に何を改善するか」という議論を重ねることで、改善のループが組織文化として定着します。
KPI・指標の継続運用
可視化を継続改善につなげるためには、KPIの設定と運用が不可欠です。
■ヘルプデスクに代表的な指標
- 1次解決率
- 平均対応時間
- 顧客満足度
- 問い合わせ削減率
これらの指標を可視化データと紐付けることで、改善の成果を定量的に把握できます。また、事業環境に応じて柔軟にKPIを見直すことも欠かせません。たとえばチャットボット導入後には「自己解決率」を新たに指標に加える、といった対応が有効です。
部門横断の情報共有
ヘルプデスク単体での改善には限界があります。問い合わせデータやナレッジを他部署と共有することで、全社的な業務最適化につなげられます。例えば、頻発するインシデントの傾向をシステム開発部門と共有すれば、根本的なシステム改修につながりますし、人事や総務と連携すれば入退社手続きの効率化が可能です。
部門横断での情報共有は、重複作業を削減し、組織全体の生産性を底上げする強力な手段となります。情報共有を「組織全体の資産」として位置づけることで、改善のスピードと質を両立できます。
社内ヘルプデスクを効率化する方法
効率化のためには、単にツールを導入するだけではなく「ユーザー自身の自己解決を促す仕組み」と「担当者の業務効率を高める仕組み」を両輪で整備することが求められます。また、ユーザーからの問い合わせがゼロになることはありません。そのため、社内ヘルプデスクで効率的に対応できる仕組みづくりを検討することも大切です。
ここでは、代表的な4つのアプローチを解説します。
FAQ検索で簡単な問い合わせを減らす
マニュアルを配布しても「どこに答えが書いてあるのか分からない」という理由で結局ヘルプデスクに問い合わせるケースは少なくありません。ユーザーは一刻でも早く解決したいため、使いにくいマニュアルは、逆に社内ヘルプデスクの業務量を増やすおそれがあります。
そこで有効なのが、検索性の高い社内FAQシステムの活用です。社員がよく直面する質問やトラブル事例をデータベース化し、検索一発で答えにたどり着ける環境を整えることで、自己解決を促進できます。FAQを整備する際は「ユーザー目線でわかりやすい表現」にすることが重要です。専門用語を避け、画面キャプチャや手順図、動画を加えると、ITに苦手意識がある社員でも理解しやすくなります。
ヘルプデスクに良く問い合わせをする方を想像してみましょう。その人でも自己解決できるか?と自ら問いかけながらFAQを作成することが効果的です。
チャットボットなどのITツールを導入する
FAQやマニュアルでもカバーしきれない部分には、 チャットボット の導入が効果的です。
チャット形式で質問を入力すると自動回答が得られる仕組みで、24時間いつでも即座に対応できるのが強みです。特に「パスワードを忘れた」「会議ツールが接続できない」といった定型的な問い合わせはチャットボットで処理できるため、担当者は高度な問題に集中できます。いつ問い合わせても即座に回答が提示されますから、社内ヘルプデスクの大幅な業務負担の軽減が期待できます。
また、チャットボットの利用ログを解析することで、FAQ改善や教育コンテンツの充実にも役立ちます。
蓄積されたノウハウを共有する
社内ヘルプデスクを円滑に進めるには、担当者以外でもスムーズに対応できるよう、組織全員で知識やノウハウを共有するしくみづくりも必要です。解決した事例や対応フローを全員がアクセスできる形で共有すれば、誰でも一定レベルの対応が可能になります。
また、対応が長期化する案件については進捗状況をリアルタイムで確認できるようにしておくと、担当者が不在の場合でも誰かが対応できるようになり、課題の早期解決も見込めます。
ヘルプデスクには日々の対応を通じて多くのノウハウが蓄積されますが、それが担当者の頭の中に留まってしまうと属人化が進みます。また、進行中の案件もリアルタイムで共有できるようにしておくと、担当者が不在の場合でも他のメンバーが引き継ぎやすくなり、業務停滞を防止できます。
定期的に振り返り改善を続ける
FAQやチャットボットを整備しても、放置すれば情報が古くなり、ユーザーが「役に立たない」と感じてしまいます。新たな疑問や質問が生まれることや、改善が必要なこともあります。そのため、定期的に利用者の声を収集し、「どの情報が使われているか」「どの質問が繰り返されているか」を分析することが欠かせません。
場合によっては、FAQやチャットボットでは解決できない根本課題が潜んでいることもあり、その場合はシステム改善や業務フロー見直しへとつなげる必要があります。一時的な解決策を案内するだけでなく、社内ヘルプデスクでの振り返りを通して根本的な原因を解決するための方策を検討することも、業務効率化を進めるうえで重要なポイントになります。
社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事
PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問……。社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。
多くの企業では、FAQの整備や手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。
問い合わせ数の削減を目指す社内ヘルプデスク代行サービス「ReSM plus リズムプラス」
ReSMplusは単なる代行ではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すヘルプデスク支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。
- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくる
- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る
それぞれの特徴についてご紹介していきます。
問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。
属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。
SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。
その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。
パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…
こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。
まとめ
ヘルプデスク業務の可視化は、現場担当者にとっては負担軽減の手段であり、利用者にとっては安心して相談できる環境を作り、経営層にとってはIT投資判断やDX推進の基盤となります。
つまり「可視化」は、組織全体をつなぐ共通言語として機能し、持続的な改善と成長を支える柱となるのです。
この記事の著者
近い課題のコラムを見る
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。