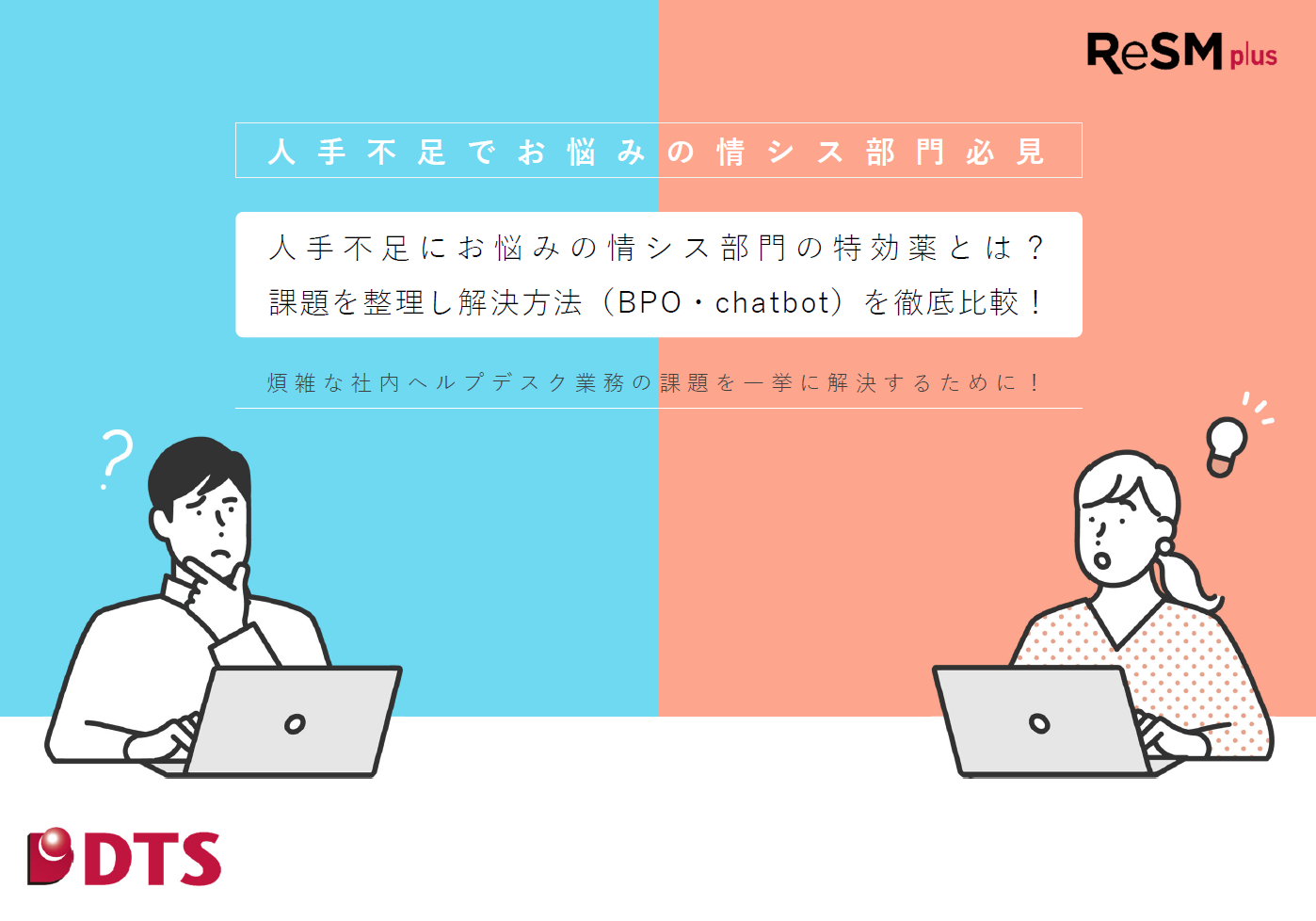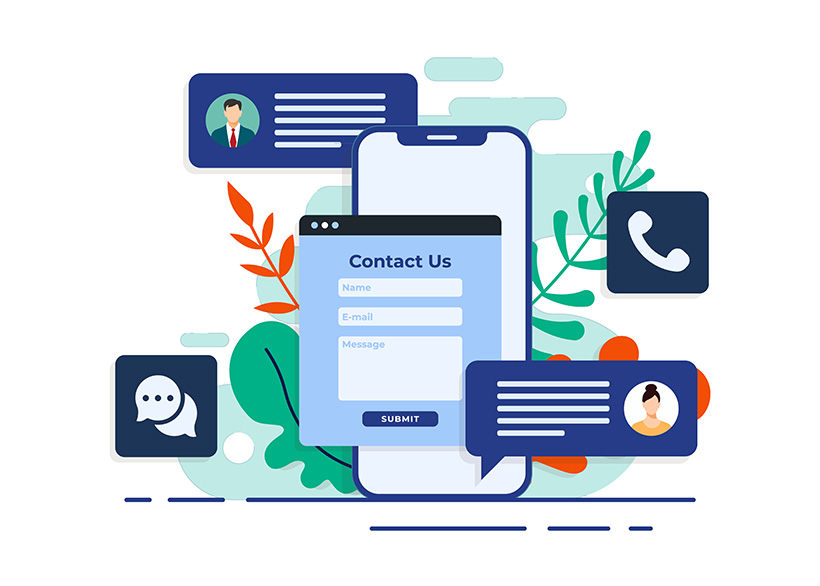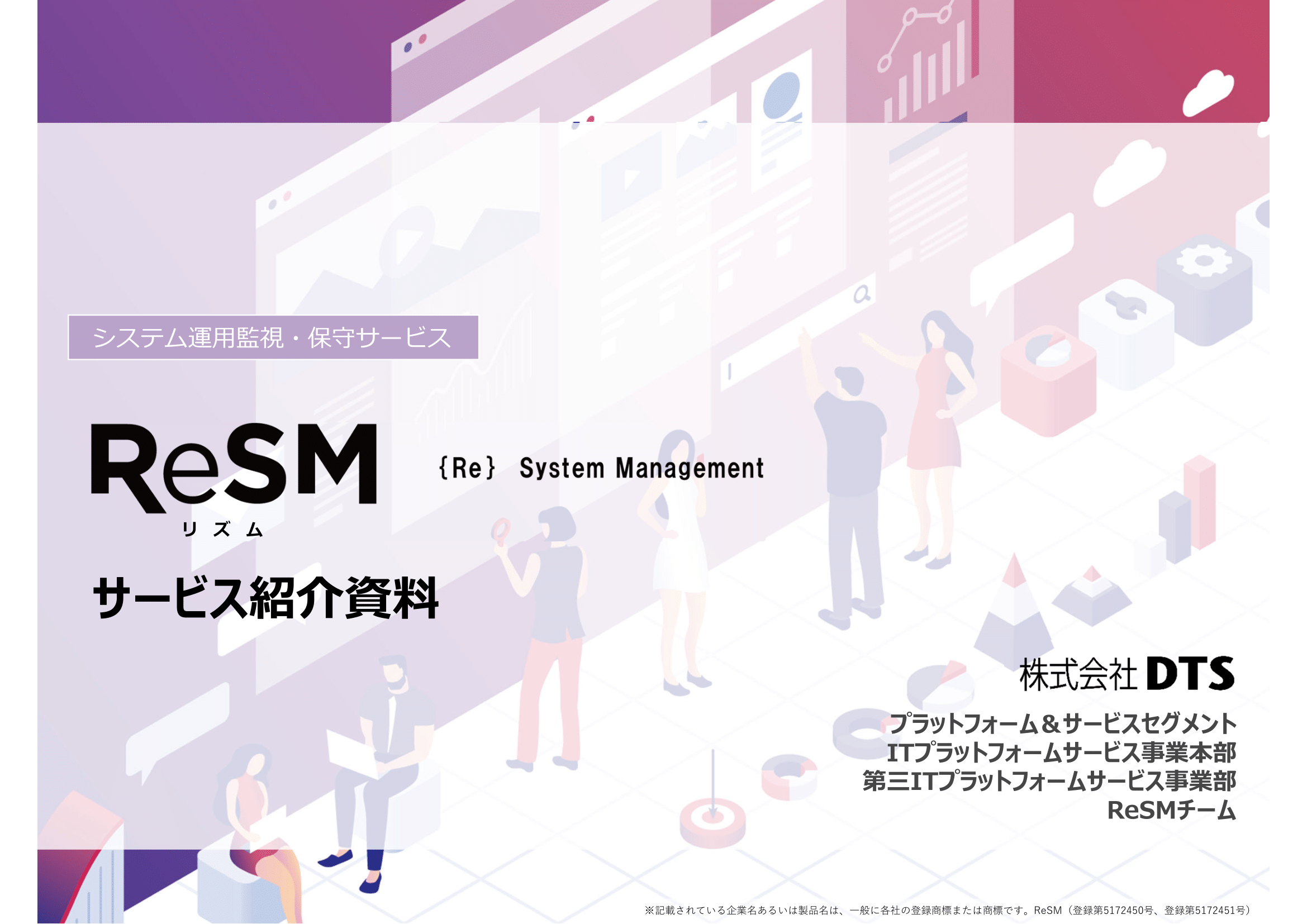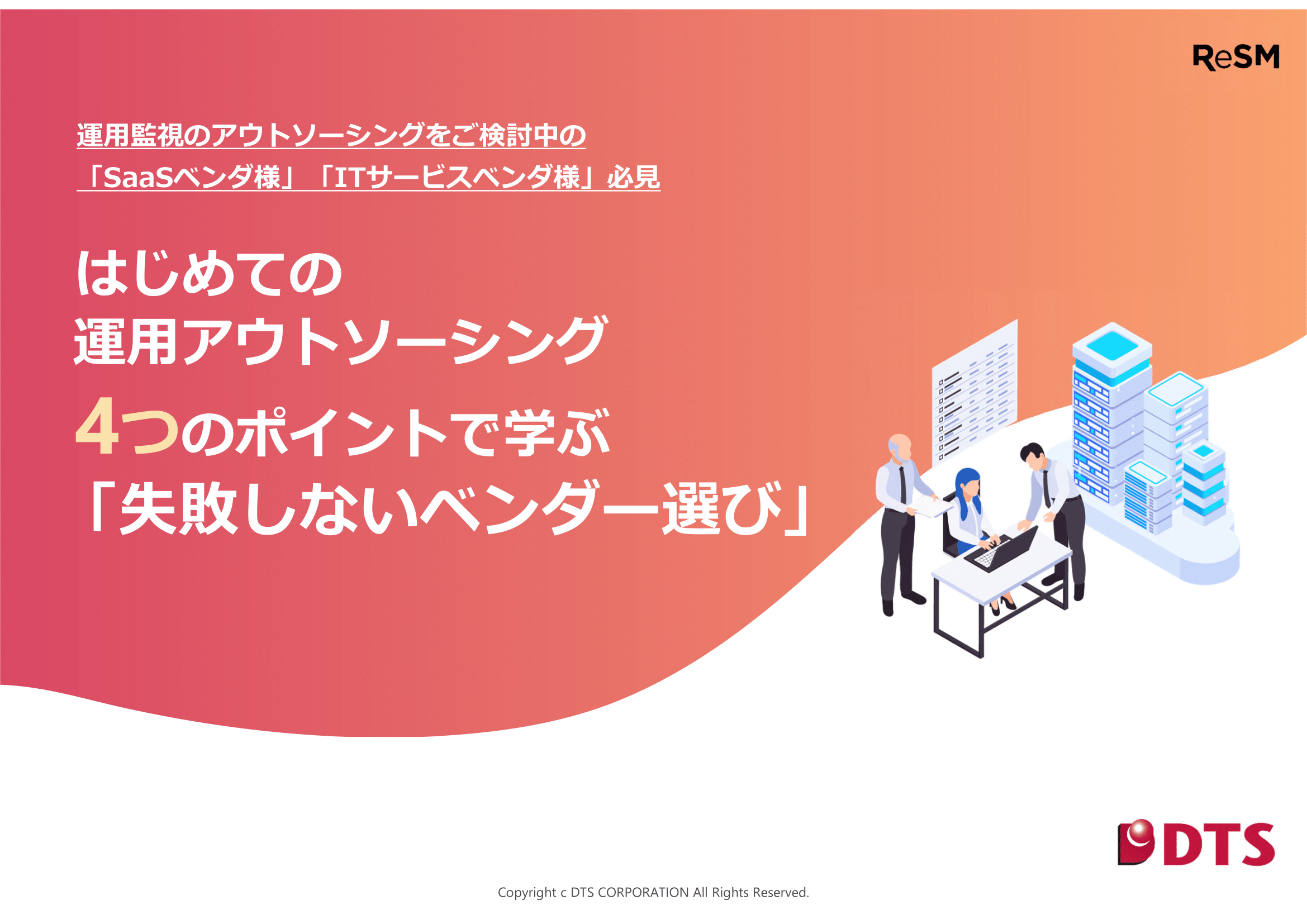ヘルプデスクの業務内容や社内ヘルプデスクと社外ヘルプデスクの違い、抱える課題まで一挙解説

ヘルプデスクとは、製品やサービスに関する問い合わせを一次受付し、情報提供や問題解決を行う業務、または組織を指します。
ヘルプデスクには日々、大勢のユーザーから幅広い問い合わせが寄せられます。そのため、人手不足や回答遅延が起こりやすい点が大きな課題です。
本コラムでは、これからヘルプデスクを立ち上げる企業様や、既存のヘルプデスク運用に課題を抱える企業様向けに、ヘルプデスクの基本と運用のポイントを解説します。
ヘルプデスクとは
ヘルプデスクの定義と役割
日々、多くのユーザーからの問い合わせを受け付け、適切な情報提供や初期対応を行う。それがヘルプデスクの基本的な役割です。製品やサービスを提供する企業にとって、ヘルプデスクはユーザーとの最前線に立つ重要な接点であり、顧客体験を支える基盤でもあります。
多くの場合、電話・メール・チャットといった複数のチャネルを通じて問い合わせが寄せられます。製品やサービスの使い方がわからないといった操作相談から、トラブル発生時の原因調査、修理の依頼、さらにはクレーム対応まで、対応範囲は非常に幅広くなります。
また、問い合わせ内容を記録し、FAQとして公開・更新することもヘルプデスクの重要な役割です。これにより、ユーザー自身による自己解決を促進し、問い合わせ件数の削減にも繋がります。
| 主な役割 | 詳細 |
|---|---|
| 情報提供 | マニュアル・操作方法の案内 |
| トラブル対応 | 不具合の一次切り分け・復旧支援 |
| ナレッジ化 | よくある質問をFAQとして公開 |
| 満足度向上 | 応答速度と品質を維持し、CSを高める |
単なる問い合わせ対応部門としてではなく、業務効率の向上やカスタマーサポート全体の品質を左右する、戦略的なポジションであると認識することが重要です。
社内ヘルプデスクと社外ヘルプデスクの違い
ヘルプデスクには、大きく分けて社内向けと社外向けの2種類があります。それぞれ、対象とするユーザーや対応内容、求められるスキルに違いがあります。
社内ヘルプデスクの特徴(従業員向け)
社内ヘルプデスクとは、社内の従業員向けに提供するヘルプデスクです。特に、情報システム部門に寄せられるIT関連の問い合わせ対応を指します。
「パソコンが動かない」「ID・パスワードを忘れてシステムに入れない」など、社内で導入しているPCやスマートフォン、タブレット端末から、システムやアプリケーションなどのソフトウェア関連、ネットワーク、セキュリティ、サーバーに至るまで、IT全般の不具合があれば、その問い合わせ対応の窓口となっているのが情報システム部門でしょう。
部署やシステムごとに異なる事情を踏まえた柔軟な対応が求められ、社内制度や業務プロセスへの理解が不可欠です。そのため、ヘルプデスク業務の負担は重くなりがちです。
社外ヘルプデスクの特徴(顧客向け)
社外ヘルプデスクとは、顧客に対して提供するヘルプデスクです。主に、自社が提供している製品やサービスに関する問い合わせを顧客から受け付けます。
不具合などトラブルが起きた際に寄せられるケースがほとんどで、特に、社内ヘルプデスクではあまりないクレーム対応が必要な点が特徴です。また、顧客への対応となるため、社内ヘルプデスクよりもさらに丁寧さが求められます。
企業によっては、この業務をアウトソーサーに委託する場合もあり、応対品質やブランドイメージを損なわないよう、応対マニュアルや対応履歴の管理が厳密に行われます。そのため、社外対応にはより高度な応対スキルと、プロとしての振る舞いが問われます。
機能面・役割の比較
両者は一見似ているようでいて、支援の前提も、成果の測り方も大きく異なります。
その違いを理解したうえで、体制構築やKPI設計を進めることが、実行力のあるサポート部門づくりの第一歩となります。
| 比較項目 | 社内ヘルプデスク | 社外ヘルプデスク |
|---|---|---|
| 対象 | 社内の従業員 | 顧客 |
| 目的 | 業務継続性の確保 | 顧客満足・信頼獲得 |
| チャネル | 社内チャット、内線電話、社内ポータル | 電話・webフォーム・メール |
| 必要スキル | 社内制度の理解、ITツールへの知識 | 製品知識・接客スキル |
| 指標 | SLA(応答/復旧速度) | 一次解決率 / NPSなど |
ヘルプデスクと混同されがちな職種
| 職種 | 位置付け | 主な業務・責任範囲 |
|---|---|---|
| ITサポート | 現場技術支援 | PC初期設定、NW機器設定、オンサイト修理 |
| テクニカルサポート | 二次対応 | 仕様調査、ログ解析、再現テスト、パッチ適用 |
| サービスデスク | ITIL上位概念 | インシデント/サービス要求/変更/資産管理 |
| コールセンター | 大量処理窓口 | スクリプト応対、受注・予約、量と効率を重視 |
| 社内SE | 上流工程 | 要件定義、システム設計、ベンダーコントロール |
ヘルプデスクとITサポートの違い
ヘルプデスクは窓口としての一次対応を主な役割とし、問い合わせ内容の受付、状況確認、簡易なトラブルの切り分けを担当します。それに対して、ITサポートは、より技術的な解決を必要とする案件を担当し、実際に現場での作業や設定、修理対応などを行うポジションです。
たとえば、PCの初期設定やネットワーク機器の構築といった作業はITサポートが担うケースが多く、ヘルプデスクはその前段階でユーザーから情報を聞き取り、対応の必要性を判断する役割にとどまることが一般的です。
ヘルプデスクとテクニカルサポートの違い
テクニカルサポートは、製品やサービスのより深い技術的な課題に対応する専門職です。
ヘルプデスクが主に受付・一次対応にフォーカスしているのに対し、テクニカルサポートは二次対応として、ヘルプデスクから引き継がれた案件に対し、仕様調査や動作検証を含む専門的な支援を行います。
技術的な深さや業務の責任範囲において、両者は明確に分かれているものの、ユーザーからは一続きのサポート体制として見られることが多く、連携の精度が求められます。
ヘルプデスクとサービスデスクの違い
サービスデスクは、ITサービスマネジメントの国際標準であるITIL(Information Technology Infrastructure Library)で用いられる概念であり、ヘルプデスクよりも幅広い役割を担う統合的な窓口です。
具体的には、インシデントの受付・対応に加え、サービス要求の管理、変更申請の対応、IT資産の管理、ライセンス情報の取り扱いなど、IT運用全体のハブとして機能します。
これに対してヘルプデスクは、その中の一部である「ユーザーからの問い合わせ受付と一次対応」を担う機能にあたります。組織のIT成熟度が高まるにつれ、ヘルプデスクからサービスデスクへの移行や統合が進むケースも見られます。
ヘルプデスクとコールセンターの違い
ヘルプデスクとコールセンターは、どちらも問い合わせ対応窓口という点では共通していますが、その業務内容と目的は大きく異なります。
コールセンターは、主に電話を通じて大量の問い合わせを受け付ける部門であり、マニュアルやスクリプトに基づいた定型的な応対が中心です。受注や予約受付、商品の案内など、業務の量と効率を重視する傾向があります。
一方、ヘルプデスクでは、ユーザーの状況や問題点を丁寧にヒアリングし、技術的な知識をもとに柔軟な対応を行うことが求められます。問い合わせ件数が少なくても、対応に時間や判断力を要するケースが多く、コールセンターとは運用方針や人材要件も異なります。
ヘルプデスクと社内SEの違い
社内SEは、社内のITインフラやシステム導入、業務プロセスの最適化など、ITを活用した全社的な仕組み作りを担うポジションです。
要件定義やベンダー選定、システム設計など、いわゆる上流工程に携わるのが特徴であり、日々の問い合わせ対応とは性質が異なります。
一方、ヘルプデスクは、導入されたシステムを日々の業務で使いこなせるよう支援する運用フェーズの業務を主に担当します。パスワードリセットやアクセス権限の変更、トラブル時の初動対応など、現場に近い位置でのサポートが求められます。
中小企業では、社内SEがヘルプデスク業務も兼任しているケースが多く、業務の切り分けが曖昧になりがちです。その結果、本来取り組むべき改善活動や戦略的なIT投資が後回しになるといった弊害も発生しています。
ヘルプデスクの主な業務内容とは?
ヘルプデスク業務は、単に電話応対をする部門ではありません。
実際には、チャネル対応から技術的な一次切り分け、アカウント管理、ナレッジの運用まで多岐にわたる業務を担っています。
以下では、代表的な4つの業務領域について詳しく見ていきます。
問い合わせ対応(電話・メール・チャット)
ヘルプデスクの中心的な業務が、問い合わせ対応です。操作説明やエラー申告など、幅広い内容が寄せられるため、チャネルごとの特性に合わせた運用が求められます。
電話対応は緊急性の高い案件に向いていますが、記録が残りづらく、属人化しやすいという課題があります。一方、メールやチャットはログが自動で残るため、対応履歴をそのままナレッジ化に活用しやすいというメリットがあります。
また、単に応答するだけでなく、ユーザーの話を整理して聴くヒアリング力や、感情を和らげる丁寧な言葉遣い、曖昧な要望を構造化する力も求められます。
トラブルシューティングと一次切り分け
トラブルシューティングとは、ユーザーからの「動かない」「おかしい」といった曖昧な報告に対し、原因を推測しながら対応方法を導くプロセスです。
例えば、「画面が真っ暗になった」という問い合わせに対し、電源/接続/モニター設定/OSの不具合といった可能性を考えながら、再起動・ケーブルの抜き差し・BIOS起動の有無などを確認します。
ここで重要なのが、症状を正確に把握し、技術部門にエスカレーションすべきかどうかを判断する力です。エスカレーションが不要なトラブルを自力で解決できれば、組織全体の対応スピードが飛躍的に向上します。
アカウント管理・システム利用支援
社内のIT業務では、IDやパスワードに関する問い合わせが非常に多く発生します。
例えば「社内システムに入れない」といった内容は、アクセス権限・ブラウザ設定・ネットワーク制限など複数の要因が絡むため、単純な案内では解決できないことも多いのが現状です。
また、SaaSやクラウドの利用拡大に伴い、Google WorkspaceやMicrosoft 365など多数のツールのサポート範囲を把握しておくことが求められます。
これらの問い合わせは、単なるログインサポートにとどまらず、業務そのものを止めてしまうリスクがあります。だからこそ、システム側の設定と現場側の業務両方を理解した、横断的なサポートが必要とされます。
ナレッジの整備とFAQの活用
ヘルプデスク業務の属人化を防ぐうえで、ナレッジの整備は欠かせません。蓄積された対応履歴を整理し、FAQに反映することで、同じ問い合わせが何度も来る状態を回避できます。
一方で、FAQが更新されず形骸化してしまうケースも少なくありません。特に、変更やバージョンアップに追随できていないFAQは、逆に混乱を招く要因となります。
そのため、FAQはつくるだけでなく、継続的に育てる仕組みが必要です。
ヘルプデスクのよくある課題とその背景
ヘルプデスクは企業の最前線でありながら、多くの現場で運用上の課題を抱えています。ここでは、代表的な4つの課題と、その背景を明らかにします。
問い合わせが集中する時期と閑散期の差が大きい
社外ヘルプデスクであれば、提供している製品・サービスの特性によっては、急激に利用頻度が上がりトラブルが発生しやすくなる時期があるかもしれません。社内ヘルプデスクの場合も、月初・月末など、特定のシステムやアプリケーションの利用頻度が上がる時期があるでしょう。
問い合わせの集中する時期と閑散期の差がある場合、人員配置を多い時期に合わせれば閑散期に人件費が無駄になり、逆に閑散期に合わせれば問い合わせが集中する時期に残業が発生してしまいます。
難易度が高い問い合わせの対応が困難
数多く寄せられる問い合わせのうち、多くはすでにFAQやマニュアルに記載してある内容であったり、似たような質問に偏っているでしょう。
ただ、時には、熟練者や専門知識を持った担当者でないと回答できないような難易度の高い問い合わせも届きます。この場合、調査が必要だったり、関連部門へのエスカレーションを行ったりするため、その場では回答ができません。
回答までに時間がかかることは、ユーザーの満足度の低下につながります。社内ヘルプデスクであればまだしも、社外ヘルプデスクであれば顧客が相手なだけに死活問題にもなりかねません。
ナレッジが蓄積されない
属人化の結果として、対応履歴や解決手順がナレッジ化されず、同じ問い合わせに何度も対応する非効率な状況が生まれます。
ナレッジが蓄積されない主な要因は次のとおりです
- 忙しさにより記録の余裕がない
- ナレッジ化ツールが整備されていない
- 情報の整理や形式が属人的で検索性が低い
こうした環境では、問い合わせが来るたびに「一から考える」対応になり、属人化と負荷集中がさらに加速してしまいます。
本来は不要なはずの問い合わせが多く寄せられる
FAQやマニュアルなどを作成し、ユーザーに公開している企業は多いです。しかし、すでに記載してある内容であるにも関わらず、「探したけど見つからなかった」「自分で調べるのは面倒くさい」といった理由から、本来は不要であるはずの問い合わせが多く寄せられ、その対応に時間を取られてしまうという悩みを抱えるヘルプデスクは少なくありません。
ユーザーに対し、FAQやマニュアルの周知を行うとともに、使いやすいFAQ・マニュアルへ改善するといった対処が必要です。
社内ヘルプデスク運用の改善ポイント
こうした課題に対して、属人化の排除・対応の見える化・対応力の底上げを図るための実践的な改善策を5つ紹介します。
ツール活用(チケット管理・チャットボットなど)
属人的な対応が常態化しているヘルプデスクにおいて、業務の可視化と効率化を実現するうえで有効なのが、専用ツールの導入です。
たとえば、JiraやBacklogといったチケット管理ツールを活用すれば、問い合わせの受付から解決までの流れを案件単位で追跡でき、誰が・何を・どこまで対応したかが一目でわかるようになります。これにより、対応漏れや重複対応のリスクが大幅に軽減されます。
また、チャットボットの導入により、よくある質問や定型業務への即時回答が可能になります。これにより、ユーザー自身が問題を自己解決できる割合が高まり、オペレーターの負荷を軽減できます。
ナレッジ共有とFAQ整備
ヘルプデスクにおいて「また同じ質問が来た」「対応できる人が限られている」といった課題は、ナレッジが適切に蓄積・共有されていないことが原因であるケースであることが多いです。
対応履歴や対応ノウハウをFAQやナレッジベースに反映させることで、問い合わせ件数そのものを減らすことができます。
また、新人や兼任担当者が短時間で対応可能になることで、教育コストの削減や業務平準化にもつながります。
特に効果的なのは、以下のような整備です。
- よくある質問のカテゴライズと構造化
- 検索性の高いUI設計
- 更新頻度を担保する運用ルールの設置
FAQが古い情報のまま放置されるような状態では逆効果になります。重要なのは「つくる」よりも「育てる」姿勢。定期的な見直しと、ユーザーからのフィードバックをもとにした改善サイクルの定着が、ナレッジ活用の成功を左右します。
対応フローの標準化・可視化
担当者ごとに対応がバラバラで、「あの人にしかできない」「判断基準が曖昧」といった状態では、業務の属人化と品質のばらつきが避けられません。
この課題を解消するには、問い合わせ対応のプロセスを標準化し、明文化することが不可欠です。
- 問い合わせ種別ごとの対応手順をマニュアル化
- 確認すべきポイントをチェックリスト化
- チケット対応状況の見える化
これらにより、経験の浅い担当者でも一定の水準で対応が可能になり、対応スピードと品質の底上げが実現できます。
また、標準化されたフローは改善の単位にもなります。業務の見直しや効率化を図る際に、どこをどう変えるかが明確になりやすく、全体の運用最適化にもつながります。
代行・外部パートナーの活用という選択肢
問い合わせ対応の全てを社内でまかなおうとすると、リソースの逼迫や品質低下につながりがちです。
特に、「定型的な問い合わせが多い」「夜間・休日対応も必要」といったケースでは、一部業務の外部委託が現実的な解決策となります。
たとえば以下のような分担が可能です
- 一次受付のみ外注し、二次対応は社内で対応
- マニュアル化された操作案内のみを委託
- 夜間や多言語対応など、特定時間・領域を分離運用
これにより、社内リソースをより戦略的な業務に集中させられるほか、対応体制の拡張性も向上します。
ただし、外注にはセキュリティや情報連携の面で注意が必要です。対応範囲・品質基準・データ取り扱いポリシーなどを明確に定義し、内部と外部が連携するためのオペレーション設計が欠かせません。
ヘルプデスク代行の比較ポイント
外部委託を検討する際には、とりあえず安価なところに頼むだけでは失敗のリスクが高まります。
業務内容にマッチしたパートナー選定を行うためには、以下のような比較観点を持つことが重要です。
| 比較項目 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| 対応時間 | 24時間対応が可能か、夜間・休日対応の有無 |
| 対応範囲 | システム操作、アカウント管理、障害切り分けなど |
| 柔軟性 | ルールの変更・運用調整にどこまで対応可能か |
| 品質保証 | SLA、一次解決率、CSスコアなどの有無 |
| セキュリティ | データ取り扱い、アクセス管理、ログ取得体制 |
| 体制・運用 | 担当者の専任可否、レポート・会議頻度など |
これらを事前にチェックリスト化して比較することで、表面的なコストではなく中長期的な成果に繋がるパートナー選びが可能になります。
また、導入後も定期的な振り返りや、改善提案の有無などを基準に、パートナーとの関係を健全に維持することが重要です。
社内ヘルプデスクの見直しを検討すべきタイミング
問い合わせ件数が急増している
社内ヘルプデスクを見直すべき最も分かりやすいサインの一つが、問い合わせ件数の急激な増加です。企業の成長やテレワーク対応、SaaS導入などIT環境が変化する中で、ヘルプデスクの負荷は一気に跳ね上がります。
特に、複数の拠点を展開し始めた企業や、社員数が短期間で増加した企業では、IT周辺の問い合わせが急増する傾向があります。また、業務システムやネットワーク環境の刷新など、社内で何らかの大きな変更があった場合にも、一時的に問い合わせが殺到することがあります。
このとき、定型的に処理できないイレギュラーな問い合わせが増えると、1件あたりの対応工数がかさみ、現行の体制では処理しきれないボトルネックが生じます。
こうした急増に備えるには、リソースの柔軟な再配置や、ツール活用による効率化、外部委託の検討などが必要不可欠です。
業務負荷が現場を圧迫している
ヘルプデスクへの問い合わせ対応が増えると、それを担当する情報システム部門や管理部門のリソースが圧迫されます。本来であればDXの推進や業務プロセスの改善、セキュリティ施策の立案といった攻めのIT施策に注力すべきIT部門が、火消し対応ばかりに追われてしまう状態に陥りがちです。
特に深刻なのが、一時対応が多すぎることで、中長期の改善活動に時間を割けない構造になってしまう点です。
「属人的に対処するしかない」「そもそも手が回らない」といった声が日常的に現場から出てくるようであれば、既に警戒ラインを超えています。
また、一部の担当者に業務が集中すると、その負担は心理的・肉体的にも大きくなり、モチベーション低下や離職リスクに直結します。 対応ミスやトラブルの見落としといった二次被害を生むこともあるため、現場が疲弊している兆候を見逃さないことが重要です。
属人化により運用が不安定になっている
ヘルプデスク業務が属人化している場合、特定の担当者がいなければ業務が回らないという危機的な構造になってしまいます。
「この人しか対応できない」「前任者の記憶頼みで引き継ぎができない」といった状況が続いている場合は要注意です。特にベテラン担当者の退職や長期休暇などが重なると、対応品質が急激に低下し、対応が滞るケースも珍しくありません。
さらに、属人化された業務はナレッジとして共有されにくく、業務の可視化・標準化が遅れることで改善スピードも鈍化します。結果的に、業務プロセスがブラックボックス化し、組織としての持続可能性が損なわれるリスクが高まります。
対応フローやナレッジのドキュメント化、チェックリストの整備など、平時からの見える化と仕組みづくりが不可欠です。
IT部門がコア業務に集中できていない
情報システム部門の役割は、社内のIT環境を整備するだけでなく、企業の競争力を高めるための戦略的なIT活用を牽引することにあります。しかし現実には、ヘルプデスク対応に忙殺されて、戦略業務が後回しになるケースが多々あります。
「セキュリティ施策が着手できない」「新システムの検討が遅れている」「データ基盤の構築が進まない」といった課題が放置されているなら、それはヘルプデスク業務がIT部門の足かせになっているサインです。
こうした状況が続くと、情報システム部門の役割は単なる作業代行部隊と化し、企業の成長を支える戦略的部門としての価値を発揮できなくなります。
短期的には現場の利便性が保たれていても、長期的には企業全体の生産性・競争力に悪影響を及ぼすリスクがあるため、部門としてのリソース配分と業務設計の見直しが急務です。
まとめ
ヘルプデスクは単なる問い合わせ対応の窓口ではありません。
社内外の業務を支えるインフラであり、対応品質が業務の生産性や顧客満足を大きく左右します。属人的な対応から脱却し、誰がやっても一定品質を担保できる仕組みへと進化させられるかどうか。これが、これからのヘルプデスク運用の成否を分ける分岐点となります。
対応件数の増加や業務負荷の偏りを個人のがんばりで乗り切る時代は終わり、業務の仕組み化をどう設計するかが問われる時代に入りました。
いま一度、現状の体制や課題を振り返り、改善に向けた第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
この記事の著者
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。