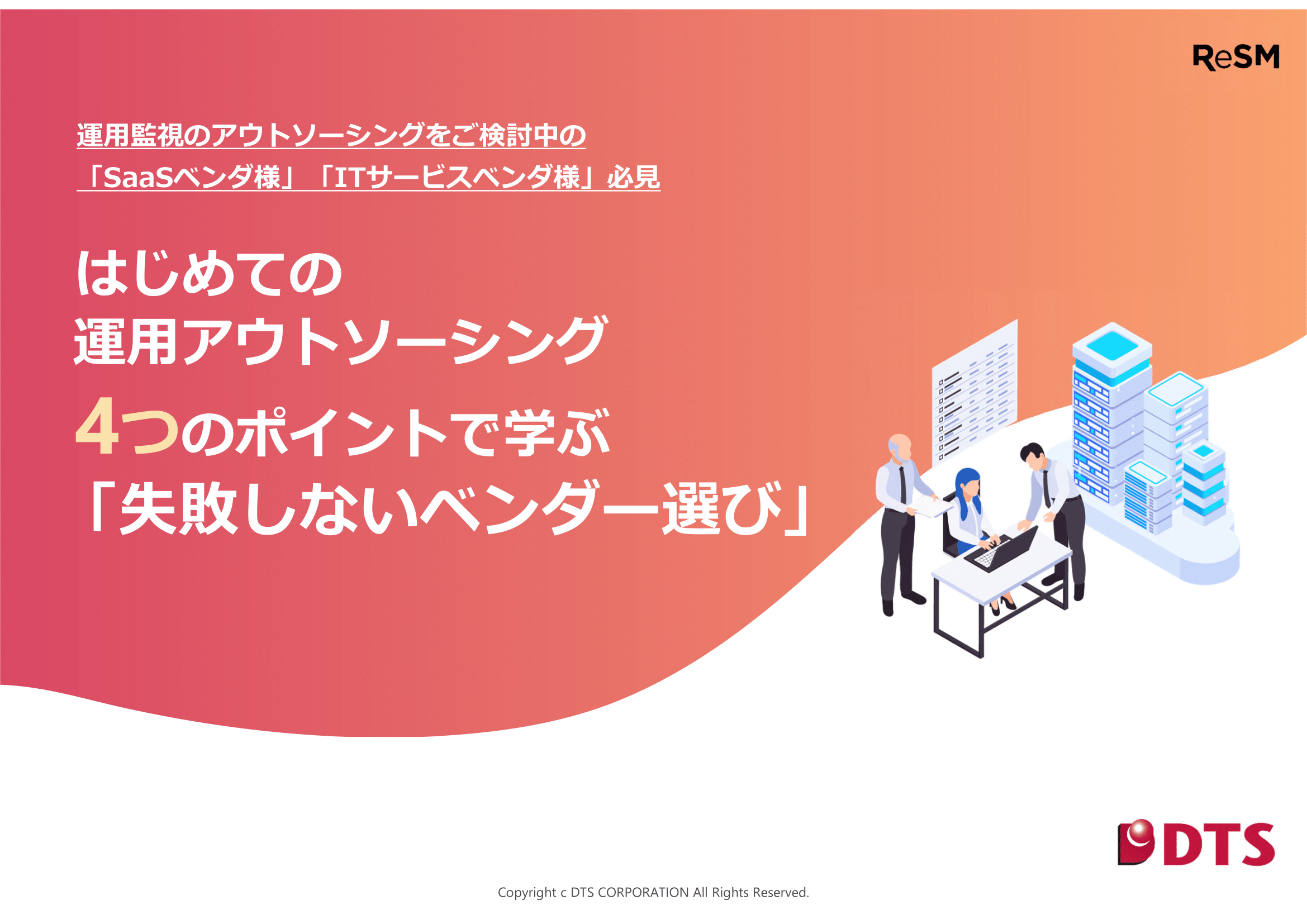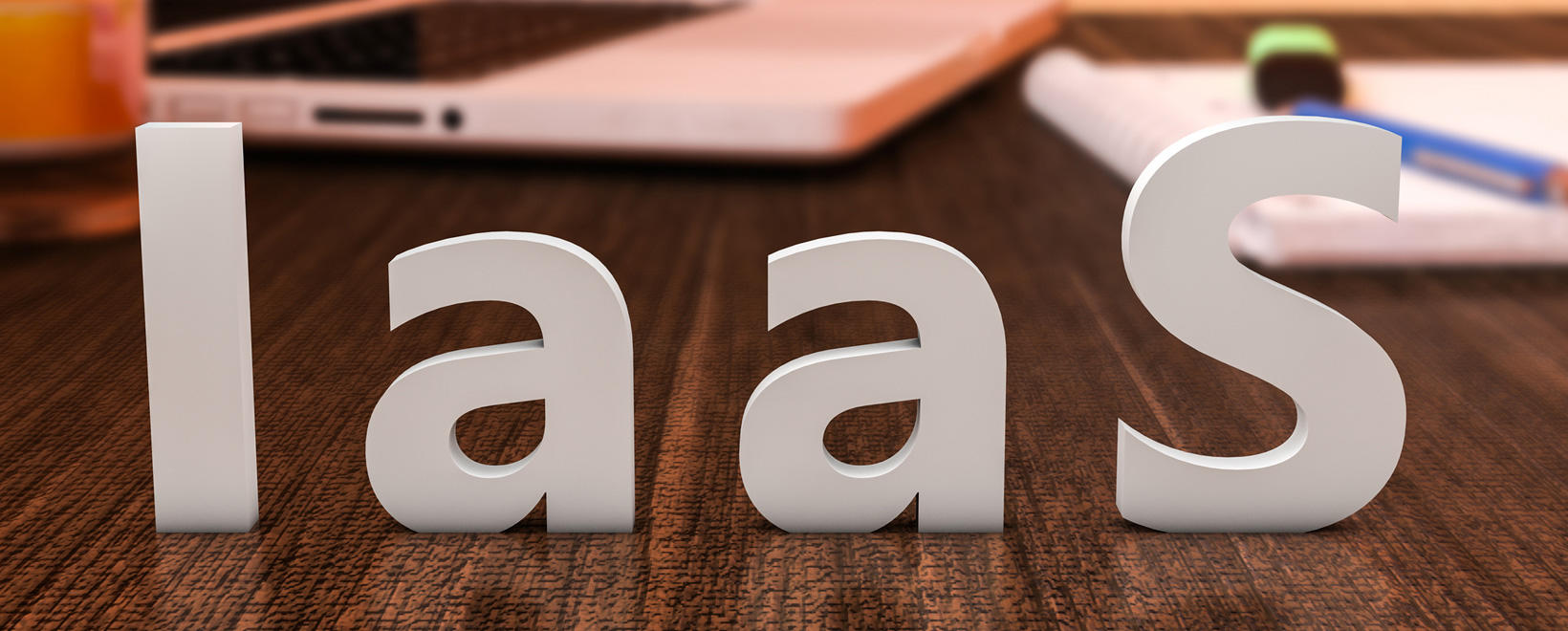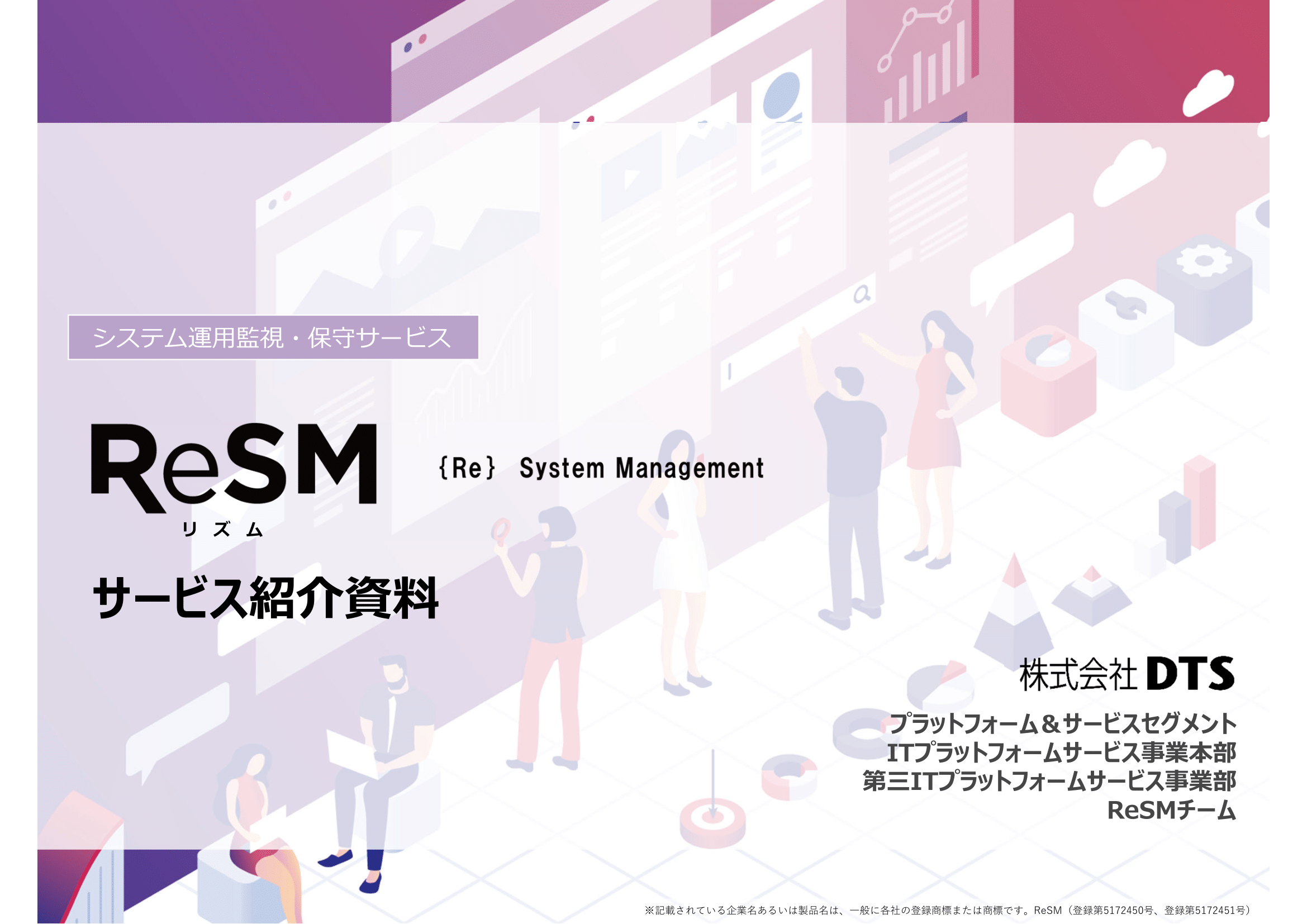AWSでできること 導入前に知っておきたい知識と代表的なサービス

3大クラウドサービスといえば、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)ですが、なかでもAWSは、世界トップシェアを誇り、全世界で22の地理的リージョンで提供されています(※2019年9月の数値)。 コストの低さや用意されているサービスの種類の豊富さ、必要に応じて規模のサイジングが可能といったメリットから選ばれています。 本コラムでは、AWSの代表的なサービスをご紹介いたします。
AWSとは
AWSとは、Amazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスで、低コストでスピーディにITインフラを構築できます。また、Webサービスにとどまらず、オンプレミスのVMwareなどをAWS上へ移行する「AWS Server Migration Service」、AWS上で下層ネットワークを作成・利用できる「Amazon VPC」など、幅広いサービスが用意されています。
ユーザーは、これらのサービスの中から、最適なITリソースを利用することができます。
AWSのサービスの種類については「AWSの提供する代表的なサービス」で詳述します。
高セキュリティ環境で、安定している点もAWSの特長です。
AWSと今までのサービスとの違い
AWSの提供サービスをご紹介する前に、クラウドサービスとオンプレミスの違い、パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いについて、おさらいしておきましょう。
・クラウドサービス(AWS)とオンプレミスの違い
そもそも、クラウドサービスは従来のオンプレミスとはどう違うのでしょうか?
オンプレミスとは、ハードウェアやソフトウェアを自社で保有して運用する形態をいいます。自社で保有しているため、メンテナンスなども自社で行う必要があります。
ただ、自社のルールで運用できるため、情報セキュリティ面などでメリットのある運用方法です。
一方、クラウドサービスとは、ハードウェアやソフトウェアの設置場所などを意識せずに利用できる形態をいいます。
コンピューター資源を基本的にインターネット経由でオンデマンドで必要な分だけサービスとして利用できます。データの保存先も基本的には自社内ではなく外部のデータセンターとなります。
・パブリッククラウド(AWS)とプライベートクラウドの違い
クラウドサービスは、「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」に分かれます。
パブリッククラウドとは、複数の無関係なユーザーでクラウドサービスに使われるサーバーやデータベース、ソフトウェアなどを共有する利用形態(マルチテナント)です。
前項でお伝えしたクラウドサービスの特徴は、このパブリッククラウドのもので、AWSはパブリッククラウドに該当します。
プライベートクラウドとは、自社に専用の環境を構築し、それを利用する形態です。
プライベートクラウドは、さらに「オンプレミス型」と「ホステッド型」に分かれます。
オンプレミス型は、前項でお伝えしたように、企業内に個別に構築された環境を利用するものです。
一方、ホステッド型は、社内にハードウェアなどを設置するのではなく、サービスプロバイダーが自社のために構築してくれた外部環境へVPN(Virtual Private Network)などの専用線を通じてアクセスして利用します。
AWSの提供する代表的なサービス
AWSが提供するサービスは、25カテゴリにまたがる200にものぼります。
ここでは、その中から代表的な7つのサービスをご紹介いたします。
・AmazonEC2(Amazon Elastic Compute Cloud)
AmazonEC2は仮想レンタルサーバーのサービスで、AWS上にLinuxやWindowsの仮想サーバーを構築することができます。
特徴は、最短で数分から作成できるスピーディさと、柔軟なコスト体系です。数クリックの動作で構築でき、利用する容量とアクセス量によって料金が自動的に変化するため、余分なコストもかかりません。
サーバーの台数や、メモリ、CPUといったスペックも簡単に変更することができ、仮想ネットワークが用意されているため、冗長化の際もネットワークを意識せずに拡張できます。
RDS(Amazon Relational Database Service)
RDSは、AWS上で利用できるリレーショナルデータベースサービスで、低額で高速処理できる点などが特徴です。
データベースのセットアップや拡張などを数クリックで簡単に行うことができ、データベースサーバーの管理も不要です。
データベースエンジンは、Amazon Auroraをはじめ、MySQL、MariaDB、Oracle、Microsoft SQL Server、PostgreSQLの一般的な6種類から選択できるため、既存のデータベースで利用していたコードやアプリケーションなどを移行してそのまま利用できます。
・Amazon CloudFront
Amazon CloudFrontは、Webページに掲載されたファイルを高速化して配信できるサービスです。静的なページはもちろん、動画やアプリケーションなどのコンテンツ、ツールを、遅延時間を抑えながら配信できるようになります。Amazon CloudFrontを活用することで、ユーザーがストレスなくコンテンツやツールを利用できる環境を整えられます。
利用料金は、従量課金制となっています。
実際にAmazon CloudFrontを活用しているサービスとして、たとえば「Amazon Prime Video」などがあります。
・Amazon S3(Amazon Simple Storage Service)
Amazon S3は、格納するデータ量の上限を考えずに利用できるストレージサービスです。データ量に上限がないほか、データ消失の可能性が極めて低い点が大きな特徴で、単にデータの格納先としてだけでなく、コンテンツ配信元としての利用も可能です。長期的にデータ保管を行う場合は、オプションでGlacierやGlacier Deep Archiveを選択すると良いでしょう。
Amazon S3に格納したデータは、インターネット経由でアクセスできます。従業員ごとにアクセス権限を付与することもできます。
・AWS Lambda
AWS Lambdaは、サーバレスコンピューティングです。アプリケーション開発を行う際に利用できる「FaaS(Function as a Service)」で、Webアプリケーションサーバー、Webサーバーといった「サーバー」の存在を意識せずにプログラムを実行することができます。
たとえば、プログラムコードだけを用意すれば、アプリケーション開発やプログラム開発が行えます。
利用料金は、100万リクエストまで無料で、その先はリクエスト単位での従量制課金となっています。
・Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatchは、AWSの提供する監視・運用サービスで、主にAWSの監視を目的として活用されます。フルマネージドのため、セットアップが不要で、さまざまなメトリクス(検出の項目)設定が可能です。
Amazon CloudWatchには、「CloudWatch」「CloudWatch Logs」「CloudWatch Events」の3つのサービスがあり、もっとも基本的なサービスが「CloudWatch」、「CloudWatch Logs」はOSやアプリケーションの各種ログを取得するサービス、「CloudWatch Events」はAPIのイベントをトリガーとしてアクションを実行させるサービスとなっています。
・Amazon Route53
Amazon Route53は、AWSのDNSサービス(ドメイン名を登録したり、ドメイン名をIPアドレスに変換したりするサービス)です。ちなみに「53」というのは、DNSの送信元ポート番号です。
PCからインターネット経由でWebサイトを閲覧したりメールアドレスを送受信したりするためだけでなく、AWSと自社のオンプレミス環境のサーバーをつなげるための名前解決のためにも利用できます。
まとめ
クラウドサービスとオンプレミスの違いや、パブリッククラウドとプライベートクラウドの違い、AWSの主なサービスについてご紹介いたしました。
AWS では、25カテゴリにまたがる200を超える豊富なサービスが用意されているため、必要に応じて組み合わせることで、低コストでさまざまな環境の構築が可能ですが、あまりに数が多くて迷ってしまう方も多いでしょう。こちらでご紹介した7つのサービスを足がかりに、自社に最適なサービスを選択してみてはいかがでしょうか。
ただ、AWS導入には、ある程度の専門知識と、導入後の運用体制も必要になってきます。
当社DTSでは、AWSの導入支援から運用サポートまで一気通貫でご提供しております。
導入・運用に不安をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の著者
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。