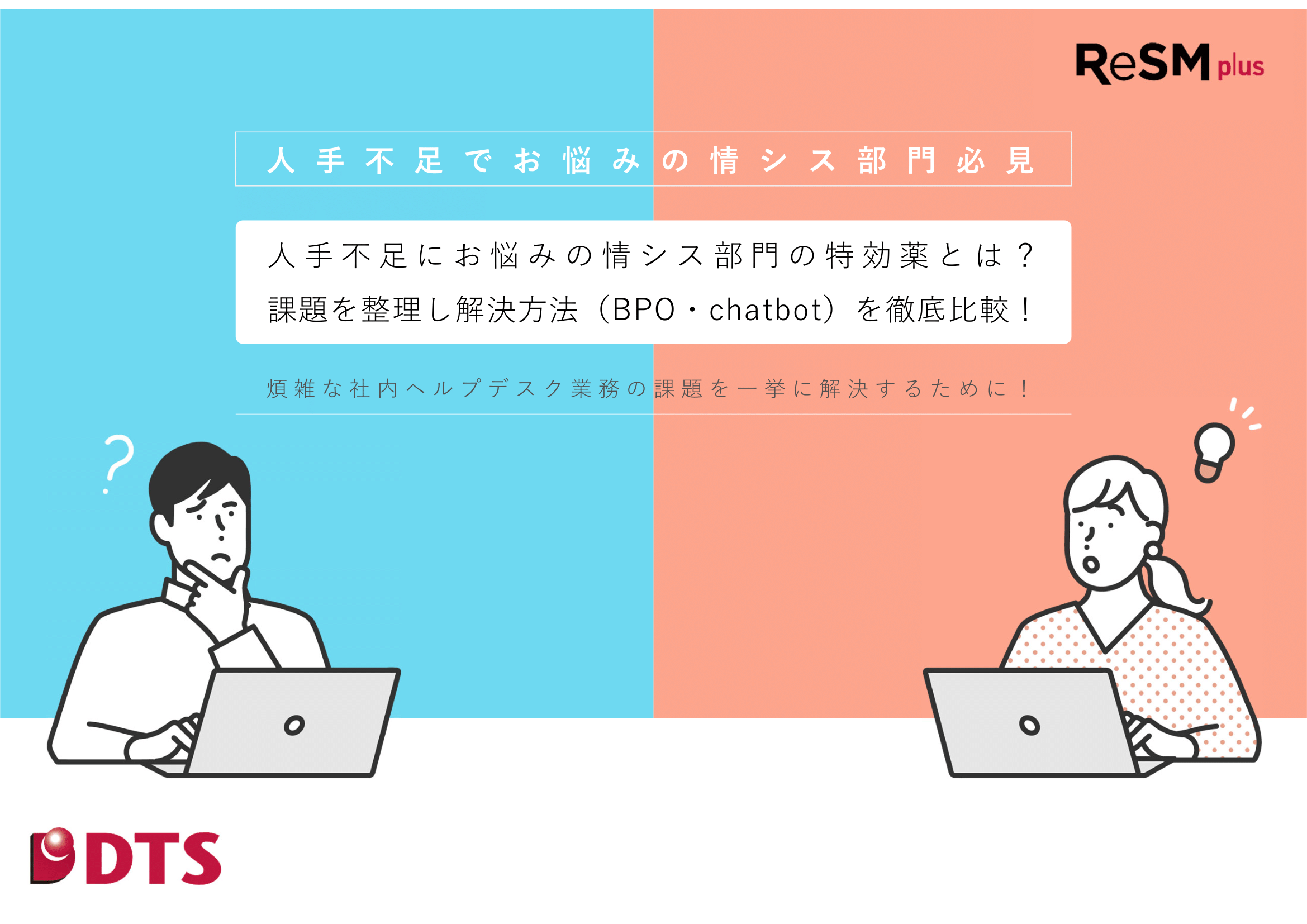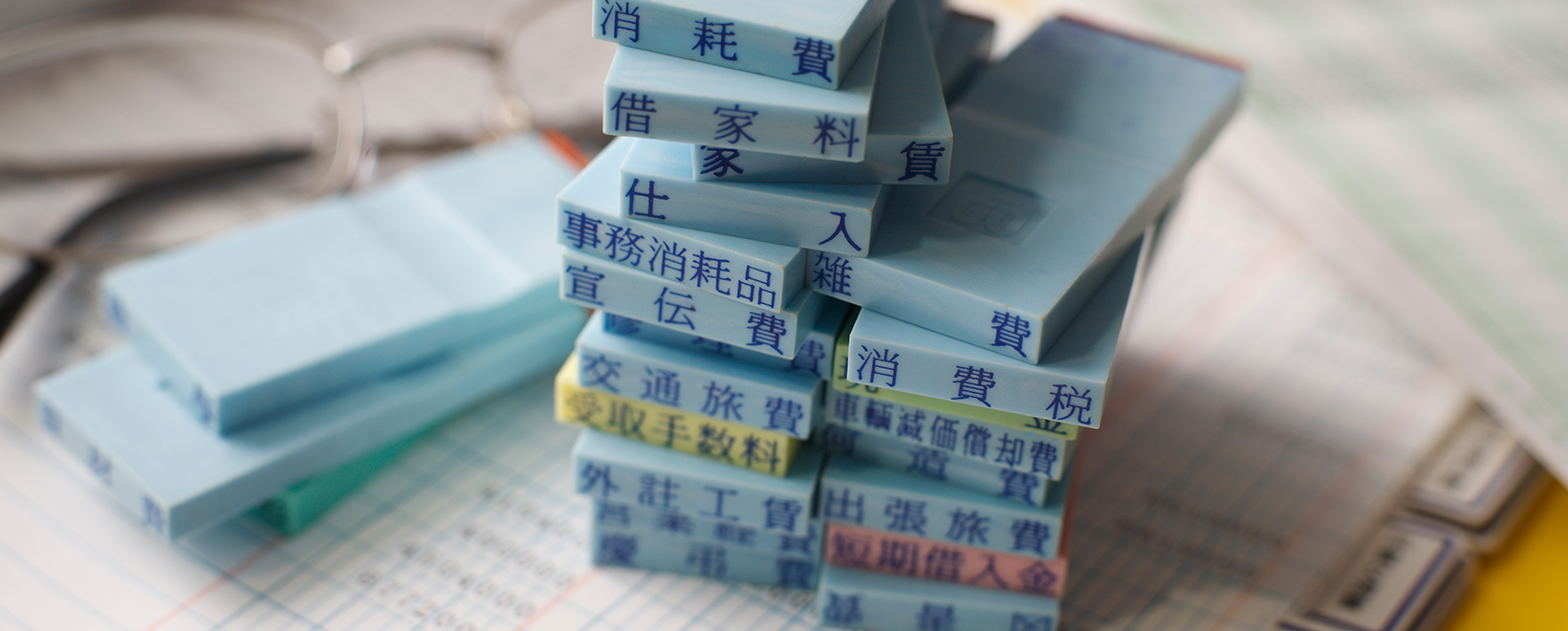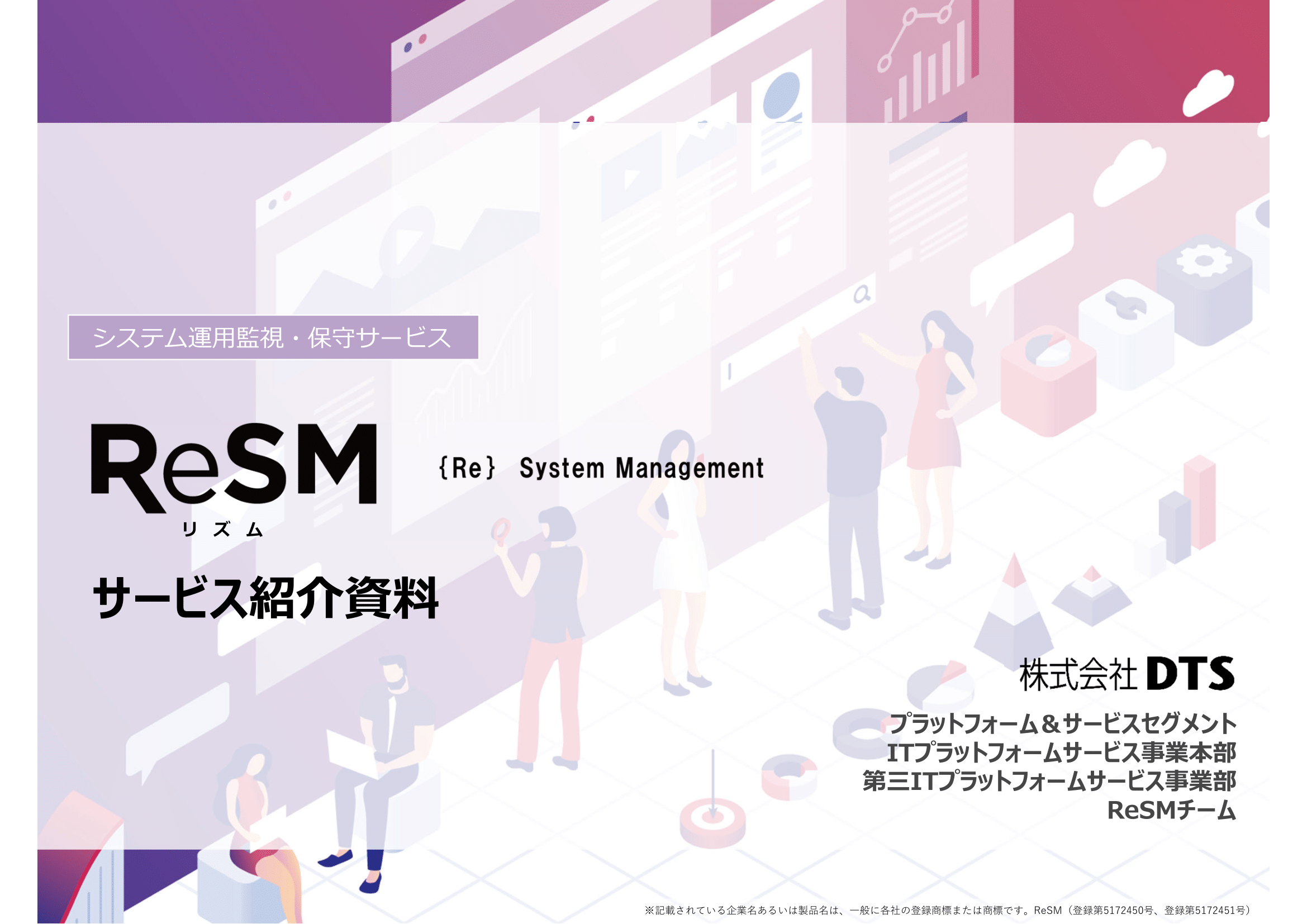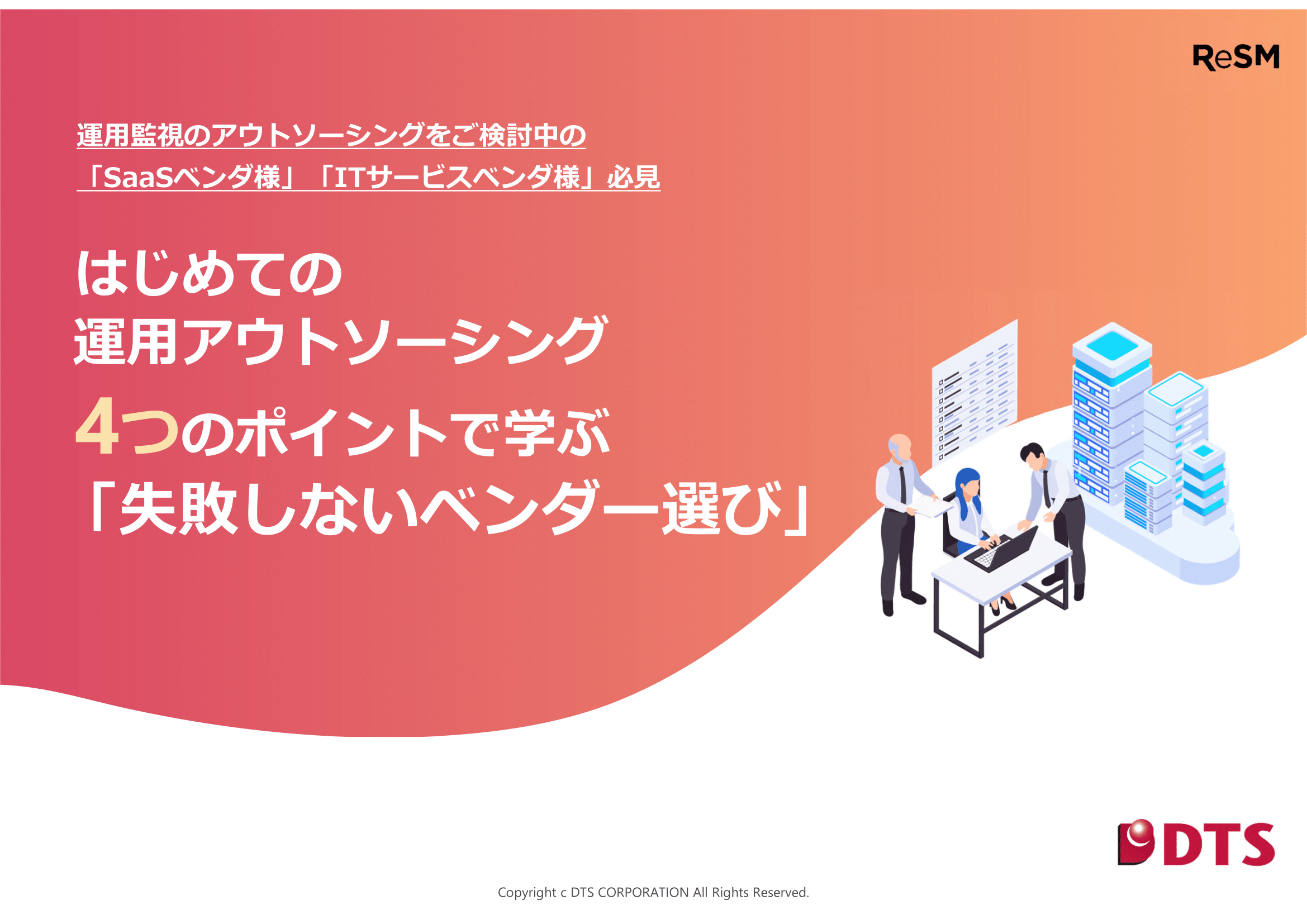情シスの効率化を進めるために、社員のITリテラシーを高める方法とは

「デジタルツールを導入したが、効果がない…」「全社で使って欲しいのに、特定の部門だけ使ってくれない…」という場合、もしかしたら社員のITリテラシーに問題があるのかもしれません。現在のデジタル社会ではITリテラシーを高めることは避けて通れません。とはいえ社員の年齢層も幅広く、デジタルに苦手意識を持ち、ツールの正しい使い方を理解していない人がいるのも事実。ITリテラシーが低いままだとどのような影響があるのでしょうか。そしてITリテラシーを高めるにはどうすればよいでしょうか。
そもそもITリテラシーとは?
コロナ禍をきっかけとしてテレワークが一気に普及し、Web会議やチャットツールといった非対面のコミュニケーションツールが当たり前のように使われるようになりました。また、社内のシステムも社外からアクセスできるようにクラウドに移行するケースも活発化しています。
ツールを使いこなすには、利用者のITリテラシーが求められます。導入したツールを使える人が少ないと、コストに見合う効果が得られずデジタル化が進みません。
ITリテラシーとはそもそもどのようなものなのでしょうか。日本総合研究所「本格的なデジタル社会の実現に向けたデジタル・リテラシーとは」によると、ITリテラシーを次の3つと定義しています。
・デジタルツールを操作できる
・利活用の知識を持つ
・リスクを回避できる
つまり操作を覚えるのはもちろん、どのようなことに活用できるのかという知識を持ち、詐欺・ウイルス感染の被害や情報漏えいを誘発するような誤った使い方をしない、というスキルが求められています。
また、厚生労働省の「平成29年度基礎的 IT リテラシーの習得カリキュラムに関する調査研究報告書」によると、「現在入手・利用可能な IT を使いこなして、企業・業務の生産性向上やビジネスチャンスの創出・拡大に結び付けるのに必要な土台となる能力」と定義されています。ITリテラシーとビジネスにおけるインパクトの関係を表現した定義になっています。
コロナ禍では緊急事態となり「取り急ぎ社外から業務ができる環境を作りたい」という「取り急ぎデジタル化」の傾向がありました。しかしコロナ禍が長期化したことで、変化に強い企業体質を作るべくデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む機運が高まっています。経済産業省の「DXレポート2」においても「ビジネスにおける価値創出の中心がデジタルの領域に移行」するとみています。「顧客の変化に対応するにはデジタルは必須」であり、「ビジネスを今変化させなければ、デジタル競争の敗者となる」と強く警告しています。
ITリテラシーが低い社員が多いとどうなる!? 社内のデジタルデバイドの課題
定義を見てもわかるように、ITリテラシーは全てのビジネスパーソンが持つべきスキルになりつつあります。最近では、ITリテラシーの高い人と、そうでない人との格差が広がり、業務に影響が発生する「社内のデジタルデバイド」の問題も取り上げられるようになりました。社内全体でITリテラシーの底上げができない場合に、どのような影響があるのでしょうか。
・生産性が上がらない
最近では、プログラミングの知識がなくてもアプリケーションを開発できるツールが増えています。そのため業務を良く知るビジネス部門の担当者が、アプリケーションを作ることも増えてきました。今までIT部門頼りだったシステム導入も、適宜協力してもらいながらビジネス部門で進めることも可能になっています。
IPAの「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査」によると、全社的にDXに取り組んでいる企業では「業務の効率化による生産性向上に効果があった」と回答した割合が71・6%であるのに対して、部署ごとに独自または個別にDXに取り組む企業では27%と大きく差が開きました。つまりIT部門やITリテラシーの高い部門だけ取り組んでも効果が薄いと言えます。全ての部門で使いこなしてもらう土壌づくりで、デジタルデバイドを解消していくことが必要です。
・コミュニケーションがうまくいかない
総務省の「令和3年度版 情報通信白書」によると、コミュニケーションツールである「Microsoft Teams」の日次ユーザー数は2020年3月11日からの1週間で1200万人増加しました。そして2020年10月には1.5億人にまで達しています。またWeb会議ツールである「Zoom」は2020年4月3日から19日間でアクティブユーザーが1億人増加しました。コミュニケーションの方法が劇的に変わるなかで、デジタルツールを使いこなせない人がいると、コミュニケーションの手段をその人に合わせる必要が出てきます。遠隔地にいる人と迅速にコミュニケーションできるというメリットが享受できなくなり、デジタルツールを使えばできていたコミュニケーションが取れなくなります。デジタルツールを使いこなせるように教育して、デジタルデバイドを解消しなければなりません。
・定量的なデータをもとに意思決定ができない
ITリテラシーというとデジタルツールの使いこなしが注目されますが、データの利活用とも深く関連しています。今やデータは企業にとって貴重な資源です。例えば、あるデジタルツールについて社員が使っているのかどうか、どのように判断すればよいでしょうか。管理者が「みんなが活発に使っている」と思っていても、実は使っていない可能性もあります。しかしツールへのアクセス数の推移を見れば、何人が使っているのか、どの時間帯に使うことが多いのか、といった定量的な事実がわかります。例えば営業部門でアクセス数が少ないということがわかれば、営業部門にヒアリングして対策を打つこともできます。
しかしアナログな業務はデータが蓄積されません。適切な意思決定をするためにはデータが必要で、データを蓄積するにはITリテラシーを向上させてデジタルツールを活用する必要があります。
・セキュリティのリスクが高まる
IPAが発表した「情報セキュリティ10大脅威 2022」によると、「テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃」が4位になりました。テレワークが一気に普及したために、その混乱に漬け込んだ攻撃が増えています。ある企業では、テレワークをしていた従業員の端末が感染し、社内ネットワークが攻撃されたという例があります。
テレワークでデジタルツールが一気に普及したことで、誤った使い方をすると、社内ネットワークを攻撃されたり、情報漏えいが発生したりといった危険が高まります。基本的なルールを徹底し、正しい使い方ができるような判断能力を身に付けてもらう必要があります。
・BCP(事業継続計画)の対策ができない
コロナ禍においては、必要に応じてテレワークと出社を組み合わせることができますが、災害時は出社すらできないかもしれません。変化に柔軟に対応する企業体質を作るなら、完全にリモートで業務ができるように環境整備はもちろんのこと、社員の意識を高めることも必要となります。
内閣府の「非常事態に対してレジリエントな経済社会の構築に向けて」によると、コロナ禍において自社のBCPが機能しなかった企業は28%にのぼることがわかりました。既存のBCPをもう一度見直し、あらゆるリスクに耐えうる「オールハザード型」のBCPを構築するべきだとしています。
コロナ禍でBCPが機能しなかった要因は、システム上の問題も多いかもしれませんが、社員のITリテラシーが追い付いていなかった可能性もあります。システムの整備だけではなく、不測の事態に耐えうるITリテラシーを備える必要があります。
情シス部門にも大きな負担に
こうした理由から、全ての社員のITリテラシーを高めて社内のデジタルデバイドを解消する取り組みを、できるだけ早く推進していくことが求められています。とはいえ、情報システム部門には大きな負担がかかります。経済産業省の「我が国におけるIT人材の動向」によると、日本のIT人材がIT関連企業に従事する割合は72%。それに対してアメリカは34.6%、ドイツは38.6%となっています。つまり日本は欧米と比較して、IT人材がIT関連企業に従事する割合が高く、ユーザー企業の情報システム部門に従事する割合が低いという特徴があります。
そもそも将来IT人材が不足するという予測もあります。経済産業省の「IT 人材需給に関する調査」によると、IT需要が高まり、生産性が現状から改善されなかった場合、2030年にはIT人材が78.7万人不足すると試算されています。つまり、IT人材が不足しており、IT人材がユーザー企業に従事する割合も低いということになります。情報システム部門が増員したくても採用がままならず、今いる担当者に負荷が集まる構造になっていると言えます。
特に深刻なのが、小規模企業です。中小企業庁の「最近の中小企業の景況について」によると、小規模企業は日本の企業の87 %、9割弱を占めています。小規模企業の情報システム部門では、担当者が1人またはゼロというケースもあります。担当者も他部門と兼任している場合もあり、負担が集中していることが問題となっています。
ITリテラシーを高めるには教育が必要
こうした状況の中で従業員のITリテラシーを高め社内のデジタルデバイドを解消するには、教育が欠かせません。情報システムに負担がかかる取り組みですが、ITリテラシーが高まれば情報システム部門への問い合わせ対応やサポート作業の減少につながります。
ここからはITリテラシーを高める方法をご紹介します。
・ITリテラシー診断の実施
まず社員がどのくらいのITリテラシーを持っているのか、現状を把握する必要があります。また社員にも自分のITリテラシーがどのくらいのレベルかを知ってもらうことも大切なポイントです。
そのためにおすすめなのが、外部資格試験の受験です。例えばP検協会運営の「P検(ICTプロフィシエンシー検定試験)」はITに関するさまざまな領域から出題されます。1級~5級までありますが、5級はオンラインで無料受講できるため、気軽に受験することができます。またIPA(情報処理推進機構)の「ITパスポート」もあります。全ての社会人を対象とした国家試験ですが、難易度高めです。
> P検(ICTプロフィシエンシー検定試験)
> ITパスポート
・社内研修の実施
社内でよく使うツールを普及させるには、社内研修が最も効果的です。外部研修を利用すると人手がかからず効率的ですが、その部門の仕事に合った使い方を教えてもらったり、社内のルールを認識してもらったりという目的には向きません。社員全員に研修をするのは時間もコストもかかるため、部門から参加メンバーを選抜して研修を行い、部門に持ち帰って広めてもらうという方法もあります。選抜メンバーが自発的に広めてくれるので、効果が高いという声もあり、ぜひ試してほしい方法です。
・ナレッジシェアリング、マニュアルの作成
他の部門がどのように使っているのかを共有すると、より自分ごと化できるようになります。またマニュアルは困った時にすぐに参照できるため、利用者側にとっても便利です。最近では画像や動画をアップして手軽にマニュアルを作成できるツールも登場しています。情報システム部門としては、ツールを整備しマニュアルのテンプレートを用意するといった方法で、誰でもマニュアルを作成できるようにサポートするとよいでしょう。
・ルールの策定、アクセス権限の設定
デジタルツールの管理者権限を一般の社員に持たせてしまうと、重要な情報の漏えいや誤ってデータを削除するといったことが発生してしまいます。使い方のルールを整備して周知しておくとともに、アクセス権限を可能な限り細かく設定しておきましょう。
・使用率の分析結果によるサポート
デジタルツールによっては、部門別の使用状況を取得できる機能もあります。この部門だけ使用率が低いということがあれば、ヒアリングして原因を探ります。業務とギャップがあることもあれば、使い方がわからないということもあるかもしれません。問題を抱える人に個別に対応して底上げを図ることも大切です。
日々のサポートを充実するために社内サポートデスクの拡充を
教育が充実していたとしても、ついていけない従業員がいるかもしれません。デジタルデバイドと呼ばれるITリテラシーの格差が広がると、全体の底上げにはつながりません。日々デジタルツールの操作で困った時に手伝えるよう、社内サポートデスクを拡充するのも一つの方法です。「社内に困っている人が多いのはわかっているけど、情報システム部門の人手が足りていない…」といった場合にもアウトソースしやすい領域です。ReSMサービスでも社内ヘルプデスクをデジタル変革する「ReSM plus」をご提供しています。社外のリソースを活用して、デジタルツールの活用を広げていきませんか。
この記事の著者
近い課題のコラムを見る
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。