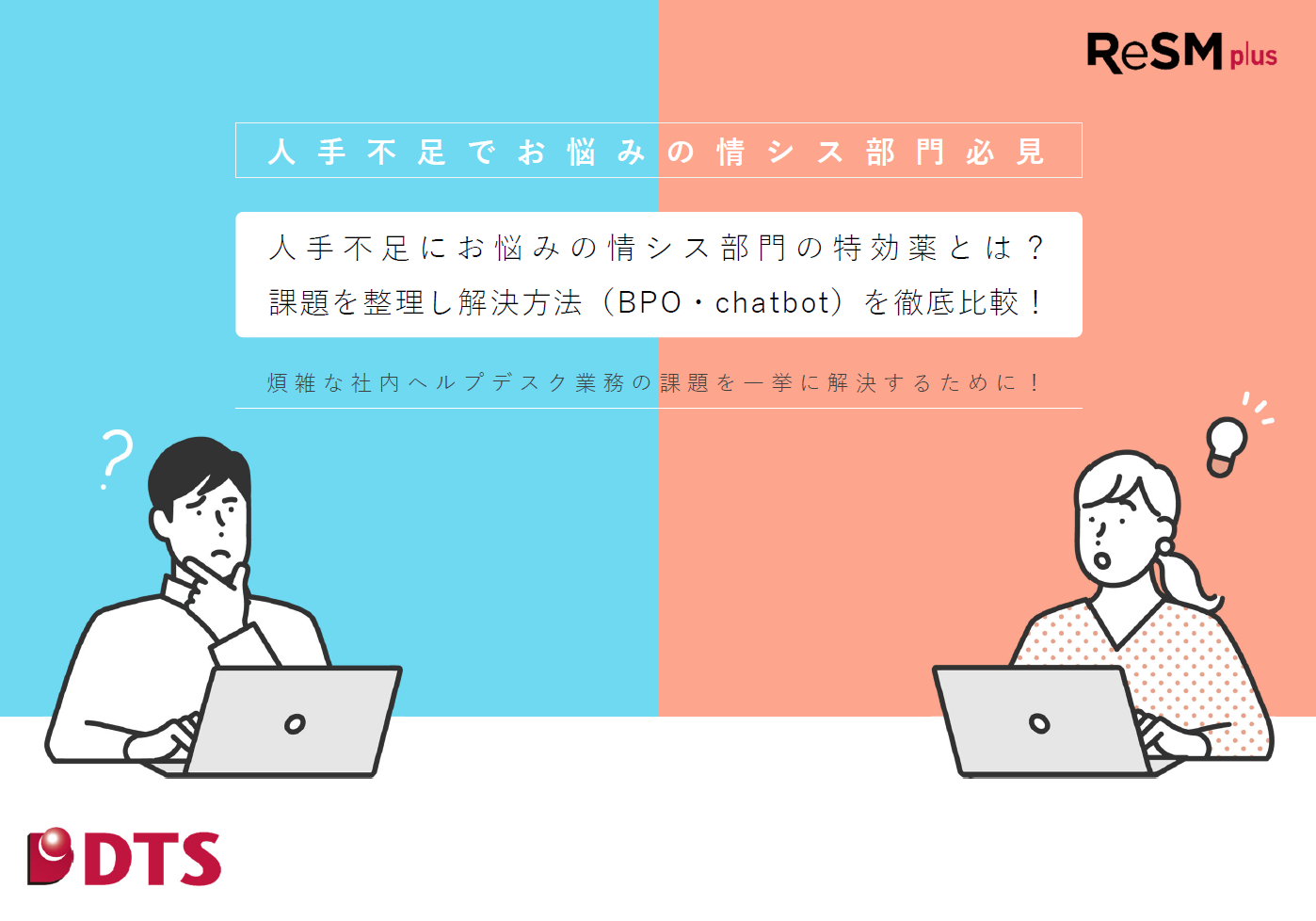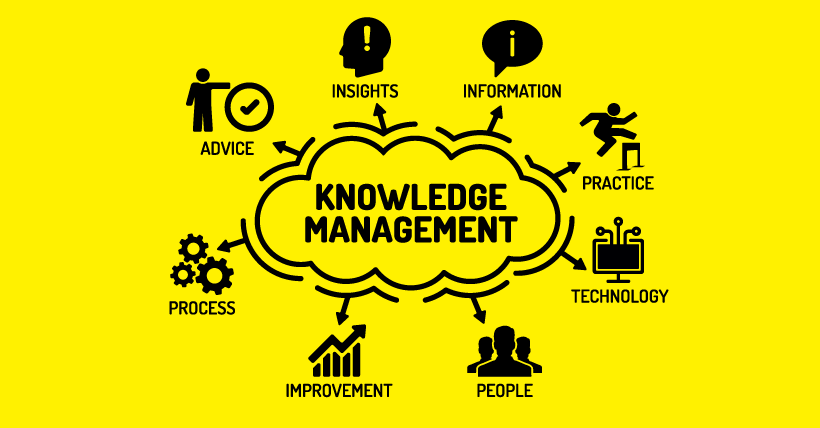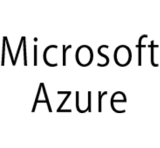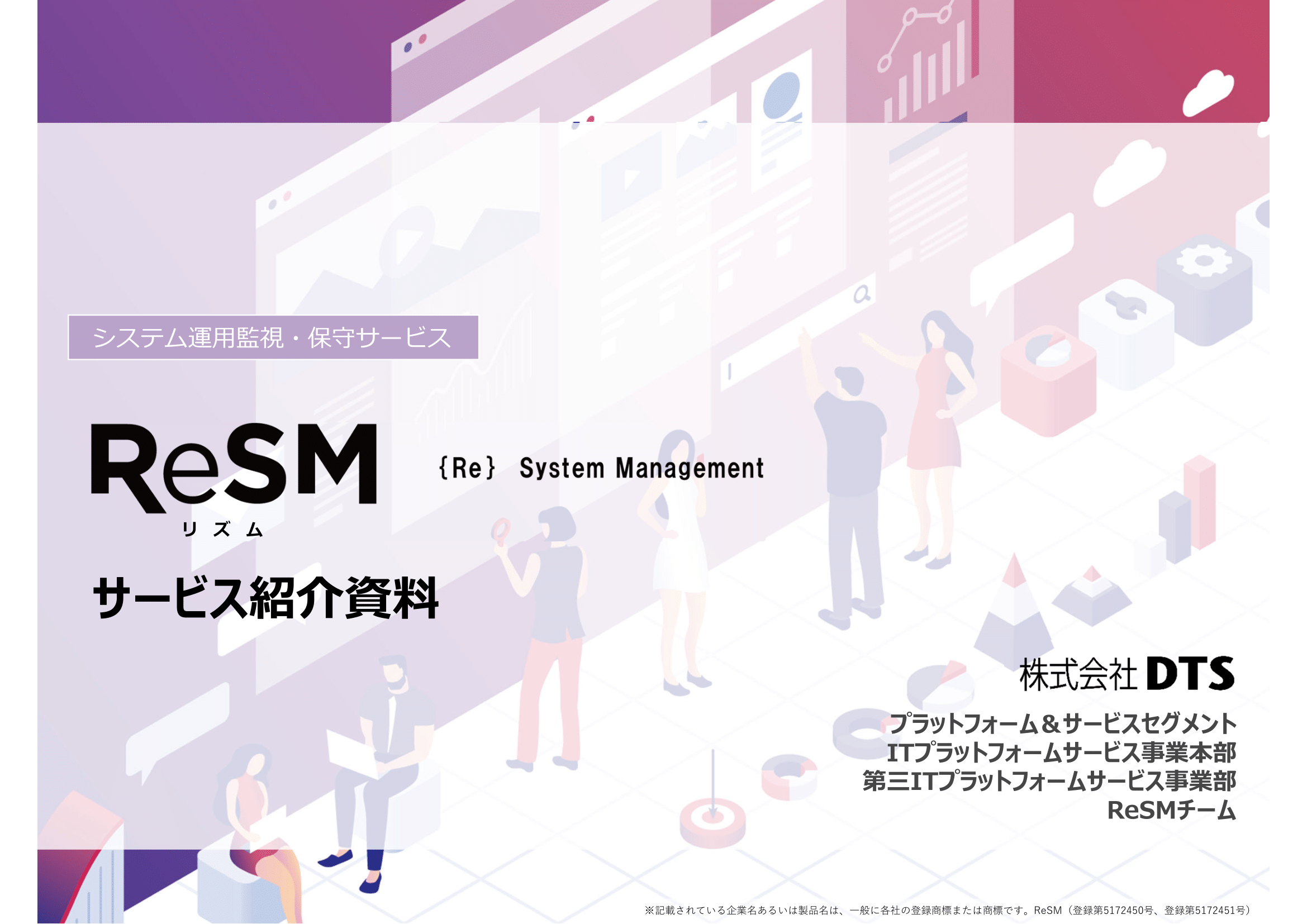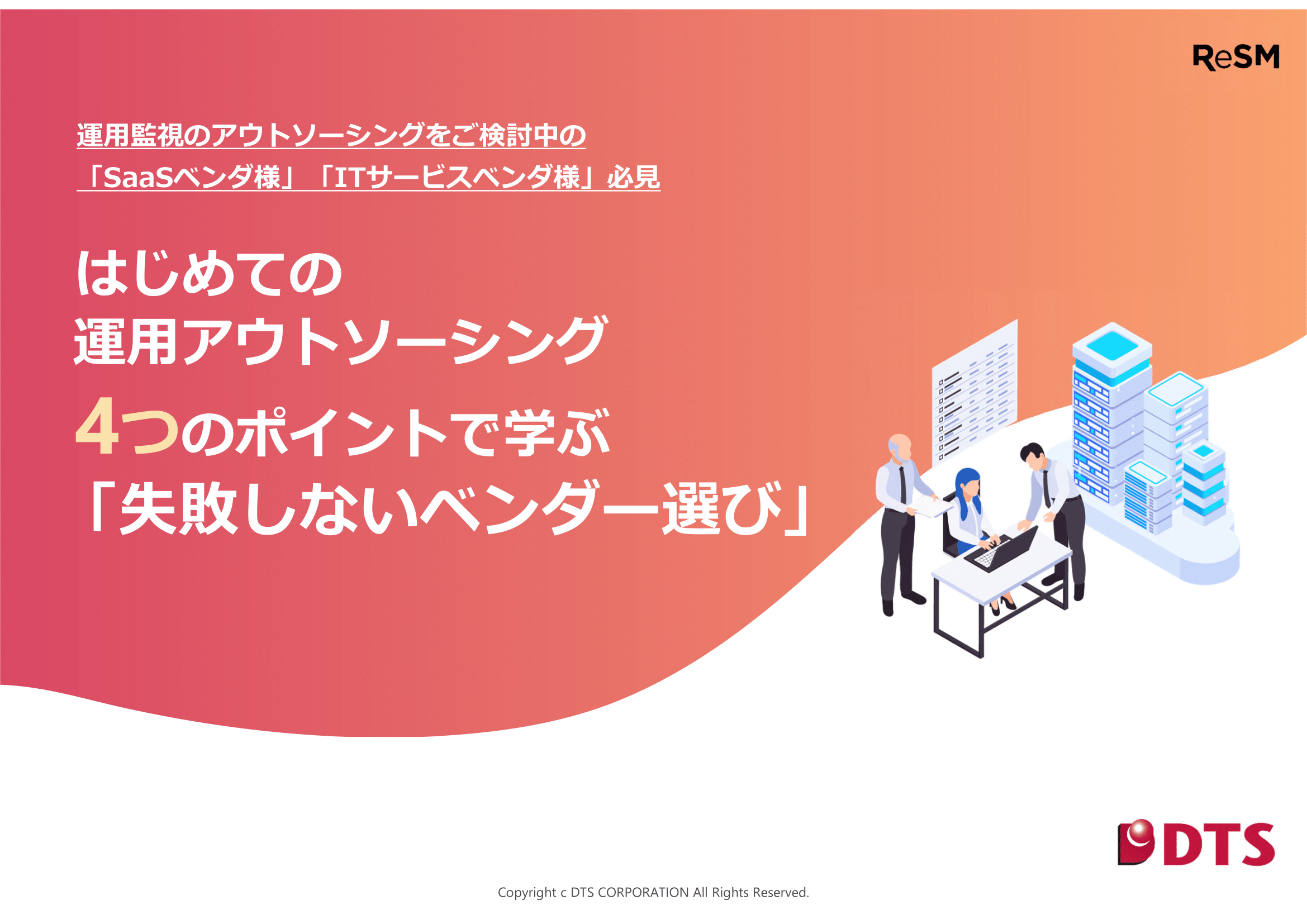サービスデスクとは?ヘルプデスク・コールセンターとの違いを徹底解説

サービスデスクとは?
サービスデスクは、ITサービスの利用者から寄せられる問い合わせや依頼、障害報告を一元的に受け付け、適切に対応・管理する窓口機能です。IT部門における運用管理の中核として、組織全体のITサービスレベル向上に貢献します。
ITILにおけるサービスデスクの定義
サービスデスクとは、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とよばれる、ITサービスマネジメントにおける成功事例をまとめた書籍群で使われている役割で、ITサービスマネジメントの指令塔ともいえます。
ITILでは、ITサービスを提供する上で、ユーザーに疑問やトラブルが生じた場合に問い合わせる単一の窓口としてサービスデスクを設置することが推奨されています。
ITILによれば、サービスデスクは受けた問い合わせに対して単に回答を行うだけでなく、対応の進捗状況についてユーザー側に発信するなど、積極的で双方向的なコミュニケーションを行うことになっています。
サービスデスクには、困ったユーザーがどこに問い合わせれば良いか迷ったり、問い合わせた先でたらい回しにされたりすることを防ぐ目的があるため、これを満たすような体制づくりも必要になってきます。
SPOC(単一窓口)としての役割
サービスデスクは、SPOC(Single Point of Contact)としてすべてのIT関連問い合わせの一元窓口を担います。
これにより、ユーザーにとってはどこに連絡すべきかが明確になり、組織にとっても問い合わせの対応状況を一元的に把握・管理することが可能になります。
| 項目 | 効果・メリット |
|---|---|
| 問い合わせ窓口の一元化 | 対応先の混在による混乱や対応漏れを防止 |
| 対応履歴の集約 | ナレッジの蓄積や品質分析、業務改善への活用が可能 |
| 情報共有の効率化 | 属人化を防ぎ、チーム内でのスムーズな連携が可能 |
| 業務可視化 | KPI分析や工数把握、外部委託管理などの基盤になる |
近年では、チャットボットやセルフサービスポータルとの連携による自動化が進み、SPOCの運用効率がさらに高まっています。
サービスデスクの業務範囲と具体例
サービスデスクの担当範囲は、問い合わせへの対応にとどまらず、IT運用の起点として業務の幅は広範囲にわたります。以下では、代表的な業務を3つ紹介します
問い合わせ対応業務
ユーザーから寄せられる操作方法の質問、システムの不具合報告などに対して、チャット、電話、メールなどを通じて一次対応を行います。
この一次対応では、丁寧なヒアリングと正確な情報提供が求められ、コミュニケーションスキルが重要となります。
例)
- 「アカウントにログインできない」「印刷ができない」など
- 必要に応じてマニュアルを案内、もしくは関連部門へ引き継ぎ
インシデントの受付と分類
トラブルが発生した際、最初に情報を受け取るのもサービスデスクです。
受け付けた内容を以下の観点で分類・整理し、初動対応またはエスカレーションを判断します。
この分類が正確であればあるほど、トラブル解決のスピードと再発防止策の設計精度が向上します。
ナレッジ共有と記録の管理
対応内容や解決策を蓄積・整備し、再利用可能なナレッジとして活用することもサービスデスクの重要な役割です。
- 過去の対応履歴を記録し、同様の問い合わせ時に再利用
- よくある質問をFAQやマニュアルとして社内に公開
- 属人化を防ぎ、チームで共有できるナレッジベースを構築
これにより、同様の問い合わせに対する迅速な対応や、対応品質の平準化が実現できます。
ヘルプデスク・コールセンターとの違い
サービスデスクと混同されやすい概念に、ヘルプデスクやコールセンターがあります。
いずれも問い合わせ対応を担う窓口業務ですが、対象範囲や役割、運用方針において明確な違いがあります。
ヘルプデスクとの違い
ヘルプデスクの主な業務は、ユーザーが商品・サービスを利用する上で生じる疑問やトラブルの解消です。社内ヘルプデスクなら、従業員が業務を行う上で生じる疑問やトラブルを解消します。
これに対し、サービスデスクはITサービスマネジメント(ITSM)の観点で全体を統括・管理する役割を果たす点が大きな違いです。
ヘルプデスクは、ユーザーから受けた問い合わせに対し、調査を行うなどした上で回答を行う業務が中心となります。電話に出た担当者で解決できない場合は、より専門性の高い部門へエスカレーションされ、該当の担当者から回答を行うことがあります。
また、ユーザーがスムーズに業務を行えるよう、マニュアルなどを整備するところまでが業務に含まれます。場合によっては、寄せられた問い合わせや要望を、商品・サービスに反映して改善するところまでを含むケースもあります。
コールセンターとの違い
コールセンターとは、顧客に対して電話業務を行う役割や部署をいい、コールセンター業務はテレマーケティングとよばれることもあります。
電話を受ける業務(インバウンド)と発信する業務(アウトバウンド)があり、インバウンドでは、ヘルプデスクやサービスデスクのように、顧客の疑問やトラブルの問い合わせだけでなく、資料の申し込みや通信販売の購入なども受け付けます。
一方、アウトバウンドでは、営業活動やマーケティングリサーチ、購入のお礼といった目的で電話を発信します。
サービスデスク、ヘルプデスク、コールセンターの機能は、用途や組織規模に応じて併用・分担されるケースも多く見られます。
サービスデスクの主な機能とKPI
サービスデスクは、単に問い合わせを受け付けるだけでなく、ITサービス全体の品質・効率・安定性を高めるための中核的な運用機能を担います。
このセクションでは、主な機能の解説に加え、評価・改善に用いるKPIについても整理します。
インシデント管理とエスカレーション対応
ITサービスにおいてインシデントは避けられない要素です。
サービスデスクでは、インシデントの発生時に迅速かつ的確な初動対応と、必要に応じたエスカレーションを担います。
主な対応フローは以下のとおりです
- ユーザーからの障害報告を受け付ける
- 内容をヒアリングし、影響範囲・緊急度を分類
- 一次対応可能な場合は即時解決
- 対応困難な場合は、適切な技術部門へエスカレーション
- 解決後、対応内容を記録・ナレッジ化
エスカレーションの基準を明文化しておくことが、対応スピードと品質の向上に直結します。
ナレッジ管理・FAQ整備による自己解決支援
ナレッジ管理とは、過去の対応履歴や解決策を体系化し、再利用可能な状態に整備することを指します。ナレッジが充実することで、対応者は迅速に情報にアクセスでき、またユーザー自身も自己解決できるようになります。
具体的には以下の施策が考えられます。
- よくある問い合わせをFAQ化し、ユーザーが自分で解決できるようにする
- マニュアルや手順書を整備し、一次対応の精度を高める
- 過去のトラブル対応を記録し、再発時に素早く再利用できる状態にする
よく使われるKPI
サービスデスクの運用状況は、KPIをもとに可視化・改善できます。
ここでは、代表的な3つのKPIを紹介します。
平均対応時間(AHT/MTTR)
AHT(Average Handling Time)やMTTR(Mean Time to Resolve)は、問い合わせ1件の対応にかかる平均時間を示します。
スピード感はユーザー満足度と直結しており、待たされないかどうかは印象に強く残ります。
これらの指標は、なぜ時間がかかるのかを分解し、業務改善の起点にする指標として活用されます。
顧客満足度(CSAT/NPS)
対応が早くても、ユーザーが満足していなければ意味がありません。
そのため、多くの組織では、対応後にアンケートを実施して満足度を数値化しています。
低評価が続く場合は、対応速度以外にも「説明が分かりづらい」「態度が機械的」など、定性的な不満が蓄積しているサインかもしれません。
初回解決率(FCR)
FCR(First Contact Resolution)は、最初の対応で問題が解決した割合を表します。
この指標は、スキルの成熟度やナレッジの整備状況を映す鏡でもあります。
担当者の知識が属人化していて、他メンバーが対応できない状況では、FCRはなかなか上がりません。逆に、ナレッジが整っていて、誰が対応しても一定水準を保てる状態になれば、FCRは自然と上がります。
再対応が減ることで、ユーザーの満足度も高まり、対応件数の削減にもつながる。まさに好循環を生み出す指標です。
サービスデスクの運用形態と選び方【4タイプ比較】
サービスデスクの導入においては、どこに、どのような体制で設置するかを慎重に設計する必要があります。
その選択肢として代表的なのが、以下の4タイプです。
- ローカルサービスデスク
- 集中型サービスデスク
- バーチャルサービスデスク
- フォロー・ザ・サン型
4つの運用形態とは
各運用形態の概要と特徴を簡潔にまとめます。
| 形態 | 概要 | 主なメリット | 留意点 |
|---|---|---|---|
| ローカル型 | 各拠点に設置し、現地で対応 | 顧客との距離が近く迅速に対応可 | 拠点が多いと運用が煩雑に |
| 集中型 | 一箇所に業務を集約し全体を対応 | リソースの効率活用、標準化が進む | 地域ニーズに応じにくいことも |
| バーチャル型 | 拠点間を仮想的に連携して対応 | 柔軟性が高く、BCP対策にも有効 | IT基盤・運用ルールの整備が必要 |
| フォロー・ザ・サン型 | 地球の時差を利用して24時間体制を構築 | グローバル対応が可能 | オペレーション管理が複雑 |
ローカルサービスデスク
各拠点にサービスデスクを設置し、現地対応を行う方式です。
特に「現場との密な連携が必要」「顔の見える対応を重視する」業態に向いています。
- ユーザーとの距離が近く、状況を即時に把握しやすい
- 拠点間で対応品質にばらつきが出やすく、管理コストが増える
- 一定規模を超えると、集中・バーチャル型への移行が検討されることも多い
集中型サービスデスク
全国・全社の問い合わせを、1つの拠点に集約する方式です。
ITインフラが整った企業や、運用コストを最適化したい場合によく採用されます。
- 業務の標準化と効率化に優れ、スキルの集約も可能
- 地域特性や部門ごとの事情に対応しにくくなるリスクあり
- 応答負荷が一点に集中するため、可用性や体制設計が重要
バーチャルサービスデスク
拠点は分散したまま、仮想的に連携しながら一元対応するモデルです。
ツールやワークフローでつながることで、拠点間の地理的制約を超えた柔軟な運用が可能になります。
- テレワークや地域分散に強く、BCP観点でも有効
- オンプレミス環境では連携が難しく、IT基盤に依存する
- 運用ルールとツール整備が成功の鍵
フォロー・ザ・サン型
世界各国の拠点を時間帯でリレー運用することで、24時間365日の対応を可能にするモデルです。
グローバル企業や、止められないミッションクリティカルなシステムを持つ企業で導入されています。
- 昼間帯での対応を維持できるため、応答品質が安定しやすい
- タイムゾーン間の連携、ドキュメント共有など高度なオペレーション設計が必要
体制構築で抑えるべきポイント
どの形態を選ぶにしても、体制設計の成功にはいくつかの共通ポイントがあります。
1. SLA(サービスレベル合意)の設計
対応速度・範囲・品質基準を明確に定め、関係者間で合意しておくこと。
これがないと、KPI管理や改善の基準が曖昧になります。
2. 人員とスキルの配置
対応難易度やエスカレーション先を考慮して、
- 一次対応:汎用スキル+ナレッジ活用力
- 二次対応:専門スキル+技術的判断力
など、階層ごとのスキルマップを設計することが重要です。
3. ツールとの連携
拠点が分散するほど、チケット管理やナレッジ共有の仕組みが不可欠です。
クラウド型ITSMツールを中心に、チャット・通話・FAQ・レポート機能を統合する設計が求められます。
サービスデスクツールの導入メリットと選定基準
サービスデスクの運用をスムーズに行うためには、専用のITSMツールの導入が不可欠です。
チケット管理・対応状況の可視化・ナレッジ蓄積・レポート作成など、多くの業務を効率化・標準化する役割を果たします。
このセクションでは、ツール導入のメリット、代表的な製品比較、導入時の選定基準について整理します。
情シスの負担軽減・属人化の解消
属人化や運用の煩雑さは、多くのサービスデスクが抱える課題です。
Excelで運用されていたとしても、問い合わせ件数が増えると管理の限界がすぐに訪れます。
そこでツールを導入することで、以下のような効果が期待できます。
- チケットベースで記録・分類・進捗管理が可能に
- 過去の対応情報を検索・再利用でき、対応品質が安定
- KPI(件数、対応時間、満足度など)のトラッキングが可能
サービスデスクツールの比較
以下は、代表的な2つのサービスデスクツールの比較です。企業規模や運用スタイルに応じて、適した選択肢は異なります。
| ツール名 | 特徴 | 適した企業規模 |
|---|---|---|
| Jira Service Management | 開発部門との連携に強く、アジャイルな運用に最適。 | スタートアップ〜中堅企業 |
| ServiceNow | ITIL準拠の本格的ITSMツール。高い拡張性とワークフロー自動化が特長。 | 大企業・グローバル組織 |
▪️Jira Service Management
- 開発プロジェクトとの連携に優れ、チーム横断的な運用が可能
- UIがシンプルで、導入・定着が比較的スムーズ
- 小規模から段階的に始めたい企業に適している
▪️ServiceNow
- 大規模環境での運用を前提に設計されており、複雑な業務プロセスにも対応
- ワークフロー自動化や統合レポート機能が充実
- IT部門だけでなく、人事・総務などの業務にも展開可能
選定基準
ツール選定にあたっては、単なる機能比較ではなく、自社の現状・成熟度・目的に合わせた設計視点が必要です。
以下は主な選定基準です。
1.UI/UXと現場への定着性
導入しても使われなければ意味がありません。現場のITリテラシーや運用負荷に見合ったUI設計かどうかを確認します。
2.ITIL準拠・機能拡張性
将来的な業務拡張や他部門展開を見越して、ITILベースのプロセス連携やAPI連携の有無も検討ポイントになります。
3.導入実績とサポート体制
同業種・同規模での導入事例があるか、トライアル環境の提供があるかなど、ベンダーの信頼性も重要です
ITサービスデスクの進化と今後のトレンド
サービスデスクは問い合わせ対応の窓口から、ITサービス全体の品質と体験を最適化する基盤へと進化しつつあります。
とくに近年は、AI・自動化技術の導入や、ユーザー自身による自己解決を支援する流れが加速しています。
AI・自動化による対応の効率化
サービスデスク業務の中でも、分類・案内・エスカレーション判断といったルーティンは、自動化の対象になりやすい領域です。
特に、次のような領域でAIが活用され始めています。
- チケットの自動分類・優先度付け
- 問い合わせ文の内容からインシデント種別や緊急度を推定し、自動でカテゴリ付けを行う。
- 自動応答・案内チャットボット
- 定型的な問い合わせに対して、ナレッジベースと連携したチャットボットが即時回答。
こうした機能は、対応スピードだけでなく、担当者の工数削減、再発防止などにも波及効果をもたらします。
ユーザー主導のセルフサービス化
もうひとつの大きな流れが、問い合わせを減らすための仕組みづくりです。その中心にあるのが、セルフサービスの強化です。
- FAQやマニュアルをWebポータル上に公開
- 利用者が自ら検索・解決できる環境を整備
- チャットボットによる一次対応
- 夜間や無人時間帯でも、基本的な案内を可能にする
セルフサービスは、問い合わせ数の削減だけでなく、わかりやすい仕組みづくりを通じたユーザー体験の改善にもつながります。
まとめ
サービスデスクは、単なる問い合わせ窓口ではなく、ITサービス全体の安定運用とユーザー体験の質を左右する中核機能です。
人的対応だけに頼るのではなく、標準化や自動化を進め、継続的に改善できるサービスデスク運用体制を構築することが求められます。
適切な設計と運用を通じて、IT部門がより戦略的な業務へシフトするための基盤として、大きな役割を果たすことになるでしょう。
社内ヘルプデスクは、情シス業務の中でも「止められない・減らせない」仕事
PCトラブルの一次対応、アカウント管理、社内ツールの利用方法に関する質問…
社内ヘルプデスクは、緊急性が高く属人化しやすい業務の代表例です。
一件ごとの対応は軽微でも、積み重なれば情シスの時間と集中力を奪ってきます。
多くの企業では、FAQの整備や手順書の作成など、自力で問い合わせを減らす努力を重ねてきたはずです。しかし、結局いつも同じ質問が来て、本質的な負担軽減につながっていないと感じていないでしょうか。
問い合わせ数の削減を目指す社内ヘルプデスク代行サービス「ReSM plus リズムプラス」
ReSMplusは単なる代行ではなく、社内から問い合わせそのものを減らすことを目指すヘルプデスク支援サービスです。属人化やリソース不足に悩む情シス業務を構造的に見直し、「場当たり対応」から「再発防止型対応」への転換を支援します。
数ある社内ヘルプデスクサービスの中でも、ReSMplusが選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。
- 問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産をつくる
- SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
- パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る
それぞれの特徴についてご紹介していきます。
問い合わせ代行で終わらず、貴社だけのナレッジ資産を作る

単に来た問い合わせに対応するのではなく、繰り返される質問を仕組みで減らすことを重視しています。
FAQの整備や定型ナレッジの蓄積、問い合わせ傾向の可視化を通じて、再発防止型の対応体制を構築します。
属人対応に頼らない「仕組みのITサポート」へと進化させます。
SIerとして実績豊富なDTSが運営し、ITサポート経験が豊富なオペレーターが一括対応
ReSM plusは、SIerとして数多くのITインフラ支援を手がけてきたDTSが運営しています。
その実績に裏打ちされたITリテラシーの高いオペレーターが、メール・電話・などウェブ問い合わせフォームなど複数チャネルでの一括対応を実現。
「話が通じるオペレーターが対応してくれる安心感」が、多くの企業から支持されています。
パスワード初期化やアカウント作成といった問い合わせの発生源ごと巻き取る

PCセットアップやアカウント発行、IT資産管理…
こうした問い合わせを生む原因そのものを巻き取ることで、対応件数を根本から減らす設計が可能です。
業務フローの一部をReSM plusに預けることで、情シスの予防的な働き方を支援します。
この記事の著者
関連するサービス
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。