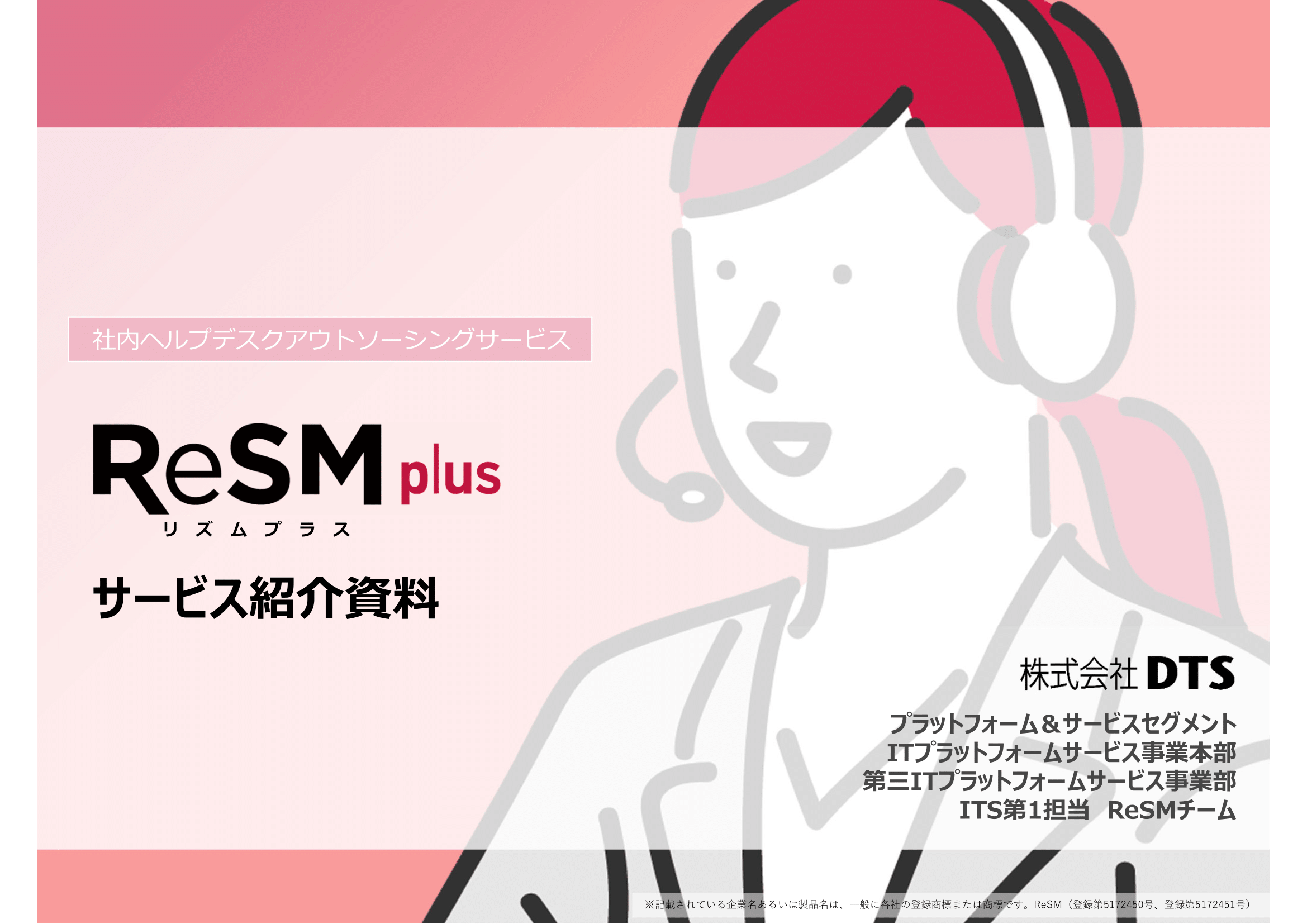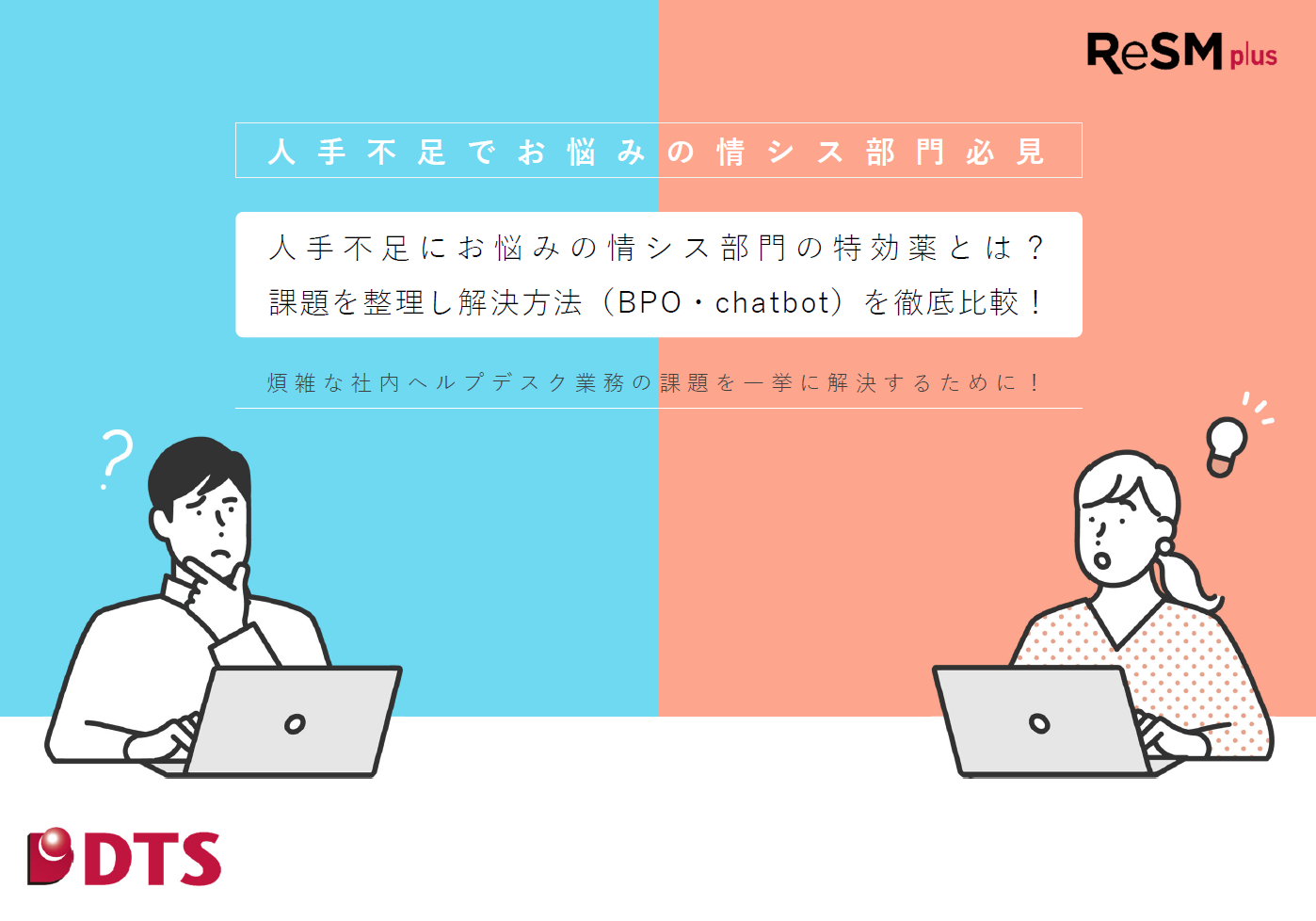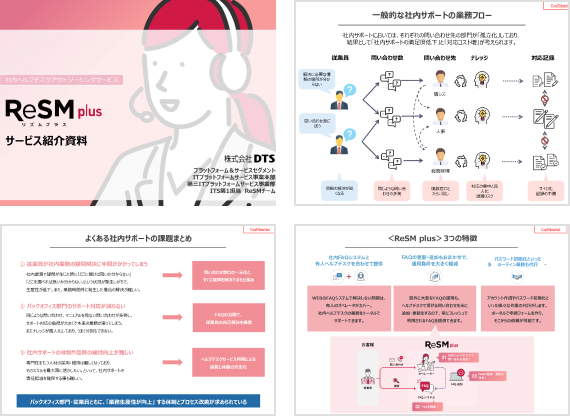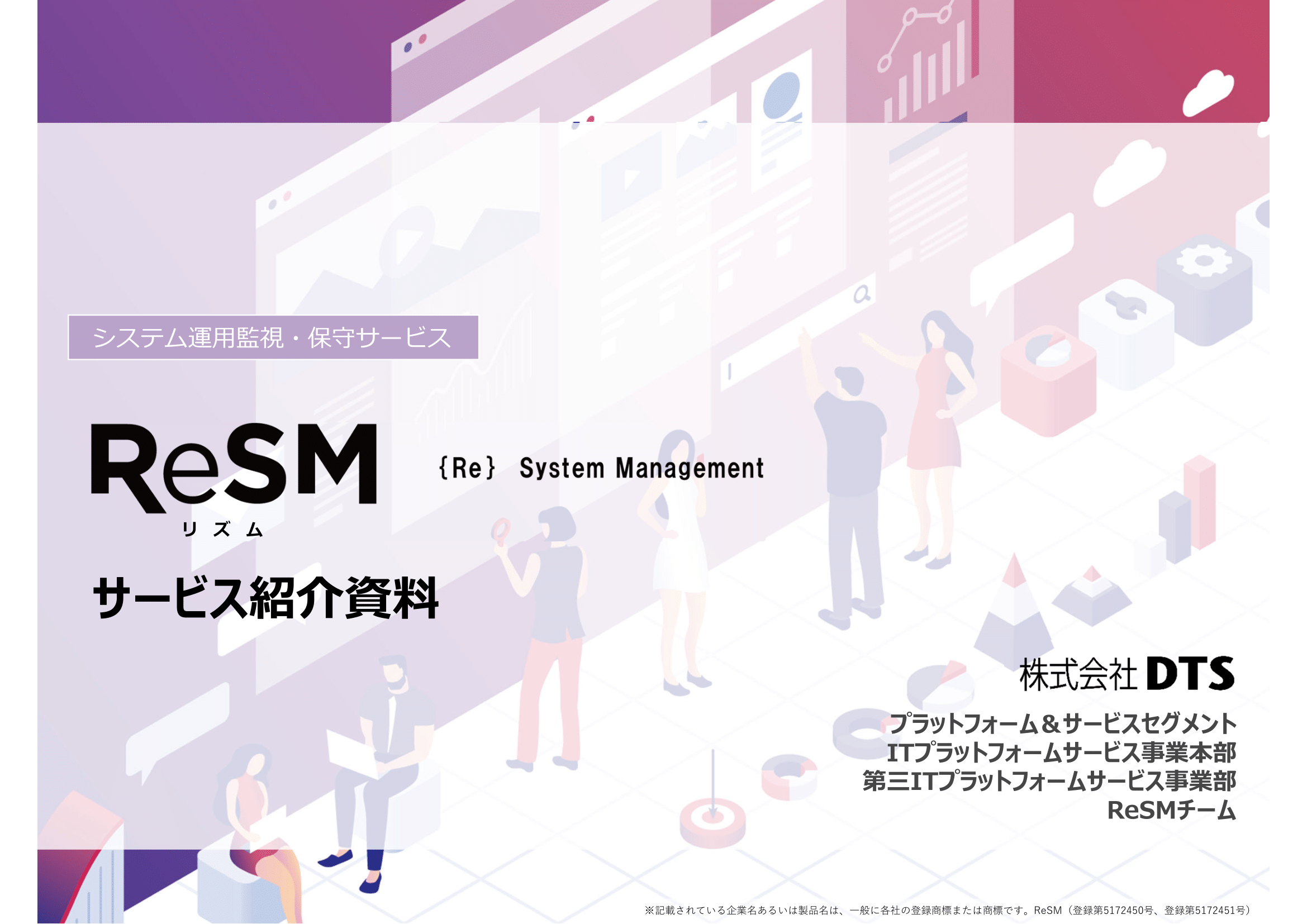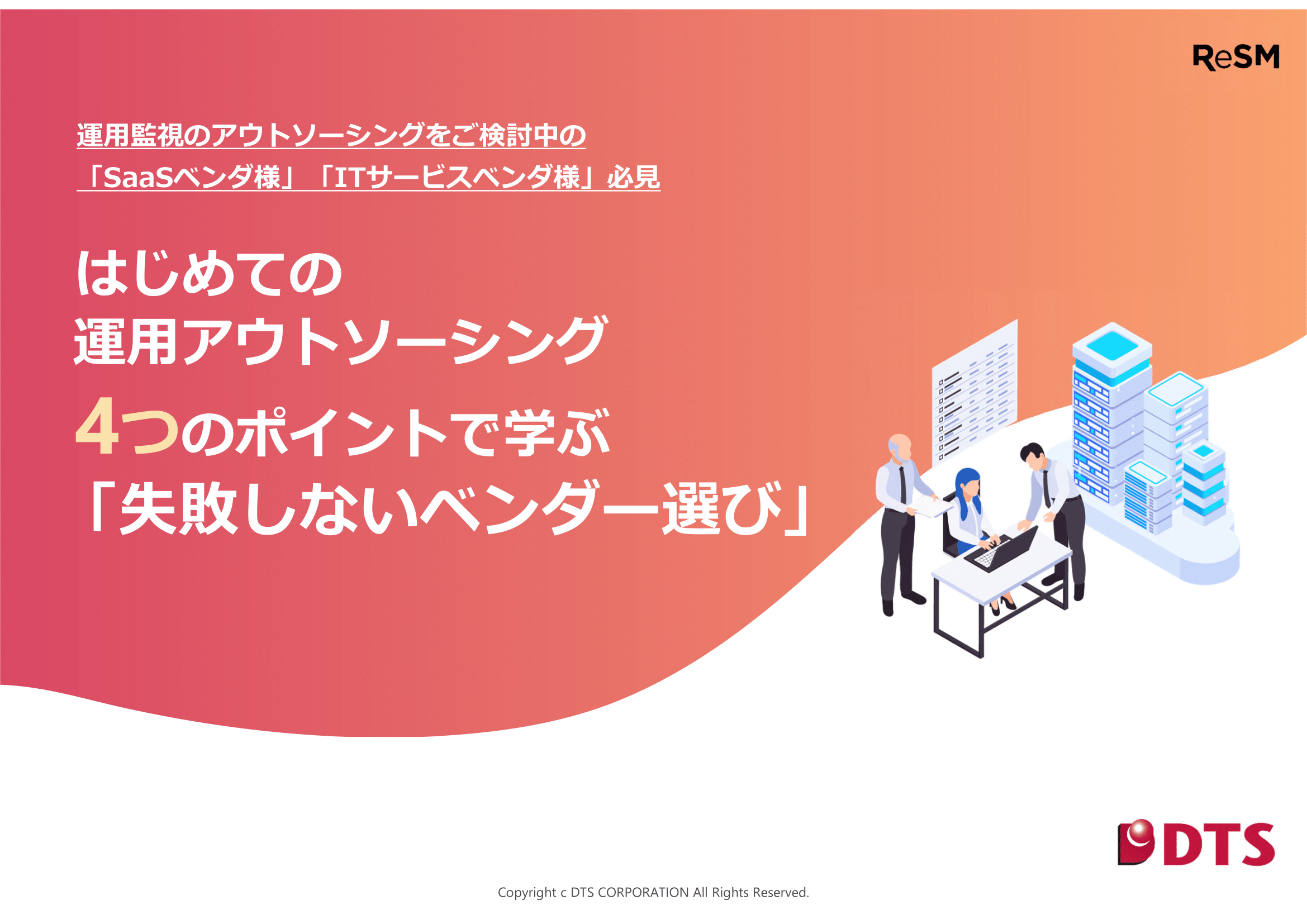社内IT担当が足りない?情シスアウトソーシングで解決できること・できないこと

ヘルプデスクの電話が止まず、障害通知が深夜まで鳴り続ける…
情報システム部門(情シス)では、ヘルプデスク対応やPCキッティング、アカウント発行といった定型業務に追われ、IT戦略の立案やDX推進に必要な時間を確保できないケースが少なくありません。
こうした課題の解決手段として注目されているのが「情シスアウトソーシング」について解説します。
情シスアウトソーシングとは?
企業のIT運用を内製だけで賄うことには限界があります。人員不足やスキルの偏りから、突発的なトラブル対応に追われ、本来注力すべき戦略的プロジェクトが停滞してしまうことも少なくありません。こうした状況を打破する手段のひとつが「情シスアウトソーシング」です。
本章では、その概要と導入検討時のポイントをコンパクトに解説します。
アウトソーシングは「コスト削減策」と見なされがちですが、最大の利点は、社内リソースに“時間的余白”を生み出し、それを戦略分野に再投資できる点にあります。空いた時間をDX推進やセキュリティ強化に再配分することで、情シスはコストセンターから、事業成長を支える推進役へと進化できます。
なぜ今「情シス業務のアウトソーシング」が注目されるのか
近年、中小企業を中心に情シスアウトソーシングの導入が進んでいる背景には、次のような3つの構造課題があります。
| 課題 | 現状・影響 | アウトソーシングで補える点 |
|---|---|---|
| 慢性的なIT人材不足 | 採用難で要員が確保できず、既存スタッフに負荷集中 | 外部人材を活用し、業務負荷を平準化 |
| 運用の複雑化 | オンプレ・クラウド・SaaS が混在し、運用ドキュメントも肥大化 | 専門会社の標準化プロセスで管理を簡素化・品質を均一化 |
| DX / セキュリティに対する対応要請 | 攻め(DX 推進)と守り(セキュリティ強化)を並行で実施する必要 | 定型運用を外部化し、社内リソースを戦略・改革タスクへ再配分 |
IT部門にはクラウド移行やゼロトラスト対応など、専門性の高いプロジェクトが次々に求められています。人材不足と時間的制約の中で、情シスのアウトソーシングは即効性のある現実的な解決策として注目されています。
アウトソーシングできる主な業務
手順が確立されている定型業務は、外部パートナーへ移管しても品質が揺らぎません。代表例は次のとおりです。
- PC キッティング
- 設定手順とテスト項目が決まっているため、担当者のスキル差が成果にほぼ影響しない。
- アカウント発行・権限変更
- 申請フローと承認ルールを共有すれば、翌日からでも引き渡し可能。
- 社内資産管理
- ハードウェア/ライセンス台帳の更新など、ルーチンワークが中心。
中でも 社内ヘルプデスクは情シスの工数を最も圧迫します。
問い合わせは いつ、何件来るかわからず、「パスワードを忘れた」「プリンタが使えない」といった反復的な内容が大半です。
それでも回答は即時性が求められ、情シス担当者は作業の手を止めて問い合わせ対応せざるを得ません。
FAQを整備しても、項目追加や改訂に時間を取られ、結局は更新が滞り、「読むより聞いたほうが早い」という状況に逆戻りしがちです。特に「即時対応が求められるうえに感謝されにくい」ヘルプデスク業務は、アウトソーシングによる負荷軽減効果が最も大きい領域です。
情シスをアウトソーシングすべき企業の特徴と課題
小規模な情シスに限らず、「ひとり情シス」の企業や中堅・急成長企業にとっても、アウトソーシングは有効な選択肢です。これらの企業に共通するのは、日常運用、DX推進、インフラ更新、セキュリティ強化といった複数の課題が同時並行で進み、慢性的な時間不足に陥っている点です。このような状況下では、外部リソースによる体制補完のメリットが非常に大きくなります。
ひとりだけ情シス
担当者が不在になると業務が完全に停止してしまうリスクがあります。障害対応やPCキッティングなど、定型業務を外部に委託することで、まずは「止まらない体制」の構築が可能になります。
中堅企業
DXとセキュリティ強化を並行して進める中で、夜間対応や拠点ごとの問い合わせ対応などは外部に任せ、情シスは改善サイクルの設計や戦略業務に集中できる環境を整えます。
急成長企業
急激な社員数の増加により、アカウント発行やヘルプデスク対応の負荷が急増します。こうしたピークタイムの工数を外部リソースで吸収することで、成長速度を損なうことなく運用を継続できます。
このような過密スケジュールの中で、日中は問い合わせ対応、夕方以降にクラウド移行プロジェクトの打ち合わせを行うといった働き方が常態化すると、タスクの「質的負債」が蓄積し、プロジェクトの遅延や業務の疲弊を招きかねません。
アウトソーシングのポイント
- 定型業務を外部に委託し、「時間の余白」を確保する。
- その余白をDXやセキュリティ強化に再投資するロードマップを設計する。
- 情シスアウトソーシングは、単なる工数削減ではなく、組織の改革を支える体制補完の起点となる。
もちろん、アウトソーシングしたからといって、すべての課題が自動的に解決するわけではありません。しかし、時間的余白がなければ、そもそも改革を始めることすらできません。外部委託によって生まれた余白をどう活用するか。それこそが、成果の分かれ目となります。
たとえば、ある製造業の企業では、ヘルプデスクを外部に委託することで担当者の時間を確保し、その時間を使って製造ラインのセンサー値の分析に着手しました。結果として、半年で不良率の改善に成功しています。
情シスアウトソーシングのメリットとデメリット
メリット
コア業務に集中できる
キッティングやヘルプデスクなどの定型作業を外部に出すことで、社内情シスは DX 推進・システム改善などの高付加価値タスクに時間を振り向けられます。
コストを抑えつつ最適な体制が築ける
必要な業務だけを契約すれば、人件費や教育費を抑えつつリソースを確保できます。採用コスト 300 万円相当を、月額 20 万円程度の委託費で代替できた事例もあります。
運用品質が向上する
専門のアウトソーサーがベストプラクティスを用いて運用するため、問い合わせは短時間で解決し、ユーザー体験は揺らぎません。加えて、標準手順と SLA により応答速度と一次解決率が平準化されます。KPIを明確に設定すれば、運用品質を継続的に管理・改善できます。
デメリット
セキュリティ
社外にデータを預ける以上、情報漏洩や権限管理の不備が懸念されます。NDA 締結、ゼロトラスト設計、四半期監査を必ず行いましょう。
コミュニケーションギャップ
窓口が複数あると要件齟齬や対応遅延が起こります。窓口を一本化し、週次レポートや月次レビューで進捗を見える化することが有効です。
ノウハウ流出・ベンダー依存
ノウハウが外部に偏ると、ベンダー交代が難しくなります。運用手順と障害ログを社内ナレッジに定期反映し、一次解決率・平均応答時間を契約 KPI に明記して、成果を数値で管理することが主導権維持の鍵です。
アウトソーシングできる業務とできない業務の判断ポイント
情シス業務は大きく分けて「ノンコア業務(定型的で標準化しやすいもの)」と「コア業務(経営判断や全社設計に関わるもの)」に分けられます。
外注に適した情シスのノンコア業務
定型化され、影響範囲が限定的な業務は外注向きです。代表例は次のとおりです。
- PC キッティング
機種ごとのイメージ展開や動作確認など、手順書が整っていれば再現性が高く、短期間での引き継ぎも可能です。 - 社内ヘルプデスク
「プリンターが動かない」「パスワードを忘れた」といった反復的な問い合わせが突発的に発生し、即時対応が求められます。FAQを整備しても更新が追いつかず、「読むより聞くほうが早い」という状態に戻ってしまうケースも多い業務です。対応の即時性・件数の多さ・感謝されにくさといった「三重の負荷」を抱える代表的な業務であり、外部委託によって情シスの負荷軽減が大きく期待できます。 - IT 資産管理
ハードウェアやライセンス台帳の更新など、ルール化しやすく、人によるバラつきが出にくい業務です。手順通りに処理すれば一定の品質が保たれるため、外部委託しやすい典型です。
これらの業務は手順が標準化しやすく、失敗しても事業全体への影響が比較的限定的であり、応答時間や一次解決率といったKPIで成果が数値化しやすい点も、外部化に適している理由です。
社内に残すべき情シスのコア業務
一方で、経営方針や全社的なIT基盤の設計など、企業の中枢に関わる業務は、社内に留めておくべきです。こうした業務は業務知識だけでなく、企業文化や中長期戦略との整合性を深く理解していなければ適切に遂行できません。
- IT 戦略立案とロードマップ策定
中期経営計画と整合性のある技術投資やシステム刷新の方針づくりは、情シスが果たすべき最重要ミッションです。テクノロジーの選定一つで事業の成長性が左右される場面もあり、外部に任せきるべきではありません。 - システム設計方針・要件定義・ベンダー選定
全社業務を俯瞰し、自社特有のプロセスにフィットするシステムを設計するには、深い業務理解と社内関係者との信頼関係が不可欠です。要件定義やベンダー選定の判断軸には、社内事情のニュアンスを加味する必要があり、社外委託は難しい分野です。 - 業務部門と連携した改善活動
現場から吸い上げた課題をもとに業務フローを再設計する活動は、部署横断のハブ機能として情シスが担うべき領域です。業務部門との連携力や現場感覚が求められるため、継続的に社内に機能を残すことが望ましいです。
これらの業務は「現場との接点」と「経営への接続」の両方を内包しており、単なるオペレーションではなく、企業価値そのものを左右する設計業務です。外部の知見を一部活用することは可能でも、最終的な判断・設計は社内主導で行うべきでしょう。
このように、アウトソーシングすべき業務と社内に残すべき業務は、「定型性」や「再現性」だけでなく、「経営判断に対する影響の大きさ」や「企業独自の文脈への適応性」を軸に見極めることが重要です。
情シスアウトソーシングの費用体系
従量課金と定額制の本質的な違い
情シスアウトソーシングの料金モデルは、従量課金制と 定額制の 2種類が主流です。
従量課金は「使った分だけ支払う」ため無駄が少ない反面、繁忙期には請求額が急増し、予算管理が難しくなります。対して定額制は「月◯時間まで一律」なので安心感がありますが、稼働が上限に届かなければ払い過ぎ、超えると追加料金やサービス停止が発生する。ここで発注側と受注側の利害が食い違います。
この利害のズレを解消する鍵は、「時間を減らすほど双方が得をする」メカニズムを契約に盛り込むことです。
たとえば弊社のReSM plusは定額型のヘルプデスクですが、対応内容を自動でFAQへ反映させて同じ質問そのものを削減します。問い合わせ件数が減ればベンダーはオペレーションコストを下げられ、発注側は情シス工数を取り戻せる──両者が同じ方向にメリットを感じる構造です。
こうした仕組みの有無を確認したうえで、見積もりを経営層へ示す際には「月○万円=情シス工数△時間の買い戻し」という「時間通貨」に言い換えて説明すると、従量課金と定額制の本質的な違いとインセンティブ設計の重要性が直感的に伝わります。
アウトソーシング会社の選び方と比較ポイント
アウトソーシング会社を選ぶ際は、成功事例よりも、実際の現場力とトラブル対応の姿勢を見極めることが肝心です。
実績の質
まず注視したいのは実績の質(例:同業界・同規模の導入経験があるか)という点です。似た環境での運用経験が豊富な会社ほど、業務理解が深く、立ち上がりも速くなります。
対応範囲の広さと柔軟性
ヘルプデスクだけで完結するのか、資産管理やクラウド運用まで面倒を見られるのか。加えて「契約途中で範囲を拡張・縮小できるか」を聞いておくと、将来の組織変化にも対応しやすくなります。
サポート体制
24 時間対応や専任エンジニアの配置、有事のエスカレーション手順を具体的に示せるかが重要です。物理常駐が必要な業務なのか、それともリモート支援で十分なのか──拠点数や夜間運用の有無に応じてハイブリッド案を提示できる会社は、提案力とリソース管理の両面で信頼がおけます。
ベンダー依存のリスク管理
手順書や障害ログを社内に還流させる運用を提案できるか、契約上のナレッジ開示条項が明確かを事前に確認しておくと、将来の乗り換えコストを抑えられます。
こうした観点を深掘りするうえでは、ベンダーの現場力や柔軟性、将来的な拡張性などを見極める必要があります。評価の際には、以下のような具体的な質問を通じて、相手の対応力や提案姿勢を確認することが有効です。
- これまでで最も困難だった導入事例は何か?その際にどのように乗り越えたのか?
-
困難な状況下での対応力や柔軟性、学習姿勢を確認できます。
- 担当チームの構成とバックアップ体制はどうなっているか?
-
属人性の有無や、緊急時の対応力を把握する上で重要です。
- 想定される課題に対して、どのような解決策を講じるか?
-
提案内容の現実性や、自社業務への理解度が表れます。
- 規模が2倍になった場合、契約条件や対応体制はどのように変化するか?
-
将来的なスケーラビリティや費用構造の柔軟性を確認する視点です。
- この見積もりを、ITに詳しくない経営層にどう説明するか?
-
論理的かつシンプルに説明できる力があるかどうかは、現場担当者とのコミュニケーションの滑らかさにも影響します。
また、近年では「生成AIをどのように運用に取り入れているか」を確認することも有効です。AIを単なる話題性ではなく実務レベルで活用しているパートナーであれば、契約期間中も継続的に運用改善やコスト最適化が期待できます。
成功事例に学ぶ、情シスアウトソーシング
情シス業務の外部化に取り組む企業を対象としたヒアリングからは、業種や規模を問わず共通した成功パターンが見えてきます。以下に示す2社は、その典型的な事例です。
小売業(全国展開チェーン)
365日発生する店舗からの問い合わせ対応を外部ヘルプデスクに移管し、情シス部門は在庫管理システムの最適化に注力しました。その結果、半年以内に店舗間の商品移動回数および滞留在庫量が減少し、在庫回転率の大幅な改善が実現しました。
日用品メーカー
月次で発生するPCキッティング業務をアウトソーシングすることで、情シスは生産ラインのセンサー値を可視化するダッシュボードの開発に注力。ライン責任者によるリアルタイムな稼働状況の把握が可能となり、設備停止の予兆検知が早まり、不良率の継続的な低下に貢献しました。
成功事例に共通する「時間再投資」モデル
成功企業に共通するポイントは、「外部化によって確保した時間を、より高付加価値な業務に再投資している点」にあります。具体的には、以下の3要素がロードマップに組み込まれています。
- 反復的かつオンデマンド性の高い運用を外部化
- 例:ヘルプデスク、PCキッティング、アカウント・権限管理など。標準化しやすく、成果指標(KPI)で管理しやすい業務を対象とする。
- 確保した時間をKPIを押し上げる業務に投下
- DX推進、在庫最適化、設備稼働の可視化など、事業インパクトの大きな領域にリソースを集中させる。
- パートナーとナレッジを循環させる仕組みの構築
- FAQの自動化や障害ログの共有を通じて、問い合わせ件数そのものを削減し、両者のコスト構造を同時に改善する。
これらの要素を初期段階からロードマップに組み込み、「確保した時間をどこに再投資するのか」を明確に定めておくことが、成果につながる共通要因です。生成AIの進化により外部化のハードルがさらに下がる現在、「どの業務をいつ外に出し、空いたリソースをどこに再配置するか」という判断こそが、今後のIT部門の価値を左右する重要な分岐点となります。
まとめ
情シスアウトソーシングは、単なる「外注」や「コスト削減策」ではありません。
本質は、限られた社内リソースから“時間”という貴重な資産を捻出し、それを成長領域に再投資するための構造改革です。
業務が複雑化し、DXやセキュリティ対応といった“攻め”と“守り”の両立が求められる中で、限られた人員・時間のなかで全てを自前で担い続けることは、もはや非現実的です。
外部委託によって生まれた余白をどう使うか。その問いに答えを持っているかどうかが、成功と失敗を分ける分岐点になります。
これから情シスアウトソーシングを検討する企業にとって、最も大切なのは、「何を任せるか」ではなく、「何を取り戻すために任せるのか」を明確にすることです。
この記事の著者
お問い合わせ
依頼内容に迷っているときは、課題の整理からお手伝いします。
まずはお悩みをご相談ください。
-
システム運用監視・保守サービスReSM(リズム)ご紹介資料
クラウドの導入から24時間365日のシステム運用監視まで、ITシステムのインフラをトータルでサポートするReSM(リズム)サービスについて詳しく説明します。
-
4つのポイントで学ぶ「失敗しないベンダー選び」
運用アウトソーシングを成功させる第一歩は、サービスベンダーの選択です。この資料ではサービスベンダーを選択するポイントを4つ紹介します。